本ブックガイド執筆者(以下「筆者」)はわが国近現代史、特に昭和戦前期を専門とする研究者である。「昭和戦前期」の20年だけでずいぶん色々論点があるのだが、やはりそうした論点が収斂するところは「わが国はなぜ中国と、そしてさらにはアメリカとの戦争を選択したのか」という命題である。
戦後しばらくは「軍部が暴走して無謀な戦争を引き起こした」「近代日本国家そのものが侵略性をもっていた」といった歴史観が学界・ジャーナリズム界で大勢を占めていた。その中で明治日本の苦悩と奮闘を描いた不朽の名作『坂の上の雲』を著す一方、昭和初期において往時の政府から独立した〈統帥権〉を振りかざす軍部によりわが国は”魔法の森”で覆われ破滅の戦争へと駆り立てたとする司馬遼太郎の歴史観(平たく言えば、明治期は立派な軍人が多かったが昭和は…といういわゆる司馬史観)も一定の支持を得た。
しかし最新資料やそれにもとづく近年の再解釈は、そうした従来のテーゼからの脱却を求めている。思想的傾向やあの戦争の正当性の是非に対する見解の相違などを超えて、世界を相手に戦った最初で最後の総力戦へとわが国をつき動かしたものは一体何であったのかが改めて、大々的に問い直されているのだ(参考まで〈統帥権〉については秦郁彦『統帥権と帝国陸海軍の時代』(平凡社新書、2006.2)、二・二六事件以降復活し軍部に内閣の生殺与奪を握らせたとされる〈軍部大臣現役武官制〉については筒井清忠『昭和十年代の陸軍と政治-軍部大臣現役武官制の虚像と実像』(岩波書店、2007.12)が従来のものと一線を画した興味深い解釈を示している)。
さて敗戦から65年たつ本年もそうしたテーマに取り組んだ書籍が多数刊行されているが、今回は比較的手に取りやすい新書を3冊ほど紹介したい。著者は偶然いずれも筆者と接点のある方々だが、まず4月に出版された(1)別宮暖朗『日本陸軍の栄光と転落』(文春新書)―― 膨大な史料を駆使した歴史サイト「第一次大戦」を主宰し、独自の切り口が定評の歴史評論家(元エコノミスト)が、参謀本部の役割・海軍との確執・統帥権問題などを通して日本型組織の欠陥を問うたものである。
| (1) |
 | 書名:帝国陸軍の栄光と転落 (文春新書) 著者:別宮暖朗 出版社:文藝春秋 出版年:2010年 |
この書名を聞いてまず思い出したのは、齋藤健『転落の歴史に何を見るか -奉天会戦からノモンハン事件へ』(ちくま新書、2002.3)。日米自動車交渉も現場で担当した現役経産官僚であった齋藤氏(現在は自民党衆議院議員)がわが国官僚組織の問題点を指摘するのに、皇帝に直接諫言して反逆罪で斬首されぬよう『史記』をもって忠言した司馬遷よろしくわが国(特に軍の)官僚が明治~昭和期という「歴史」を舞台にどのように変質していったかを考察し忠告するものである。その中で福沢諭吉・大隈重信・原敬はじめ政/官/財/メディア各業界にまたがって卓越した業績を残す〈ジェネラリスト〉の存在を挙げて、それが幕末~明治初期つまり近代日本軍の士官養成システム(〈スペシャリスト〉を量産)確立前にしか生み出されなかったことを指摘。日露戦争では政戦指導者たるジェネラリスト(幕末の武士階級出身)と現場指揮官たるスペシャリスト(陸軍士官学校/海軍兵学校出身)の絶妙のコンビネーションが劇的な勝利をもたらした一方で、昭和の戦争においては指導者側も現場も〈スペシャリスト〉ばかりになってしまい大所高所から大戦略を構築する人材に欠けていたとしている。奉天会戦(1905)~ノモンハン事件(1939)の間あらゆる層で「改革」が叫ばれながらも長期的にはそれが実を結ばなかったこと、そしてロングセラー『失敗の本質 -日本軍の組織論的研究』(ダイヤモンド社、1984.5のち 中公文庫、1991.8)のテーゼを基底に置く日本軍の意思決定過程や責任所在の不明瞭さこそ、「失われた10年」を経た現在の日本の組織にも当てはまりませんか…といった問題提起は重い。司馬史観とは一線を画して先述〈軍部大臣現役武官制〉復活が軍部のさらなる台頭をもたらしたのではなく、むしろ既に軍部が台頭していたからこそ制度復活したのだというようにシステムよりも意思決定現場における〈組織風土〉に左右されてしまう実態を説くのも現役官僚ならでは。
さて本題の別宮書に戻ると、こちらは明治初期にドイツの影響を強く受けた陸軍大学校(関ヶ原の戦いの布陣を見て即座に「西軍の勝ち」と言ったことで知られるドイツ人招聘教官メッケルは実は本国でも二流参謀)出身の”エリート参謀”にまず疑問の目を向けている。日露戦争では「参謀たちの作戦計画の失敗を補う将軍が一体、幾多帝国陸軍にいたことか」(p.144)と乃木希典・秋山好古ら現場指揮官の優秀性を特筆している(乃木の軍事的才能を再評価したものとしては兵頭二十八との共著『「坂の上の雲」では分からない旅順攻防戦』(並木書房、2004.3))。
〈統帥権〉の問題では、吉野作造東京帝国大学教授による軍部批判「帷幄上奏に就て」(1922)について「軍部大臣が勝手にやっていることを、明治憲法自体の欠陥であるかのように述べたため、その批判意図とは別に、二重政府が憲法から導かれるように思い込ませ、軍の立場をかえって強化するのに益したように思える」(p.164)「吉野作造の平時における二重政府論批判を逆手にとって、昭和の陸軍(軍人)は統帥権を、平時においても政府から独立してもつと主張しだしたのである」(p.176)と、戦前における憲政の守護神がもたらした言説効果に対する再考をうながしている。
また齋藤書でも〈組織風土〉が重視されていたが、こちらは加えて〈思潮〉、特に「昭和の陸軍軍人たちは、ドイツ参謀本部を手本とするだけでなく、ドイツの社会主義をも手本とした」(p.8)ことにも強く焦点をあてている。一部の軍人が革新官僚と手を組み国家総動員の統制経済体制を実現しようとする過程で「どこの国の軍人でも叫ぶ「政治は作戦に介入するな」ではなく、みずからが政治に飛び込」(p.9)んだのが実態であったというわけである。巷間いわれる陸軍「皇道派」と「統制派」の対立において前者が実力行使辞さずとの姿勢で二・二六事件を起こし、後者がそれを処理したうえで合法的権力獲得を目指したというのが教科書的理解であろうが、別宮氏は(後者の首魁である)「永田自身が暴走の牽引役であった」(p.199)としてそのドイツ戦争経済体制導入論に対し冷ややかな目を向けている。その二・二六事件についても「どこの国の軍人が、財閥の横暴や農村の疲弊といった中傷的な題目で、自分たちの理想とせねばならない戦争ヒーロー(筆者注: 日露戦争時に指揮官として英雄視された渡辺錠太郎教育総監や鈴木貫太郎侍従長)を殺傷するのか」(p.201)とにべもない。
また広田弘毅内閣総辞職(1937.1)後に予備役陸軍大将宇垣一成の組閣が陸軍上層部により阻止されたことによる「宇垣内閣流産」は、「今日に至るまでの官僚社会に決定的な影響を与えた事件」(p.214)であるという。これによりわが国官僚社会で「現役主義」が確立して「人事の実権は大臣を飛ばして完全に局長クラスに移った」ことで、現代でも「中央官庁の局長クラスが大臣をさしおき、事務次官を自らが決定できると錯覚している」(p.215)状態は、”政治主導”を掲げる民主党政権の行く末を考えるうえで単なる歴史上の事象というだけではすまされないであろう。
次に、6月に出版された(2)戸部良一『外務省革新派 -世界新秩序の幻影』(中公新書)――『ピース・フィーラー -支那事変和平工作の群像』(論創社、1991.8)として書籍化された博士論文で支那事変期和平工作の第一人者としての地位を不動のものとし、また『日本陸軍と中国 -「支那通」にみる夢と蹉跌』(講談社選書メチエ、1999.12)では辛亥革命に共感し日中提携を志した「支那通」を擁する日本陸軍が支那事変を泥沼化させてゆくというジレンマの実相を論じた筆者は、先掲『失敗の本質』の共著者でもある。
| (2) |
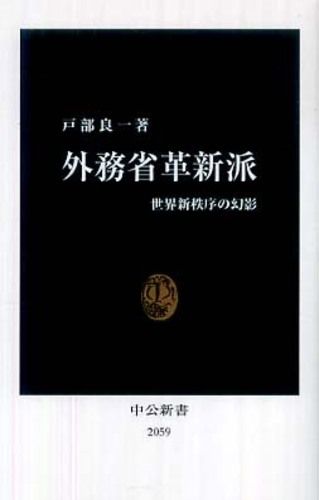 | 書名:外務省革新派 (中公新書) 著者:戸部良一 出版社:中央公論新社 出版年:2010年 |
筆者にとっては「支那事変(いわゆる日中戦争)はなぜ泥沼化したか?」という大テーマに取り組む雲上の大先輩であるが、軍部と同様かそれ以上に知識人・民衆なども事変長期化を支持したということ自体は井上寿一『日中戦争下の日本』(講談社選書メチエ、2007.7)など最近の研究でも顕著に指摘されている。本書が取り上げる「外務省革新派」とは、「ときに軍部以上の強硬論を吐き、軍部と密着して外交刷新を実現しようと行動した」往時の少壮外交官たちである。戸部氏は彼らが外務省の実権を握り日本外交の舵取りをしたというつもりはないとしつつも、「皮肉なことに、日本の国策は彼らが主張した方向に進んだ」(p.6)というのがポイントである。彼らが主唱した日独伊提携(外務省主流は対英米協調路線)は、たとえば一部の革新官僚が唱えていた「統制経済」論などと同様そもそも部内で少数派であり、当初は政策決定者間で大勢を占めることはなかった。しかしその言説自体は生き続けやがてわが国をその方向に誘導していったのは、それを必要とする国内外情勢に対応した〈言語空間〉における強さ(魅力?)ゆえであろう。「革新派が登場してきた時代は、外交がエリートの独占物ではなくなった。そして、このような時代には、革新派が提示した単純明快な説明のほうが、エリート好みの難解な解説よりも説得力を持ち得たのではないか。こうした意味で、外務省革新派は外交の大衆化・民主化の申し子であったとも言えよう」(p.306)という所論は、直後の「彼らが、外務省首脳部を批判したことには、外交の大衆化・民主化に対応できない外務省の体質に対する批判も含まれていたと考えられる」という行とあわせて読めば、目下尖閣諸島問題でその対応を批判されている外交当局における問題の根源(のひとつ)に行き当たる。外務省革新派は「皇道」外交と「世界新秩序」構想を掲げたが、かたや民主党政権の「友愛」外交と「東アジア共同体」構想は一般国民が認識している日中関係の実態の前に耐えうるかどうか・・・近代日本が「東アジア」においてどう立ち回ってきたかについて壮大かつコンパクトにまとめた渡辺利夫『新 脱亜論』(文春新書、2008.5)も読み返しつつ、今後の行方も見すえたいところ。
そして、8月に出版された(3)三宅正樹『スターリンの対日情報工作』(平凡社新書)―― 日独伊三国軍事同盟や政軍関係理論についての先駆的研究(それぞれ代表作に『日独伊三国同盟の研究』(南窓社、1975)『政軍関係研究』(芦書房、2003.5))で知られ、こちらもそれぞれ第一人者としての地位を確保している著者。そうしたバックグラウンドを知る人が本書を手に取れば、タイトルだけで「これはまたはやりの陰謀説モノかな」と判断することはないはずである。しかし目次に目を通しただけでは、そこそこ日本近現代史や国際関係史を学んだ人にとっても少し敷居が高そうには見える。いわく
第一章 クリヴィツキーの諜報活動
第二章 ゾルゲ諜報団
第三章 ゾルゲと赤軍第四本部との関係
第四章 オット駐日ドイツ大使が受けた衝撃
第五章 トルストイの暗号解読
第六章 日本人スパイ「エコノミスト」
しかし「本書を通して、軍の動きをはじめ、昭和前半期において日本政府の内部情報のほとんどが、すべて最終的にはスターリンのもとに集められていた事実が明らかになるはずである」(p.10)と銘打っている以上、虚心坦懐にかつ気合を入れて読み進めねばならない。
| (3) |
 | 書名:スターリンの対日情報工作 クリヴィツキー・ゾルゲ・「エコノミスト」 (平凡社新書) 著者:三宅正樹 出版社:平凡社 出版年:2010年 |
ゾルゲは映画『スパイ・ゾルゲ』(2003)でもおなじみのソ連のスパイ(といわれている人物)であり、ちょっと詳しい方ならオットもそのゾルゲに利用された人物として知っているであろう。駐日ドイツ大使オットに重用されたゾルゲは、その立場を最大限に活かしてドイツのソ連侵攻(1941.6)を予測し、また同じく近衛文麿首相に重用されて「南進論」(支那事変の南方への拡大)を唱える尾崎秀実と連携し日本軍の動向について決死の情報収集を行った人物として知られる。しかし冒頭に出てくるクリヴィツキーは、歴史を真剣に勉強していても「情報史」つまり〈インテリジェンス〉と呼ばれる分野に深く興味をもつ方でなければまったく知らないかもしれない(「インフォメーション」と「インテリジェンス」の違いを分かりやすく説明したものとしては、たとえば北岡元『仕事に役立つインテリジェンス』(PHP新書、2008.3))。
ユダヤ人として生まれ、ソ連の赤軍参謀本部やKGB諜報部に所属しヨーロッパ各地で諜報活動に従事するもパリついでニューヨークに亡命したクリヴィツキーは、ソ連を仮想敵国とする日独防共協定(1936.11)の全容をつかむことに成功した立役者である。何の前提もなく「スパイ活動が歴史を変えた」と言えば安っぽい陰謀論と同列扱いされそうであるが、昭和10年代に日独防共協定~西安事件(1936.12)~盧溝橋事件(37.7)~第二次上海事変(37.8)~第二次国共合作(37.9)~独ソ不可侵条約(39.8)~三国同盟(40.9)~日ソ中立条約(41.4)~独ソ戦(41.6)と数年で目まぐるしく激動した国際情勢において、あえて下世話に「事態を動かした側」―「翻弄された側」に二分すれば、わが国はやはり後者に入るであろう。独ソ不可侵条約の報を受けた平沼騏一郎が「欧洲の天地は複雑怪奇」と言って総辞職したのは有名であるが、それに対して今でも国際政治系の授業などでテキスト指定されている高坂正堯『国際政治 -恐怖と希望』(中公新書、1966.8)では国際政治は複雑怪奇なのが当たり前と一喝されている。複雑怪奇な国際情勢を乗り切るのも、あるいはそもそもそれを複雑怪奇にしてしまっているのも、表面に現れる外交交渉と表裏一体で展開されてきた各国情報(諜報)活動である。第二次世界大戦やその後の国際関係におけるそうした活動は、本書でも取り上げられる「ミトローヒン文書」(KGB記録担当者が文書の写しを冷戦後イギリスへ持ち出したもの)や「ヴェノナ文書」(アメリカ国防省が戦時中からソ連暗号を解読し続け、戦後になってようやく解読できるようになったもの)の公開によってようやく実態の一端が明らかになってきている。前者をメインで扱った日本語研究文献はまだないが、後者についてはヘインズ、クレア著/中西輝政監訳『ヴェノナ -解読されたソ連の暗号とスパイ活動』(PHP研究所、2010.1)参照。三宅氏は最後で「スターリンが、ゾルゲの伝えた情報の価値を高く評価しなかったことも、あらためて力説しておかなければならない」(p.233)と述べる。戦後さまざまな形でドラマチックにもてはやされたゾルゲよりもむしろ「エコノミスト」(日本人情報協力者、実名未特定)やトルストイ(KGBの前身であるNKVD(ソ連内務人民委員部)日本暗号解読担当者)といった人物こそスターリンの究極的な対日政策決定のカギを握っていた可能性があり、今後さらに研究されなければならないということを示唆しているわけである。
〈組織風土〉〈思潮〉〈言語空間〉そして〈インテリジェンス〉的視点といった、普段とは少し違う角度からあの戦争を見れば教科書が教えてくれない歴史がここまで広がるものである。21世紀に入ってもまだまだ総括されないあの戦争の真相がさらに少しずつ明らかになってゆくのを、以上紹介した書籍などに触れることで読者諸兄にもぜひリアルタイムで感じてみてほしい。
(文責:久野潤)