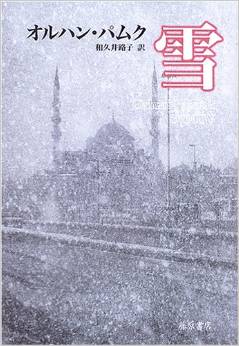 | 書名:雪 著者:オルハン・パムク 訳者:和久井路子 出版社:藤原書店 出版年:2006 |
本書は2002年にトルコ語で出版されたオルハン・パムクの「最初で最後の政治小説」と言われる作品である。執筆期間が2001年の9.11テロと重なることもあり、イスラム原理主義に対する関心の高まりを受けてか、英訳版は欧米各国でベストセラーとなったそうだ。
舞台は1990年代初め、トルコ北東部の辺境にあるカルス(Kars)という町。かつて、東西の通商・文明が行き交う要衝として栄え、各時代の権力者たちによって軍事的拠点として整えられてきた場所であった。だが、現在では、街中の建造物がかつての面影を残すにとどまり、町全体は降り積もる雪のように深い貧困と混沌に覆われている。物語は、詩人であるKaが、その町を訪れるところから始まる。
フランクフルトのデパートで買った外套に身を包んだKaは、イスタンブルの中産階級出身で、ドイツへ亡命していた来歴を持つ。Kaはカルスで、この町の現状を世界中へ伝えるために「西」からやってきた知識人として迎えられる。しかし彼の真の目的は、この町の現職市長が殺害された事件や、次の市長選の様子、最近相次いで起きている少女たちの自殺等について取材を進めることよりも、むしろ学生時代の仲間であった女性イペッキと再会することの方にあった。無神論者で政治には関心の無い彼だったが、意中の女性と再会を果たしている最中に、店内で教員養成所の校長が殺害される事件に遭遇し、次第に政治的・宗教的立場を異にするさまざまな人々との接触を通して、クーデターに巻き込まれていく。
作者は、この作品の中で、実に多くの人物たちに彼らの内面を語らせることに成功している。本作を一貫するストーリーはまぎれもなくKaのイペッキに対する恋慕と詩作の営みであるが、その一個人としての幸福の追求、一詩人としての精神的至境の追求の過程で、Kaは否応なく周囲の人々の政治的意図や宗教に対する見解に耳を傾けることを余儀なくされる。われわれ読者も、Kaの詩作と恋の行方を追いかける中で、次々と登場する人物たちの言葉に否でも耳を澄まさなければならない。それらはまさに、本作の冒頭でスタンダール『パルムの僧院』から引かれている一節にあるように、「ひどく醜悪な」銃声としての要素だと言える。
文学作品において政治とは、コンサートの最中に発射された拳銃のように、耳障りだが、無視することもできないものである。今や、このひどく醜悪なものに触れることになるのである……
単にロマン小説あるいはミステリー小説としても十分に高い評価をかち得たであろう作品に、敢えて「耳障り」なほどの多様な声明を鮮やかに吹き込み、政治小説へと仕上げた作者の力量に、読者は誰しも感服させられることだろう。と同時に、オルハン・パムクの文学者としての使命感をそれほどまでに強く駆り立てたものの一つに、当時の緊迫した世界情勢があったであろうこともまた想像に難くない。
しかし、あの9.11が明示的に提起した「西洋」対「イスラム」の衝突を読み解く手掛かりとなることを期待して本書を手に取った人の多くは、おそらく読み進めるうえで戸惑いを覚えることだろう。実際に作中に散りばめられた各登場人物の見解は、どれも「○○主義」という名を付して理解するにはあまりにも複雑で多様であるということを感じさせ、読者に単純化した図式的理解を促すものとはなっていないからである。
たとえば、カルスの少女たちの自殺を巡って対立する二者のやりとりを挙げてみよう。
第一に、政教分離の原則に基づいてスカーフで髪を覆った女生徒の登校を拒否した――そのうちの一人の女生徒が自殺をする――校長に対し、イスラム戦士会から送り込まれた男が詰問する場面。
「残念なことに、わたしたちは自分の国のことを知りません。この国の人々を愛しません。さらには、この国を、この国民を馬鹿にしたり、裏切ったりすることをいいことだとさえしています。先生、一つ質問してもよろしいですか?先生は無神論者ではありませんね?」
「そうではない。わたしはモスレムだ。」
「コラーンがアラーの言葉であることを信じているのならば、『御光章』のあの麗しき三一節についてどう思うか聞かせてほしい。」
「この説では女たちは髪を覆うようにと、さらに、顔を見せないようにとはっきり言っている。」
「よろしい。それなら、アラーの命令で髪を覆っている少女たちを学校に入れないことと両立するか?」
「髪を覆った少女たちを教育機関に、学校に入れないことは、政教分離主義国家の命令だ」
「国家の命はアラーの命よりも上だろうか?」
「それらは政教分離の国では別のものだ」
「それでは政教分離は無神論ということになりますか?」
「いいや」
「それなら宗教の命に従う少女たちをどうして政教分離の口実で授業に入れないのか」
「この問題を議論しても結論は出ない。一日中イスタンブルのテレビでこの問題を話しているが、どうだというんだ。少女たちは髪を出すことを拒否しているし、国も彼女たちをその状態では授業に入れないではないか」
「髪を覆った少女たちの、わたしたちが散々苦労して育てたあの勤勉でお行儀のいい、従順な少女たちの教育の権利が奪われることは憲法や教育と宗教の自由に合っていますか?」
「もしその少女たちがそれほど従順ならば、髪も覆わないだろう」
「政府の命令とアラーの命令とでは、どちらが大事ですか?コラーンの『部族連合章』と『御光章』に極めてはっきり書いてあるのに、大学の門で残酷な扱いを受けている少女たちの苦悩に対して、先生の良心は痛まないのか?」
「コラーンは盗人の手を斬るように言っているが、国は斬らない。それにはどうして反対しないのかね?」
「盗人の腕と女たちの操が同じだと言うのか?髪を覆っている女に教育を与えないで、社会の外に追い出すことによって、髪を出したものを大事にすることによって、女たちの操を性革命後のヨーロッパにおけるように価値のないものにすることは自分たちを、売春宿屋の主人に引き下げることになりませんか?」
「いうまでもなく、本当の問題はスカーフを象徴にして政治的芝居に利用したことによって少女たちを不幸にしたことだ」
「芝居だって? 学校と操の間で悩んだ少女の一人がかわいそうに自殺した。これが芝居か?」
「お前はひどく怒っているのだろうが、トゥルバンの問題をこのような政治的問題にしているのは、トルコを分裂させ、弱体化させようとする外の力があることがわからないのか?わしが決められることではない。これはアンカラからの指令だ。」
「スカーフをかぶっている少女が、スカーフを外すことがこの国に何の役に立つのか? 心から良心が納得する理由を言ってくれ。たとえば、スカーフを外せば、ヨーロッパ人が彼女を人並みに扱うだろうとか、少なくとも、目的がわかれば、お前を撃たない。」
「女がスカーフを外せば、社会の中でもっと楽になる。尊敬される」
「しかし覆うことは、その反対に、女を暴力や侮辱や凌辱から守り、人の中により楽に出て行けるようにした。覆った女は、外で男たちの動物的本能を刺激したり、他の女たちと魅力を競う必要がない。そしてそのために絶えず化粧する哀れな性的対象物になることもない。」
…(和久井訳、62-67ページより、一部略)
第二に、髪を覆う少女たちのリーダー的存在である少女に対し、クーデターの首謀者で少女に髪を出すように仕向ける男が少女たちの行動の理由を問う場面。
「全ての自殺の本当の理由は、もちろん、誇りです。少なくとも、女はそのために自殺します。」
「恋で自尊心が傷つけられたためか?」
「女は誇りが傷つけられたからではなく、どんなに誇りが高いかを示すために自殺をするのです。」
「あんたの友達はそのために自殺するのか?」
「彼女たちを代弁することはできません。皆、それぞれの理由があります。」
「しかし自殺は我々の宗教では禁じられておる。」
「コラーンの『女』の章で、『自らを殺す勿れ』と命じておられます。しかし、そのことは自殺した少女たちを、万能なるアラーが彼女たちを許さず地獄に送るという意味にはなりません。カルスの何人もの少女たちが髪を覆うことを望んだのに許されなかったために、自殺した者もいます。偉大なアラーは公正でおられます。彼女たちの苦悩をご覧になられます。心の中に神への愛があるのならば、このカルスの町にわたしの場所がないために、わたしも彼女たちのように自らを殺します。」「あなたが怖いのは、わたしが賢いことではありません。わたしが個性を持つことが怖いのです。この町の男たちは、女が賢いことではなくて、彼女たちが独立して、自分でことを決める、それが怖いのです。」
「まさにその反対だ。あんたたち、女がヨーロッパ人のように、独立心を持って、自分で決めることが出来るようにとわしはこの革命をしたのだ。」
…(同前、524-532ページより、一部略)
第一の場面で、イスラム戦士会の判決により校長の処刑を実行するためにやってきた男は、髪を覆う少女たちの信仰と操を擁護し、政教分離に徹した校長が少女を自殺に追い込んだと論難する。他方、第二の場面で、髪を覆う少女たちのリーダーは、髪を覆う彼女たちの個性・自己決定を主張し、自身の誇りの高さを示すために教典で禁じられている自殺さえも辞さない意志を語る。
この二人が同じイスラム主義者として「西」側の論理に対抗しているのは確かであるにもかかわらず、二人の護ろうとしているものが本質的に同じものと言えるかどうかにわかには判定しがたいような、どこか視点の不一致のようなものが感じられる。それどころか、少女たちのリーダーが彼女たちの自己決定を尊重しない「男」を批判する時、進歩主義の革命家が唱える啓蒙的な視線と一瞬の重なりが現れるかのようにすら思われる。
彼らが何を望み・何を信じるか、二者間の対話を追ってようやく辛うじて対立の軸が見えかけたところに、また別の人物が語り出す。新たな見解が加わるたび、彼らの政治闘争の場の総体は見失われかけ、各人の主張・彼らの政治的対立を「理解(判断)」することは一旦留保される。そのような、読者にとって決して平易・享楽的とはいえないプロセスが随所に仕掛けられているのである。
本書を読み終える頃に、一読者である私が得たものは、何某かの政治的主張を理解したという確信ではない。ただひたすらに、それぞれの幸福(恋人・家族との絆)や至高の芸術、神と救いを求めた人々の良心や思想に触れたという経験だけである――パムクは、おそらく意図的に、作中の人物を単なる(純粋な)政治活動家としては描かなかった。大部分の登場人物から、家族の幸せや自身の恋の成就、日々の穏当な生活の確保のために心身を賭ける儚い個人の一面を引き出している――。 彼らの内面がいかに政治的言説として表明され他者と衝突するかを、読者として目撃(・・)こそすれ、理解する視座が備わったわけでもなく、当然、現実世界の様々な政治闘争を正確に解釈できるようになったわけでもない。
作者は周到にも、作品の最後で、Kaの足取りを追うKaの友人としてオルハン・パムクという小説家を登場させ、カルスの一青年からパムクに対して次のように言わしめている。
「俺たちがどんなに貧しくて、あんたの小説を読む人たちとはどんなに違っているかを書きたいんだろ。だが、俺はそんな小説には書かれたくない。」「あんたは俺のことを知りもしない! よく知って、ありのままに書けたとしても、あんたの西側の読者は、俺を貧しいといって憐れんで、俺の人生を見はしない。たとえば、俺が、イスラム主義者の空想科学小説を書いていると言って、彼らは微笑するだろう。馬鹿にして、笑いながら、同情する。そんな者のように書かれたくない。」
…(同前、543ページより、一部略)
「カルスを舞台にする小説に俺を入れるなら、俺たちについてあんたが話したことを読者に信じてほしくないと言いたい。遠くからでは、誰も、俺たちのことをわかりはしないのだ。」「(評者註:パムクの小説を読む人たちは)自分たちのことを、賢くて、より秀れていて、人間的だと見ようとして、俺たちのことを滑稽で、かわいらしいと、この状態で俺たちを理解し、愛を感じることができると信じる。でも、俺のこの言葉を入れれば、多少は疑問が残る。」
…(同前、564ページより、一部略)
自身の立場に普遍性や特権を与えることを回避する、作者の徹底した相対主義によって編まれた本作を閉じるとき、自分の認識論的視座を如何様に固定してよいかわからないまま、目耳に飛び込んできた彼らの訴えを整理できず、立眩みにも似た感覚に襲われるというのが正直なところだ。だが、現実の政治情勢に対しても、元来そのような感覚を抱いて然るべきなのであり、日頃つい「複雑な事象が明快に解説されること」を望み頼りにしてしまう自らの安直な態度を今一度戒められる思いがする。
無限の他者の言葉を聴取してゆくという倫理の求める果てなき作業には、常に絶望に近い感覚が付き纏う。本作を通して読者は地道な傾聴に付随する疲労や無力感を少なからず痛感させられることだろう。しかしこうして様々な他者の存在を配慮しわれわれの目の前に書き現した文学者の偉業を思う時、凡庸な読者である私も、最低限、目の前に現れる他者の呼び声を聞き逃すわけにはいかないという具体性をもった僅かな使命感を取り戻す。(無限の試みの中で、具体性の現れは、ある種の希望であると言ってよいだろう。)
本書が世に出されて十数年、相変わらずあちこちに戦地を拡げては衝突が繰り返されている。海の向こうの話ではない。他者の喉元を襲いにかかるような声明が当たり前に叫ばれたり、書店に平積みされたりするようになって、ヘイト・スピーチという外来語はこの国に定着した。そうかと思えば、通りで反戦歌を歌うことが監視の対象とされたり、特定の政治的見解を持った人物は討論番組から降ろされたり。自分の身近なところで、確実に言論を取り巻く環境が変わり始めている。
大手を振って隊列を組む言葉もあれば、陰へと追い込まれかき消されそうな言葉もある。
その数々に眩暈を覚えるとき、私は本書を思い出す。そしてこう思うのである。Kaが個人の幸福を求めるうえでそれから逃れられなかったように、私も、現代に生きるおそらく誰もが、皆等しく「政治」から逃れることはできないのだろう、と。
(評者:田中いくみ)
更新:2014/12/21