◇このページについて
このページでは、「死の社会学」という社会学の一分野を「これから勉強しよう!?」という初学者の人向けに、どんな本を読んでいけばよいのかをジャンル別に紹介します。もちろん社会学を学ぶ人ではなくても、身近な経験から死に興味を持ったり、死についてこれまでよりも深く考えてみたくなった、という人も気軽にご覧になってみて下さい。なお、内容については適宜更新・追加してゆく予定です。
◇そもそも死の社会学って?
ブックガイドに入る前に、簡単にこの分野の紹介をしておきます。死の社会学は、前述したように社会学の一分野で、社会学の中ではややマイノリティに属しますが、死について社会学の方法・物の見方から研究する学問です。また、death study(「死生学」)とも呼ばれる(訳される)死にまつわる一連の研究領域の中では、死の社会学は人類学や心理学と隣接しつつ、病院や葬送、グリーフケアなどの現場を扱ったミクロな研究と、人の死生観の変遷といったマクロな研究の両方の担い手となっています。
◇「死を社会学する」とは?
ここで次のような疑問が生じるかもしれません。それは、「私たちは死を決して経験できないので、死について何も分からない。それなのに、死を研究するとはどういうことか。特に、哲学や宗教学ならいざ知らず、死を社会学の研究対象にすることはできるのか?」といったものです。この疑問に関しては、これから紹介する本を読んでいただくのが一番良いのですが、ここで一応筆者の見解を述べておくと、死の社会学では「私たちor社会にとって死とは何であるか。また、死が社会にとってどのような意味を持っているのか」といった視点で死についてアプローチを行います。昨今の脳死にまつわる議論や、高齢者所在不明問題のことを考えると、人の死には倫理や法律、社会制度などの社会的な諸次元が絡んでいることは明らかであり、その死の社会的側面を扱おうとする死の社会学には少なからず意味があるものと思われます。
入門編
◆ 澤井敦『死と死別の社会学――社会理論からの接近』青弓社、2005年。
 | 書名:死と死別の社会学――社会理論からの接近 (青弓社ライブラリー) 著者:澤井敦 出版社:青弓社 出版年:2005年 |
死について扱った社会(学)理論の解説書です。これまでの死について論じてきた社会理論(ヴェーバー、デュルケム、パーソンズ、アリエス、エリアス、バウマン、……)、ならびに死に関する社会学の事例研究(サドナウ、グレイザー&ストラウス、ゴーラー、……)が平易な文体でとても分かりやすく整理されており、死の社会学の最初の一冊としては、現時点では最良の選択になると思います。著者は前書きで、同書の作業は「見取り図を描く試み」であると述べていますが、これから死について学ぶ人にとっては、同書はまさしく「見取り図」の役割を果たしてくれるでしょう。また、同書を読むと「死の社会的側面に焦点を当てる」という死の社会学の前提が感覚的に理解できるようになっており、この点も同書を最初の一冊として薦める理由です。
◆ G・ゴーラー、宇都宮輝夫訳『死と悲しみの社会学』ヨルダン社、1986年。
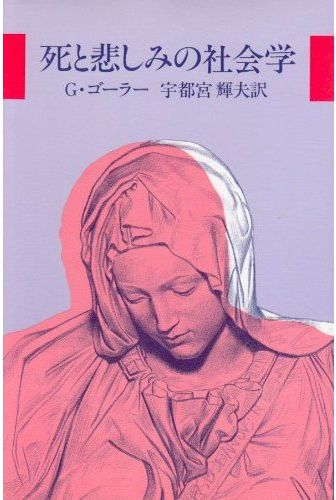 | 書名:死と悲しみの社会学 著者:ジェフリー・ゴーラー 訳者:宇都宮輝夫 出版社:ヨルダン社 出版年:1994年 |
原著は1965年。この論考は、死の社会学の研究の端緒を開いたといえる「死のポルノグラフティー」(1955年)という論文の執筆後に、死に関する著者の事例研究をまとめる形で執筆されたものです。同書は死の社会学における初期の古典として位置付けられていますが、驚くべきことに、この著作の中で後に死の社会学で議論される論点の多く(種々の死別体験、遺族、宗教、葬儀、そして死のタブー化)がすでに提起されています。よって、いまから読むと死の社会学の論点の始まりを知ることができて大変有用です。もちろん、検証されている事例や語りは時代的には古いものが多いのですが、その切り口は現代に通じるものがあり、(やや重苦しい内容ではありますが)内容も分かりやすいので、事例研究の入門書として初学者の方にオススメの一冊です。
◆ 島薗進・竹内整一編『死生学 1 死生学とは何か』東京大学出版会、2008年。
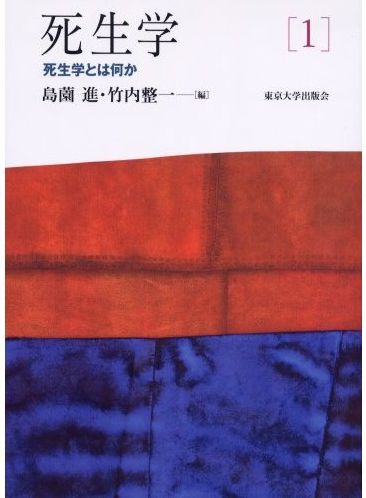 | 書名:死生学1 死生学とは何か 編者:島薗進、竹内整一 出版社:東京大学出版会 出版年:2008年 |
「死生学」とはthanatologyもしくはdeath studiesにあてられた訳語で、哲学・医学・心理学・民俗学・文化人類学・宗教学など様々な視点から人の死生観について総合的に論じる学問です。それまで多様な分野で別々に行われてきた死の研究を、1970年代ごろよりまとめて「死生学」と呼ぶような視点が生まれ、それが徐々に発展・体系化されてきたものが現在の姿であるといえるでしょう。この死生学の入門書が1~5巻(2010年現在)からなる『死生学』シリーズで、同書はその1巻目にあたる本です。この本では死生学の趣旨と意義が説明されるとともに、現在の死の研究状況全般が概観されているので、死の社会学よりももう少し広い分野の(死の研究全体の)研究状況が知りたい、という方には特におススメの入門書です。また、「死生学」の定義では死の社会学もまた「死生学」に属する学問の一つなので、死の研究全体の中で、死の社会学のアプローチがどのように位置付けられるのか、その大まかなポジションを知ることができるのもこのシリーズのメリットです。
研究成果の本(ミクロ編)
◆ バーニー. G. グレイザー・アンセルム. L. ストラウス、木下康仁訳『死のアウェアネス理論と看護――死の認識と終末期ケア』医学書院、1988年。
 | 書名:死のアウェアネス理論と看護――死の認識と終末期ケア 著者:Barney G.Glaser, Anselm L.Strauss 訳者:木下康仁 出版社:医学書院 出版年:1988年 |
原著は1965年。死の社会学の事例研究、ならびに看護研究における古典中の古典とされている本です。「アウェアネス」という言葉は「認識」を意味していて、この本では、アメリカの病院において終末期患者がいかにして自分の死期を認識するか、そしてそのような患者を周囲がどのようにして扱うのかが明らかにされます。この問題は今でこそ「インフォームド・コンセプト」として盛んに論じられていますが、当時のアメリカ社会では患者に対して「告知」をしないことが一般的であり、それゆえ患者の自身の死に対する認識は、医師、看護士、患者たちの医療の場における相互作用によってもたらされることになります。この相互作用を「閉鎖」認識→「疑念」認識→「相互虚偽」認識→「オープン」認識へといたる変化として理論化し、精緻な記述と分析を行ったのが同書でした。この理論は、「告知」が一般的な選択肢の一つとなった現代日本社会にはどれぐらい当てはまるでしょうか。なお、同書は看護の現場に向けて書かれた本でもあるので、デザインも含めて非常に読みやすい内容となっています。
また、グレイザーとストラウスは、グラウンデッド・セオリーという研究方法を確立したことでも有名です。グラウンデッド・セオリーは、質的研究(インタビューなど数字に還元できないデータを用いた研究)の有効な方法の一つとして、社会学を超えて看護学や医療の領域などでも幅広く用いられている方法です。グラウンデット・セオリーを用いて死の研究を試みる人にとっては、同書は、グラウンデッド・セオリーを用いた調査研究の優れた実践例としても読むことができるでしょう。
◆ D. サドナウ、岩田啓靖・志村哲郎・山田富秋訳『病院でつくられる死――「死」と「死につつあること」の社会学』せりか書房、1992年。
 | 書名:病院でつくられる死――「死」と「死につつあること」の社会学 著者:デヴィッド サドナウ 訳者:岩田啓靖、山田富秋、志村哲郎 出版社:せりか書房 出版年:1992年 |
原著は1967年。アメリカの病院でのフィールドワークを通して、患者の「死」や「死につつある」という事実が、実は病院内での個別具体的な社会秩序(患者やその家族、看護士や医者の考え、活動、計画などが折り重なった状況)によって形作られるものであることを記述した同書は、『死のアゥエアネス理論と看護』と並んで死の社会学における事例研究の古典とされています。同書は『死のアウェアネス理論と看護』とほぼ同時期に、しかも病院内の死という同じテーマで書かれていますが、同書の方はよりエスノグラフィー的な記述がなされているという特徴があり、社会学におけるエスノグラフィーの成功例としてもしばしば挙げられます。どちらも読みやすい本なので、合わせて読むと良さそうです(ちなみにこの時期に優れた事例研究が産出された背景には、アメリカ社会学における、それまで普遍化を志向してきたパーソンズ理論への反動の流れがありました)。
また、患者が医学的・生物学的には生きているのに、既に死んだものとして扱われるようになるとき、そのような時点を「社会的死」として初めて定義したのも同書です。この「社会的死」の概念は、死の社会学の発想を端的に示す重要なものであるといえます。
◆ 樽川典子編『喪失と生存の社会学――大震災のライフヒストリー』有信堂高文社、2007年。
 | 書名:喪失と生存の社会学――大震災のライフ・ヒストリー 編者:樽川典子 出版社:有信堂高文社 出版年:2007年 |
こちらは日本の、それも現代の事例を扱った本ですが、やや特殊な文脈における死を扱った本でもあります。というのも、この本は1995年に起こった阪神大震災で生じた「死」を主題としているからです。同書では、震災で家族を失った遺族へのインタビューを通じて、遺族がいかにして悲しみの中で家族の死を受容し、また自分が生き残った意味を確認するのかが明らかにされます。このように特殊な文脈を扱った研究であるにもかかわらず、その語りが私たちに強く訴えかけてくるのは、私たちの多くが死者に対して「あの人は今も心の中で生きている」といったような感覚を持ったことがあるからであり、そのうえでさらに、そのような一般的な感覚が震災という特殊な文脈によってどう変わってしまうのか(または変わらないのか)を思い知らされるからだと思います。このような普遍性と特殊性の交差こそが、ケース・スタディの醍醐味といえるのではないでしょうか。その語りの「重さ」から、読み進めるのは困難が伴うかもしれませんが、特殊の文脈における死を研究したい人はぜひ読んでおきたい一冊です。
研究成果の本(マクロ編)
◆ P. アリエス、伊藤晃・成瀬駒男訳『死と歴史――西欧中世から現代へ』みすず書房、1983年。
◆ N. エリアス、中居実訳『死にゆく者の孤独』法政大学出版局、1990年。
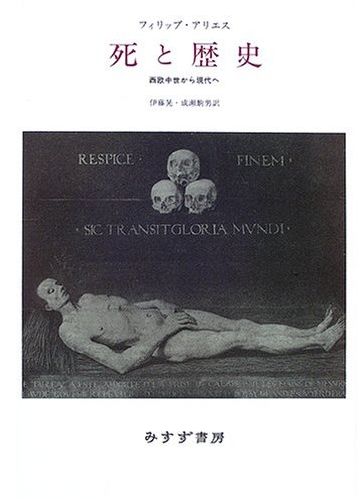 | 書名:死と歴史――西欧中世から現代へ 著者:フィリップ・アリエス 訳者:伊藤晃、成瀬駒男 出版社:みすず書房 出版年:2006年 |
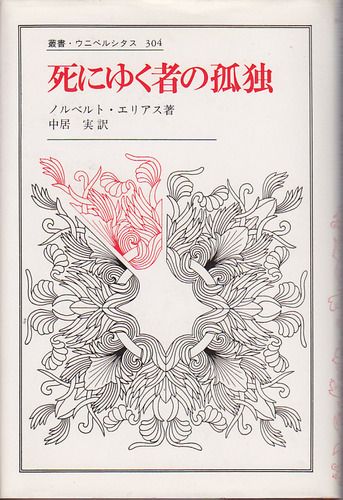 | 書名:死にゆく者の孤独 (叢書・ウニベルシタス) 著者:ノルベルト・エリアス 訳者:中居実 出版社:法政大学出版局 出版年:1990年 |
原著はそれぞれ1975年、1980年。「社会が死をどのように扱ってきたか」というテーマに関する歴史社会学の研究といえば、この2つの文献がまず挙げられると思います。アリエスは死の扱いが「飼いならされた死」(中世)→「己の死」→「遠くて近い死」→「汝の死」→「タブー視される死」(近代)と時代を経るごとに変わってきたことを論じます。それは、かつて身近なもの、慣れ親しんだものであった死が、徐々に遠ざけられタブー化されていく過程です。一方、エリアスは現代の死の特徴を「閉ざされた人間の死」という言葉で説明し、死者と周囲の人間の関係性が変化してきたことを論じています。さて、名前も似ていてややこしい(?)エリアスとアリエスは、ともに歴史社会学者として死以外の研究で多大な功績を残している論者であり、死に関する見解も一見すると似通ったものに見えます。しかし、両者の議論は実は決定的に異なる点があるようで、実際にエリアスはアリエスを批判しています。二つの本は、タイトルの割にはページ数も少なく読みやすいはずなので、この両者の食い違いについては、実際に読んで確認してみると良いでしょう。
また、両者の時代よりもさらに時が進んだ現代において、死の言説がメディア上で溢れる現状をどう考えるべきでしょうか。これについては、先に挙げた澤井敦さんの本でも挙げられている通り、Z.バウマンのSurvival as a Social Construct(雑誌Theory, Culture & Societyの9号1巻に収録)と小林直毅の「メディア・テクストにおける死の表象」(伊藤守・藤田真文編『テレビジョン・ポリフォニー――番組・視聴者分析の試み』世界思想社、1999年に収録)の二つの論文を読むことをお薦めします。
◆ 市野川容孝『身体/生命』岩波書店、2000年。
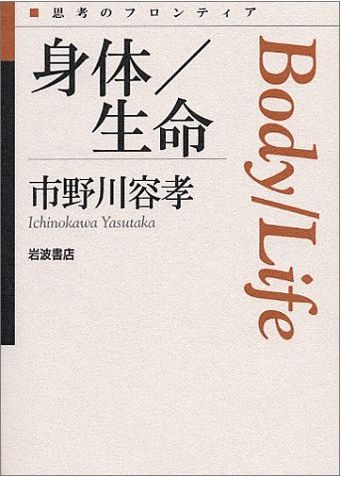 | 書名:身体/生命 (思考のフロンティア) 著者:市野川容孝 出版社:岩波書店 出版年:2000年 |
この本では、フーコーの「生-権力」の議論に依拠しつつ、しかしフーコーが参照したテクストをもう一度捉え直すことで、人々が生命や身体といったものをどのように捉えてきたのかを明らかにする作業が行われています。同書が現代の脳死をめぐる議論に与える深い示唆――同書の著者は、脳死が間違った方法で批判されることで、結果的に脳死の適用範囲が拡張されることを危惧している――についてはここでは置いておくとして、さしあたって重要であるのは、私たちの生命観は西洋近代医学において成立した伝統的生命観の原則にのっとったものであり、その原則には一定の重要な根拠があるということでしょう。個人的には、死の社会学が「死の社会的側面」等の議論を行うときも、話しはあくまでもこの原則の枠組みの中で行われているように思います。同書は短い本ですが、スムーズに読み進めるためには哲学史と思想史の若干の知識がいるかもしれません。しかし、死の社会学にとってフーコーの議論がとても重要である(視点や方法論に関してもそうですし、物凄く単純に考えても、「生-権力」論はそのまま死に関する議論でもあるわけです)ことを理解するためにも、同書はぜひ読んでおきたい本です。
◆ 竹内整一『日本人はなぜ「さようなら」と言って別れるのか』筑摩書房、2009年。
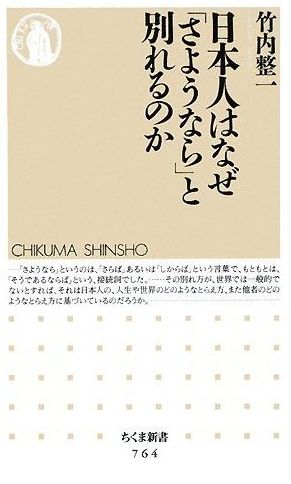 | 書名:日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか (ちくま新書) 著者:竹内整一 出版社:筑摩書房 出版年:2009年 |
ここで一冊、ライトな本を紹介しておきます。この本は、日本人の別れの挨拶である「さようなら」の語源や意味の変遷を辿ることで、そこに秘められた日本人の死生観を解き明かすという内容の新書です。おそらく同書は社会学の研究書として書かれたものではありませんが、挨拶という私たちにとって身近な話題から、日本人の意識の核心へと議論を繋げていくという構成をとることで、非常に分かりやすい死生観の解説書となっています(死の社会学も、このような研究をもっとすればいいのに、と思ったりもします)。新書なので文体も非常に易しく、すぐに読める内容になっているので、死についての重い議論に疲れてしまったときに、この本で日本人の死生観について入門してみるのはいかがでしょうか。
論文集
◆ 副田義也編『死の社会学』岩波書店、2001年。
 | 書名:死の社会学 編者:副田義也 出版社:岩波書店 出版年:2001年 |
死の社会学の論文が10本収録された本です。章立ては「ガンによる死と死別体験」「地震災害のなかの死の諸相」「子どもの死別体験」「日本文化と死の社会学」の4章に大きく分かれていて、事例研究から日本人の死生観まで、「死の社会学」の全体像のイメージを掴めるような構成になっています。ただ、本ではなく論文ということで、初学者の方にはややとっつきにくい印象があるかもしれません。むしろ、ある程度死の社会学に馴染んだあとで見てみると、10本の論文はどれも魅力的なものとなるはずです。
また、同編者が書いた新書に『死者に語る――弔辞の社会学』(筑摩書房、2003年)という本がありますが、こちらは様々な弔辞(一般的な弔辞、政治家の弔辞、社葬における弔辞など)から日本人の死生観を読み解くという、弔辞の比較社会学ともいえるようなユニークな内容になっており、オススメです。
◆ 日本法社会学会編『死そして生の法社会学』有斐閣、2005年。
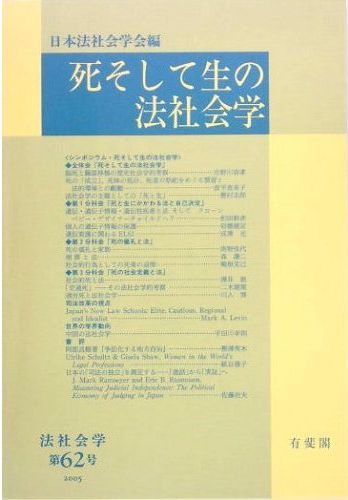 | 書名:死そして生の法社会学 編者:日本法社会学会 出版社:有斐閣 出版年:2005年 |
同文献は雑誌『法社会学』の第62号なのですが、シンポジウム「死そして生の法社会学」の特集号として編集されているために、上のタイトルになっているようです。掲載されている論文は、タイトルの「法社会学」の通り、死の社会的側面の中でも法律上の死に何らかの形で焦点を当てたものがほとんどです。また、そのような性質上、「死をいかに定義すべきか」というところにまで踏み込んだ議論が見られるのも特徴です。とはいえ、法社会学の観点から論じられているというよりは、死の社会学の論者たちが各々の専門領域に合わせて、法律上の死も含めた死の社会的側面について論じるという形ですので、法律の知識がなくても安心して読むことができます。また、法律や社会制度と死の関係という視点は、今年(2010年)話題になった高齢者所在不明問題を考える上でも重要になってくるでしょう。
周辺領域の重要な本
◆ V. ジャンケレヴィッチ、仲澤紀雄訳『死』みすず書房、1978年。
 | 書名:死 著者:V. ジャンケレヴィッチ 訳者:仲澤紀雄 出版社:みすず書房 出版年:1978年 |
原著は1966年。死を主題とした難解な哲学書ですが、死の哲学のみならず死の研究全般の古典として位置付けられている重要な文献です。特に有名なのはジャンケレヴィッチが提唱した「一人称の死」「二人称の死」「三人称の死」の概念です。ジャンケレヴィッチによれば「一人称の死」は経験不能な私の死であり、「三人称の死」は無名の死、死一般を指しています。その中間に「親しい者の死」である「二人称の死」があり、この「二人称の死」は他者の死でありながら、私の死とほとんど同じぐらいの衝撃を私に与えるという点で、特権的な地位を与えられています。このジャンケレヴィッチの区分は、死を考える際の基本的な思考の枠組みとして、今まで多くの批判を受けつつも、死の研究全般に多大な影響を与えてきました。難解な書物ですが、是非読んでおきたい本ですので、初学者の方はまずは序論の「死の神秘と死の現象」にチャレンジしてみると良いでしょう。
◆ E. キューブラー. ロス『死ぬ瞬間――死とその過程について』読売新聞社、1998年。
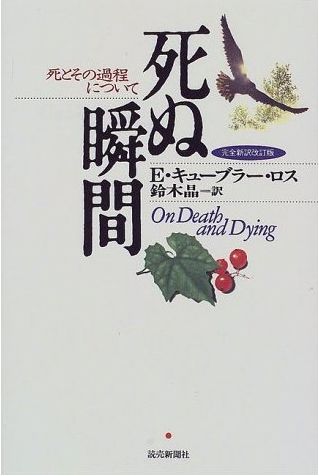 | 書名:死ぬ瞬間――死とその過程について 著者:エリザベス・キューブラー・ロス 訳者:鈴木晶 出版社:読売新聞社 出版年:1998年 |
原著は1969年。死を迎えつつある患者の生(なま)の語りを綴り、死に至る心の動きを描いたこの本は世界的なベストセラーとなり、ターミナルケア(終末医療)研究の分野では「聖典」と呼ばれているそうです。もちろん、同書はケアの分野のみならず死の研究全般にとっての古典として位置付けられており、死の現場をフィールドワークすることが多い死の社会学にとっても重要な先行研究であることは言うまでもありません。また、同書で描かれる死を受容するまでの五段階の過程――否認と孤立→怒り→取り引き→抑鬱→受容――は、様々な文献で引用されています。しかし、この本の真の価値は収録された末期患者たちの語りそれ自体にあります。その意味を、ぜひ実際に本を手に取って感じていただければと思います。なお、同書は主に患者たちの語りで構成されており、とても読みやすいので、初学者の方にもオススメです。
◆ P. メトカーフ・R. ハンチントン『死の儀礼――葬送習俗の人類学的研究』未來社、1996年。
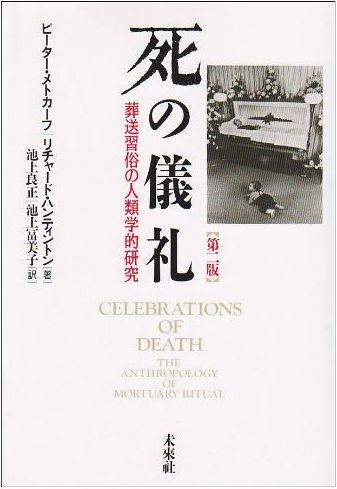 | 書名:死の儀礼――葬送習俗の人類学的研究 著者:ピーター・メトカーフ、リチャード・ハンティントン 訳者:池上良正、池上冨美子 出版社:未来社 出版年:1996年 |
原著は1991年(第二版)。これまでの葬送に関する人類学の代表的研究が整理・紹介され、それらについての包括的な議論が試みられています。同書ではエルツ、ジェネップをはじめとした様々な人類学者の視座に触れることができるほか、豊富な研究事例の紹介によって古代エジプト、ヨーロッパ、アメリカなどの葬送を知ることもできるので、死の社会学から人類学へと視座を広げよう、という方には格好の入門書となっています。死の社会学と死の人類学はとても似た研究領域なのですが、死の社会学の方が後から出てきた学問なので、死の社会学は人類学の成果に多くのものを負っているといえます。よって、死の社会学の視点からフィールドワークを行う場合、人類学の業績を無視することはできません(もちろん、両者は厳密に区別できるわけではなく、そうであるがゆえにお互いの知見を援用できるはずです)。
お役立ちURL
◆「表現文化社 雑誌SOGI」(http://www.sogi.co.jp/index.htm)
「葬送の原点と将来を問い続ける雑誌」SOGIのホームページです。そのようなコンセプトに基づき、ホームページは死について総合的に扱う学術情報サイトの様相を呈していて、様々な情報を入手することができます。中でも「評論」の項のページ下部にあるブックガイドは秀逸で、死にまつわる基本文献が広範囲に網羅されています。先に述べた通り、死の研究では社会学の隣接領域ですでに膨大な先行研究があるので、そちらに目を向ける際にはこのホームページを参考にすると便利です。
◆「死 death/dying」(http://www.arsvi.com/d/d01.htm)
立命館大学グローバルCOEプログラム「生存学」創成拠点のホームページ内にある、立岩真也さんが作成した「死ぬことに関する本のリスト」です。死に関する膨大な数の文献が列挙されており、研究を行う場合にまだチェックしていない文献があるかどうかを確認できたりして、便利です。
※文献の入手方法について
死の社会学という分野のマイナー性からか、ブックガイドで挙げた本の中には入手しにくいものがあります。というよりも、半分以上は普通の本屋さんには置いていないはずです。その場合、最寄りの図書館や学校・研究機関の図書室に本が置いてあれば良いのですが、置いていない場合は、
① 学術書に強そうな書店に行ってみる。無ければ注文をする。
(『死者に語る――弔辞の社会学』と『死にゆく者の孤独』は絶版で、注文できませんでした)
② Webcatで本が収蔵されている図書館を検索する。
③ Amazonや楽天で古本を検索する。
の3つの方法を試してみるのが良いと思われます。
(文責:中森弘樹(h_nakamori1225□yahoo.co.jp)(□に@を入れてください))