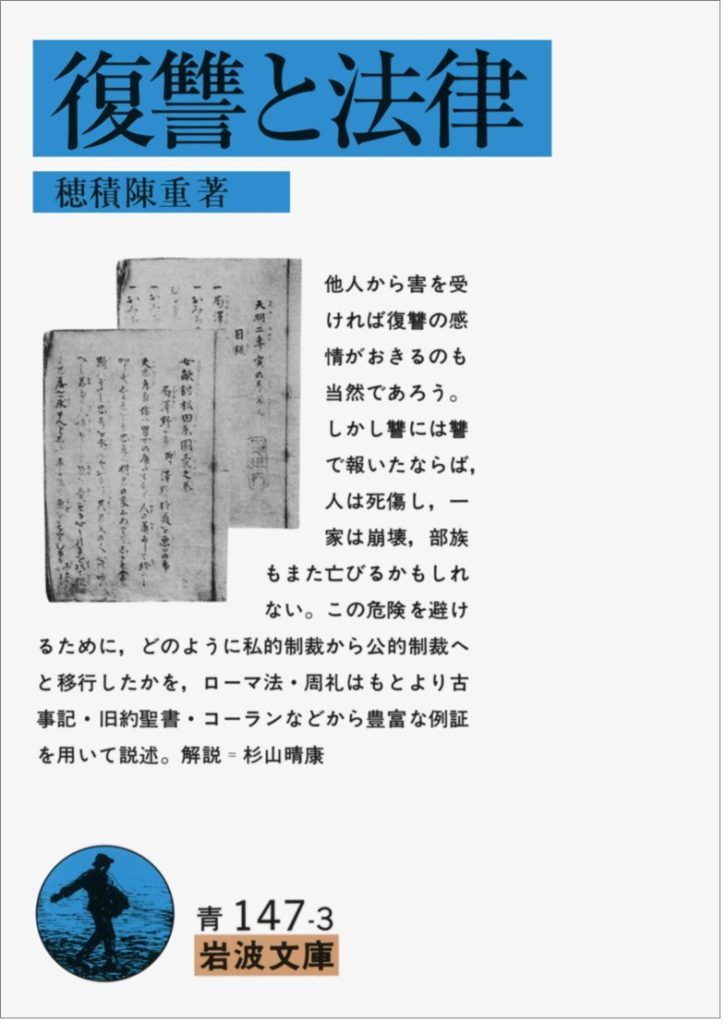 | 書名:復讐と法律 著者:穂積陳重 出版社:岩波書店 出版年:1982 |
■はじめに
西欧中世史家の阿部謹也がアジールに関する日本の先行研究のひとつとして挙げていたことから、評者は本書を知った。著者の穂積陳重は1855年(安政2)に生まれ、1926年(大正15)に没した法学者。若かりし日に明治日本の文明開化を経験し、欧州の先進各国にも留学した世代に相応しく、ダーウィニズムに影響を受けた「法律進化論」を説いた。この立場から、本書において穂積は、かつての私的制裁である「復讐」が起源となって、国家による公的制裁である「刑罰」へと進化した、と説く。穂積は明治・大正期の法学界の大立者であり、新一万円札の肖像画となった渋沢栄一の娘婿でもあった。本書は穂積の没後、息子の重遠が編集した遺稿「復讐と法律」(1931年刊)に、同趣旨の講演録や論文を併収した岩波文庫版である。以下、引用・参照の後の括弧内の数字は本書の頁数を指す。
■本書の概要
本書がアジールについて言及するのは、国家が私的制裁である復讐を抑え込み、平和をつかさどる公権力を独占的に掌握してゆく過程で、国家による避難所(アジール)の認可・特設などがその一手段となった、という連関からである。本書のアジール論に触れる前提として、復讐から刑罰への「進化」の段階を、穂積がどのように捉えていたかを大まかに紹介しておこう。
まず、法についての穂積の基本的な考え方は、「法の起原は自力制裁の公力制裁に転化するにあり」、「転化は個体力の連合集中による」(245)というものだ。国家の力がまだ弱かった時代において、血族集団の一員が他の血族集団によって殺された場合などには、被害者の集団が私的な実力行使によって報復することは正当であるばかりでなく、むしろ果たすべき義務であった。この「復讐義務時代」から進んで、「社会の組織漸く整備し、社会力を以て個人を統制する」時代になると、私闘の応酬が治安を害することが理解され、復讐が次第に制限される時代に入る。これが「復讐制限時代」である。
その制限の一般的な方法として(一)復讐義務者を限定する(二)復讐義務者の順位を定める(三)復讐避難所を設ける(四)復讐調停の機関を設ける(五)復讐の届け出をさせる(六)復讐の許可を求めさせる(七)復讐の賠償を許可する、の七つを穂積は挙げている(118)。最後の「賠償」は人々の経済生活が進んだ段階を俟って行われるようになるものであり、「復讐から賠償へ」の流れは、公権力のさらなる発展生長に伴い、国家が加害者を罰する「刑罰」へと発展してゆく。かくして国家が暴力を独占する「復讐禁止時代」へと移行する。
■穂積のアジール論
穂積がアジールについて論じるのは、むろん、上記(三)款(133-174)においてである。(一)避難制、(二)避難俗の起原及び避難場、(三)避難制の効果、(四)避難制の衰滅、の四項からなるこの節で、穂積は豊かな語学力を駆使して欧語文献や漢籍を渉猟し、約四十頁にわたって世界各地のアジールの実例を引照している。そして、これらの豊富な実例に基づいて、アジールへの避難が「私力の公権化」のプロセスにおいて持った意味を鋭く分析している。
それを要約するならば、まずアジールの習俗はタブーの観念に起因しており、その不可侵性ゆえに、復讐を逃れようとする者の避難所となることが多く、復讐の連鎖を終息させる効果があった。このことを利用して、立法者が新たにアジールを設けるようになる。つまり、元来の宗教的タブー観念に基づくアジールに加え、治安の確立・維持のために立法者が特設するアジールが発生する。
旧来のアジールが犯罪の種類を問わずに庇護を提供したのに対し、立法者によって特設されるアジールは、過失致死犯は庇護されるが謀殺犯は庇護されない、などの条件が付加される。また、立法者は特設されたアジールの不可侵期間を、仲裁や賠償、審判などによる紛争解決へと導く手段として用い、「これによりて自力救済を公権力に収むるの一手段とする」。(150)
とはいえ、アジールの存在は一国内に治外法権があるようなものであり、国家の司法権が確立すればアジールそのものが不要となり、復讐と共にアジールは制限・廃止されてゆき、わずかに特赦などの形で残ることとなる。穂積のアジール論は以上のように要約できる。
■後の論者との比較
穂積の上記の一連の議論を通読して、その先進性に驚かざるを得ない。現代のアジール論の標準となっている法制史家Ortwin Hensslerの『アジール その歴史と諸形態』(原書1954年、国書刊行会より拙訳)が参照しているA.HellwigやJ.Kohlerの基本文献を、江戸時代に生まれた東洋の一学徒がすでに縦横に活用している。のみならず、阿部謹也がのちに論文「ドイツ中世後期におけるアジール」で展開した、国家によるアジールの取り込みと廃絶に至る過程での二種のアジール(「固有のタブーに根差すアジール」と、「立法者が特設するアジール」)の意味を、半世紀以上前に先取りしている立論にも唸らされる。
とはいえ、現代の我々が本書を読む場合、その後の論者のアジール論と比較した上で、穂積のアジール論には欠けていてその後の論者が補った論点や、逆に、穂積にはあって後の論者では希薄化した論点を拾い出すことが、アジール研究全体にとって生産的な読み方であろう。
まず、現在から振り返ってみたときに、穂積の議論において再考を要すると思われる点は、差し当たり三つある。以下で、アジールの前提となる復讐に関する捉え方の問題点とも併せて、それぞれについて考察を加える。
■「法的」行為としての復讐
第一は、「復讐と法律」というタイトルに端的に示されているごとく、復讐は「法的」な行為とは捉えられておらず、自然的・本能的な行為として理解されていることである(27)。だが、西洋中世史家の堀米庸三が西欧中世のフェーデについて指摘するように、復讐はそれ自体当時の自然法観念に根差するまぎれもない「法的」行為であった。そして、犯罪の被害者(やその一族)は犯罪によって傷ついた共同体の平和を回復する手段として、フェーデと法廷での闘争のいずれをも、自由に選択することができた。同様に、アジールもまた不可侵性の観念と慣習に根差す「法」制度であった。
なお、ここで確認しておけば、アジールは復讐の連鎖を緩和する場として「平和」の場であることはイメージしやすいが、そもそもフェーデ自体が平和回復のための法的行為であり、それがうまく機能せず報復の連鎖などが生じた場合の安全装置としてアジールが機能したと言える。つまり、アジールとフェーデはいわば一体となって民衆レベルの平和回復・維持システムを構成していた。したがって大局的にみれば、国家による「刑罰」がフェーデを抑え込んでゆく過程とは、フェーデとアジールが一体になった平和維持システムの全体が、国家のもとで解体・再編成されてゆく過程であるといえる。
■「公的」行為としての復讐 ―― 二種の「公」
第二は、「法の起源は自力制裁の公力制裁に転化するにあり」とし、その転化は「個体力の連合集中による」(245)と述べているように、穂積は「復讐から法律へ」の移行を、自力での「私的」な制裁から「公的」な制裁への移行として捉えており、さらにこれを、「個人」の力による制裁から「集団」の力による制裁への移行とも重ねて理解している点である。
しかし、これも堀米が指摘するように、復讐(フェーデ)が「私的」な闘争と表現されるのは、あくまで国家のみを「公的」な存在とし、それに抗するものとしての性質から「私的」の形容が付されるにすぎず、既述のようにフェーデは国家以前の共同体における平和回復のシステムであるという意味では、国家とは違う種類の「公」的な行為であった。
同様に、フェーデの緩和装置としてのアジールも、国家の側から見れば「治外法権」がまかり通る「私的」な無法地帯とも映るであろうが、これも国家以前の宗教的慣習に根ざす平和秩序の場であり、その意味で国家の公共性とは別種の「公的」な場であった。網野が日本中世史に見出したアジールの多くが「公界」と呼ばれていたことも、これに呼応している。
また、これと関連するが、「復讐の原始状態は団体的にして、復讐義務は全族員これを負い、復讐対抗義務も斉しく全族員これを負うものとせり」(111)と穂積自身が言っているように、原初における復讐は、そもそもの初めにおいて「個人的」な私的怨恨に基づく行為ではなく、血族共同体全体の平和に関わる公的な「集団的」行為であった。
■アジールの背後にあるもの
第三は、おそらくは適者生存というダーウィニズムの考えに則って、法による刑罰のほうがそれに先立つ復讐よりも優れており、国法による刑罰が誕生した後は、復讐やそれを前提としたアジールはもはや不要のものとなる、と考えている点である(173-174,276-277)。これは、言い換えれば、アジールという制度のうちにフェーデの緩和装置としての機能しか見ない、ということであり、その点で、アジールという現象の背後に、人類史に通底する「自由・平和・平等」の原理として、「無縁・無主」の原理なるものを看取した網野善彦の議論と、大きな対照をなす。つぎに、これについてみてみよう。
■網野善彦におけるアジールと「無縁の原理」
1978年に刊行された網野善彦の『無縁・公界・楽』は、日本史上のアジールを扱った基本文献として知られている。確かに、そこには日本中世のアジールが数多く紹介されてはいる。しかし、網野が同書を記した目的は、実は、歴史上のアジールの掘り起こしそのものではなかった。網野が目指したのは、アジールという現象の背後にあり、アジール以外にも一揆や惣村、自由都市、山野河海とそこを行きかう遍歴民のエトス、などに通底する「無縁・無主の原理」を浮かび上がらせることにあった。網野のこうした立場からは、アジールは国家権力の伸長とともに消滅しても、その背後にある「無縁・無主の原理」そのものは滅びることなく、地域と時代ごとに別の形をとって「雑草のごとく」強靭に芽を吹く、と考えられていた。
つまり、あくまで国家による治安が未確立の時代における過渡的制度としてアジールを捉えていた穂積に対し、網野はアジールの背後には国家の「公」とは別種の、人類史的な「公」の原理があるとみて、そこに来たるべき人類社会の「自由・平等・平和」の可能性を探ったという点に、両者の根本的な違いがあると言えよう。終生マルキストだった網野にとって、それはやがて到来するコミュニズムの社会を、ソ連型社会主義とは全く違う仕方で構想するための基本原理であったかもしれない。
■網野に欠けた論点
しかし他方で、穂積と比較することで、網野についても補うべき点が浮かび上がってくる。というのも、上でみたようにアジールがフェーデを前提とし、両者がセットになって国家以前の平和秩序のシステムを構成していたとするなら、網野の議論において、アジールだけでなく、その前提となるフェーデ(復讐)の慣行についても、併せて「無縁の原理」との関係から語られなくてはならないはずである。穂積が指摘するように、赤穂浪士をはじめとして、日本においては国家の法が成立したのちも長く復讐(仇討ち)の風習が残ったことを考慮すれば、なおのことであろう。しかし、管見の及ぶ範囲では、網野が復讐というテーマを「無縁・無主の原理」との関係から扱っている箇所はないように思われる。
たまたま網野の視野に入らなかったのかもしれないが、『無縁・公界・楽』執筆の時点では、網野はアジールに関して穂積著作の存在を知らなかった(その後勝俣鎮夫の教示により知る)。アジール論の先人として網野が同書で紙幅を割いて言及するのは戦前の皇国史観の泰斗である平泉澄の、若かりし日の著作『中世における社寺と社会の関係』(1926)である。同書中に後年の平泉の国家至上主義に連続する史観を見出す網野は、「皮肉なことに、平泉氏の著作の中で現在もなお十分な生命を保ちえているのは、このような諸民族についての西欧の研究を紹介している部分である」としている。しかし、そうした観点から言えば、穂積の『復讐と法律』は西欧各国もちろんのこと、古代ギリシア・ローマ、オセアニア、アフリカ、中国、イスラーム世界をも含む世界各地の豊富な事例を紹介しており、平泉著作に勝るとも劣らない価値を持つと言えよう。文献検索の便が今ほど良くなかった時代、本書が『無縁・公界・楽』執筆時の網野の目に留まらなかったことは、学問的にはいささか惜しまれるところである。
■「判別」をめぐる介入
穂積と網野のアジール論の比較はこれで措くこととするが、穂積の著作の叙述から気づいたことをもう一点記しておきたい。穂積も言うように、アジールの存在は、一面ではある種の治外法権の面を持つが、他面では「私力の公権化」を推し進める媒介ともなる。私の目を引いたのは、アジールを媒介にして国家が自らの力を強大化する際の道筋には「判別をめぐる介入」という契機が存在することである。それは旧約聖書についての記述に見られる。そこでは元来固有のタブーに根差すアジールに加え、立法者が特設したアジールの例として、過失致死犯のための「逃遁邑(逃れのまち)」が取り上げられているが、穂積は次のように記している。
「この逃遁邑なるものは殺人者の避難市にして、その場内において復讐を禁止せるものなり。然るにこの避難市の保護を受くることを得る者は、過って人を殺したる者に限り足るを以て、避難市に入りて復讐を免れんとする者ある毎に、その者の避難権の有無に関し審判をなすの必要を生ずるに至れり」(152)
「これらの聖律によれば、避難市の設置とともに避難権の有無を生じたるのみならず、避難権と復讐権とは両々対立し、前者有るときは後者なく、後者あるときは前者なきを以て、避難権の有無を審判するときはこれと同時に復讐権の有無をも判決するの結果を生じ、漸く私制裁が公権力に吸収せらるるの端緒を啓くに至れり」(155)
つまり、フェーデとアジールからなる民衆の平和秩序に介入し、そこに自らの権力を浸透させようとする立法者は、特設したアジールへの避難権に「過失致死犯のみが庇護を享受できる」という条件を設け、謀殺か過失致死かの「判別者」の立場に立つという道筋で権力の浸透を実現していった、ということである。
評者がこれに目を留めたのは、日本の近代において現行刑法(明治40年公布)に39条が設けられた際、精神医学(者)が地位向上獲得のためにとった立場がこれに類似するからである。刑法39条は精神障碍者が原因で生じた犯罪に関し、「心神喪失者ノ行為ハコレヲ罰セズ、心神耗弱者ノ行為ハソノ刑を減軽ス」という規定である。言わば触法精神障害者のための「刑事罰からのアジール」とでも呼びうるものであるが、実際、この規定によって刑事罰を免れた者は精神科病院(アジール/アサイラム)での治療を義務付けられる。
この法制度についての評価はここでは控えるが、芹沢一也は『狂気と犯罪』において、この規定が導入された当時、まだ医学界のなかでも日蔭者の位置にあった日本の精神医学(者)が、心神喪失なのか、心神耗弱なのか、あるいは完全に責任能力を有するのか、の「判別」を担う存在として司法の領域に接近し、やがて「精神障害者の犯罪からの社会防衛」と「医療による触法精神障碍者の救済」という二重の使命を担う存在として大きな権力を獲得していった、と分析している。
ここから旧約聖書の「逃れのまち」についての穂積の記述を振り返ると、両者の時代と地域の違いにもかかわらず、アジールでの庇護を享受する資格があるか否かの「判別をめぐる介入」が、権力の浸透のカギとなっていることに気づく。「判別をめぐる介入」が権力一般の性質にとってどのような意味を持つのかは、さらなる考察を要する興味深いテーマだが、ここでは問題の指摘にとどめ、他日の考察を期したい。
■おわりに
評者が穂積陳重『復讐と法律』を読んで考えたたことは以上のとおりである。穂積の法律進化論に賛成するか否かはさておき、その博学ぶりにはとにかく圧倒された。安政2年(1855年)生まれだから、ろくな辞書もなかったはずの時代である。そうした時代にあって、欧州に留学して身に着けた語学力を生かし、古今東西の法制度について膨大に調べ上げ、それを「私力公権化」という道筋へと整理した手腕を見るにつけ、近代化の途上にある国家の命運を背負って研鑽した明治の学究の偉大さを感じずにはいられなかった。法律を専門としない人びと(評者もその一人である)にも、一読をお勧めしたい。
〈参考文献〉
網野善彦『無縁・公界・楽』(平凡社)
堀米庸三編『世界の歴史 3 中世ヨーロッパ』(中央公論社)
芹沢一也『狂気と犯罪』(講談社)
(評者:舟木徹男)
更新:2024/08/31