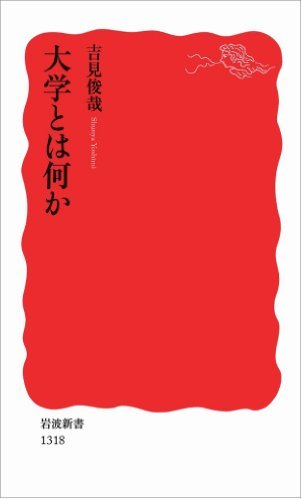 | 書名:大学とは何か 著者:吉見俊哉 出版社:岩波書店 出版年:2011 |
▼「大学とは何か」という問い
大学教育改革、国公立大学の法人化、グローバル教育への対応、キャリア教育、大学生の就職活動、入試制度改革、学生の学力低下、教養教育の議論等々。今日、大学についての話題が新聞やテレビにのぼらない日はないというくらい 大学は人々の関心と注目を集める対象となっている。たしかに、教育には、個々人のライフスタイルや社会制度の再生産にとどまらず、むしろ、それらを大きく転換しうる可能性をも秘めている。それゆえに、教育や行政に携わる専門家であるなしにかかわらず、ジャーナリスト、企業家、そして学生、市民など、様々な人たちがそれぞれの立場から、大学についての意見や議論を交わしてきたのである。ところで、こうした議論の中で、ともすれば見落とされがちな前提があるのではないだろうか。多くの大学論が自明のものとしてし、不問に付している前提。それは、そもそも大学とは何であるのか、という根本的な問いである。
本書は「大学とは何か」という問いを正面から扱っている。全体の構成としては、①大学の世界史的な変遷、②メディア論的な観点、③教養の価値の新たな形での再定位、という3つの軸を中心に構成されている。章立ては歴史的展開に沿っており、1、2章では中世、近代までの西洋世界での展開、3、4章では江戸、明治時代から戦後、現代までの日本での展開が論じられる。後半詳述されるような、たとえば、国権/民権に対応づけられる国立大学と私学との理念的な対立や、戦後の民主化に裏打ちされた新しい大学の理念の構想と挫折、1960年代に巻き起こった学生運動が出現させたユートピア的学習の実践等々の分析は非常に興味深いのが、しかし、ここでは前半の西洋における展開に絞って紹介することにしたい。
▼大学の起源
本書は、世界で最初の大学の誕生を12世紀末から13世紀初頭の北イタリア・ボローニャのボローニャ大学に求める。当時のヨーロッパでは、中世の自治都市が発達してきており、都市は、流浪者、遍歴者、旅の学者、朗読家やその支持者などの多種多様な人間たちが出会う場所となっていた。大学は、そうした都市の移動の自由を前提として、文字通りの地理的領域を横断する知的なネットワークを媒介するメディアとして誕生し、後にヨーロッパ全土に拡大していくこととなる。また、流浪者、異邦人たちは当地の法によって保護されなかったため、お互いの利害、権利を保障するための互助組織(コンソルティア)が必要とされた。それこそが大学の起源であったという。大学を意味する「ユニヴァーシティー」の語源はラテン語の「ウニヴェルスィタス」(universitas)であるが、その意味は「組合団体」のことであり、学問の普遍性とか学知の宇宙などといった理念とは本来何の関係もなかった。中世の大学でとりわけ法学が重要視されたのも、ローマ教皇と皇帝との、いわゆる叙任権闘争を利用することで、都市の自治権を保障させるために役立ったからである。
さて、こうしてみると、黎明期の大学は、現在そのように呼ばれているものとはまったく異なっていることに気づく。大学というと、われわれは、実体的な土地や建物、組織・制度、あるいは、学問を教授する教師とそれを聴く学生という固定的な関係によって成立する空間をイメージする。しかし、少なくとも、当時のボローニャの自治都市の大学はそうではなかった。むしろ、自由な諸個人がランダムに出会う結節点が大学だったのだ。
しかし、一方で、見逃してはいけないのは、当時の大学が、普遍性を指向する空間でもあったという要素である。各大学の講義はヨーロッパの共通語であるラテン語で行なわれ、各分野での授業内容にはほとんど地域差がなかった。背景には共通言語の使用に加え、イスラム経由で復興したアリストテレスの形而上学と学問的方法論、そして、キリスト教の神学体系が共通の基盤を形成したためである。だから、教師たちは土地に縛られることなく、ヨーロッパ中の大学を自由に移動することが可能だったし、また、理念的には、古代ギリシアを出自とする哲学体系とキリスト教出自の神学体系とが、ある種の緊張を伴いながら、統合されたのである。その意味で、「大学は最初からトランスローカルな知識空間」であった。
▼大学の一度の死と再発明
しかし、12世紀頃に誕生した大学は、現在の大学と直接つながっているわけではない。ボローニャ・モデルの大学は近代初頭に一度衰退し、死んでしまったのである。まず、13世紀、14世紀頃、神学教育のために大学を利用するようになった、修道会(ドミンゴ会)の修道士が大量に大学に流入し、教師になる者も増えた。その結果、本来の自治組織としての性格が失われ、大学と教会、哲学と神学との緊張関係も消えた。さらに、それに加えて、ドイツ地方では領邦国家が台頭。ヨーロッパ各地で保守化、階層化傾向が進行し、大学は領邦内の官僚組織の中に組み込まれていった。かくして、当初の大学の理念であった都市の自由や普遍的な学知は一度死んだのである。
大学が「第二の誕生」を果たすには19世紀初頭までまたなければならない。フランス革命とその後のナポレオン戦争での敗北を受けて、プロイセンでは改革的意識の高まりとナショナリズムの高揚を背景とした新しい教育改革の機運が高まった。そのときに誕生したのが有名なフンボルト大学(後のベルリン大学)である。フンボルト大学は、従来の教育に加えて、研究カリキュラムを重視した。それは、学生が単に教えを受ける存在であるにとどまらず、自律的に考えられる主体となるように陶冶をはかるためである。これが今日の大学の直接のルーツとなった。
近代の大学の思想的核心を準備したのはカントである。カントは、大学の外部に教育内容を方向づける審級がある上級学部(神学、法学、医学)と、政府からの命令から独立し、命令を下すことはできないが、すべての命令を判断する自由をもつ下級学部(哲学)とを区別し、その綜合の場として大学を位置づけた。それによって、”何のために役に立つのか”というような、「社会的有用性」とは切り離された、「理性的な自由」の価値を擁護したのである。これによって、大学は他の研究機関や専門学校とは一線を画する、自律性と独自の権威を獲得することになった。
▼アカデミーの起源
ところで、今日では大学(ユニヴァーシティー)とアカデミーの区別は等閑視されているが、両者は成り立ちからまったく異なった存在であったという。アカデミーは、今日でいうところの専門学校であり、「大学の保守性を批判し、新しい知を切り開く先端的役割が、アカデミーには期待されていた[…]新しい時代に対応できない伝統性などとは正反対の、むしろ、実学的で先端的、新しいものに対応して実験的な知を紡ぐ専門家集団を基盤としていた。」
一方、大学は19世紀の大学の再発明まで、旧来の知識体系や時代遅れの偏見に支配されていた。むしろ、近代知は、デカルトやパスカル、ロック、スピノザ、ライプニッツに象徴されるような、大学に所属しない担い手たちと、その知的なネットワークによって牽引されたのである。彼らの活動を可能にしたのは、他方では、印刷技術というメディアとそれを受容する公衆だった。それまでは一部の関係者にしか伝えられなかった知識は、国語に翻訳された印刷物によって、不特定多数の「読者」に届けられることを通じて、あらゆる人々が参加しうる公共的な討議空間を出現させたのである。
▼三度目の画期―ポスト国民国家と情報化
現代の大学は基本的にはカント的思想に裏打ちされた教養的理念によって発展してきたのだが、著者は、現代の大学が直面している根底的な変化があるとみている。その変化とは、国民国家の退潮である。19世紀以来の近代の大学は、国民国家を基盤として成立してきた(もちろん、それゆえに、国家と大学との緊張関係という問題も立てられたわけだが)。しかし、現在進行している大きな変化は、その国民国家が役割を終えようとしているということだという。その上で、著者は「中世の都市ネットワークを基盤にした大学概念」に未来の大学のモデルを見出す。中世の大学から抽象されるポイントは、「移動性」、「共通性」、「普遍性」である。たしかに、いまや、人やモノの移動性が飛躍的に上昇し、すでに英語は、世界中の人々がニュートラルに対話するための共通の基盤を提供しつつあるようにもみえる(単純な「アメリカン・スタンダード」とは別のアスペクトとして)。いずれにしても、未来の大学を実現する環境のいくつかは整備されつつあるといえるのかもしれない。
他方、メディア論という観点からみて、とりわけ重要な要素は、情報化である。印刷技術が近代初頭の知的活動の基盤となったように、今度は、インターネットの世界的な普及、浸透が、大学にとって新たな衝撃となりつつある。書籍のデータベース化や電子出版、動画配信技術の利用(たとえば、iTunen Uの利用やインターネットを駆使した無料授業履修システム)など、すでに兆候は様々な場面でみられはじめているようである。
大学はこれから、新しい情報技術をうまく摂取、利用しながら、発展していくことができるのだろうか。そのような事例もきっと出てくるだろう。しかし、現れてくる新たな大学は、今われわれが自明に考えている大学の姿ではないのかもしれない。さらに言えば、大学がいつも新しい知の牽引役であるという保障は、過去の歴史に学ぶ限り、じつはどこにもないと言わなければいけないのではなかっただろうか。
さまざまな形で「大学の危機」が叫ばれる今、歴史的な変遷を振り返ることは、そもそも「大学とは何か」、という根本的な問いを考える上で、重要な手がかりを提供してくれる。
(評者:大窪 善人)
更新:2013/08/15