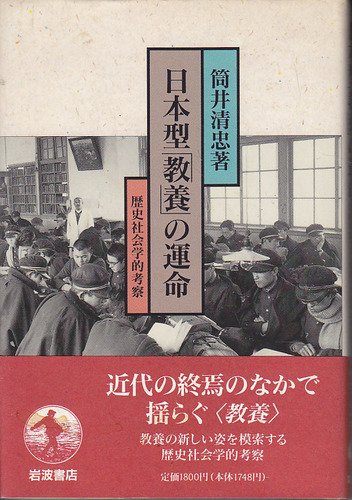 | 書名:『日本型「教養」の運命――歴史社会学的考察』 著者:筒井清忠 出版社:岩波書店 出版年:1995 |
本書は、明治期から昭和期にかけての日本型「教養」の盛衰を追った研究書である。研究書とはいっても、その語り口は平易で、具体例が豊富に含まれているので、一般の読者にも手に取りやすい。日本型「教養」の系譜を知るためには最適の一冊といえるだろう。
近代日本における「教養主義」の成立を語る際には、東京帝国大学講師として来日したケーベルの存在が強調されることが多い。夏目漱石や西田幾多郎をはじめとして、安倍能成、岩波茂雄、阿部次郎、九鬼周造、和辻哲郎など、その教えに影響を受けた知識人は多い。このケーベルがドイツ型「教養Bildung」理念の信奉者であったことから、その教え子たちを通じて、明治末期から大正期にかけて「教養」の理念が普及したと言われている。
本書の特徴は、このようなケーベル由来の教養主義の系譜を認めつつ、同時にもう一つの「教養主義」成立の系譜、すなわち「修養主義から教養主義へ」の流れを強調している点にある。本書によれば、明治末期から大正期にかけての「教養主義」の成立に先立って、明治30~40年代に「修養主義」の流行があり、これが「教養主義」の性格を決定づけていたという。「修養」とは「学問を修め精神を磨き、人格を高めるよう努力すること」を意味するが、これが「文化の享受を通しての人格の完成」という意味での「教養」理念に先行していたのである。
この修養主義が成立した時代背景が興味深い。修養主義が成立した明治後期は、明治国家の体制整備が進み、明治前半期の日本の駆動力であった立身出世主義に陰りが見え始めた時期であった。明治20年代後半から高等小学校・中学校、30年代からは専門学校生徒が急増し、「受験」という言葉が大量に使用されるようになった。また、日清・日露戦争の勝利により維新以来の「富国強兵」という国家目標がある程度達成されたと受け止められたことから、一種の「社会的弛緩状態」が産まれ、青年層の「柔弱」「奢侈」「享楽的傾向」「官能耽溺」「頽廃」がしきりに指摘されるようになった。つまり、「受験地獄」の成立や社会のアノミー化、若者バッシングなど、戦後日本社会でも大きな問題になる事柄がすでに明治後期の時点で出揃っていたということであり、このような「頽廃」状態への反動として「修養主義」が成立してきたのである。
明治後期の社会的アノミー状況に生きる青年層に対し、その閉塞感打開のための新しい思想・宗教・社会運動が起こり、これが「修養主義」の思想を形づくる原動力になっていったという。例えば、清沢満之の雑誌『精神界』、網島梁川の「見神の実験」、西田天香の「一燈園」設立、蓮沼門三の「修養団」設立、田沢義鋪野の青年団運動、野間清治の講談社設立などである。さらに明治30年代の「成功書ブーム」の反動として、明治40年代に「修養書ブーム」が到来し、これによって「青年の人格陶冶」という修養主義の性格が徐々に形成されていくこととなった。
以上のような修養主義の成立を受けた後に、明治末期から大正期にかけて「教養主義」が登場する。その教養主義を育んだのは、まず第一に旧制高校文化であった。とりわけ明治39年に新渡戸稲造が第一高等学院(現在の東京大学)の校長として就任したことが、教養主義の成立に大きく寄与したと本書は位置づけている。新渡戸は歓迎会で「周囲に城壁を築くなく襟懐落々として性格の修養にこれ努めよ」と一高生に説き、当時一年生だった和辻哲郎は「わたくしたちはただその弁舌に魅せられて、うっとりとして聞いていた」という(本書、21ページ)。新渡戸は週一回倫理の講義を行うほか、「一高の近くに一件の家を借り受け、週に一度生徒との面会日を定めて、生徒と話し合う機会をつくった。そのほか課外講義、特別講義を通して、生徒の人格向上、修養向上をはかるよう努力し、生徒に深い感化を与えた」(同前)。そこでは、ゲーテの『ファウスト』やミルトンの『失楽園』など、西洋哲学や文芸についての講義が行なわれるとともに、こうした文化・学問の享受を通した「人格の陶冶」の重要性が繰り返し語られたという。
こうして修養主義を包摂するかたちで成立した教養主義は、形を変えながらも戦間期を越え、戦後の一定時期まで継承された。その衰退が始まるのは1960年代後半からであり、この背景には大学の「大衆化」が進んだことやマルクス主義の衰退が大きいと著者は分析する。旧制高校文化のなかで成立してきた「教養主義」も、大学の進学率が向上するとともに、そのエリート主義的性格を失い、また戦後日本経済の発展とともに「文化の享受を通じた人格の陶冶」という教養の理念も次第に薄れていくこととなった。その過程を、著者は大学生の読書傾向の変化を調査することによって示している(文芸書・文芸雑誌から大衆書・大衆雑誌へ)。
この教養衰退の傾向は現代に至るまで続いているわけであるが、本書の最後は日本型「教養」理念の展望について触れられるかたちで締めくくられている。著者は、今後の日本における「教養」のあり方は大衆文化との関わりにかかっていると述べ、二つの方向性を示している。一つは、教養ある内容の文化を大衆文化に浸透させていくこと。もう一つは、教養主義文化の中に大衆文化の良質のものを取り込んでいくということである。つまり、教養文化(ハイカルチャー)と大衆文化(サブカルチャー)の相互浸透こそが、現代的「教養」再生の鍵であるというのが著者の立場である。
しかし私見では、教養文化と大衆文化の相互浸透という本書が示す処方箋によって、教養主義の再生を期待しうるのかどうかは、やや疑問の残るところである。もちろん、教養的知識を得ることによって大衆文化をより深く楽しんだり、逆に教養的知識を大衆文化に応用したりすることによって新しい知の世界が広がる可能性はあるだろう。だが、教養文化と大衆文化を比べれば、やはり大衆文化のほうが圧倒的に親しみやすく娯楽性も高いゆえに、最終的には「教養」は大衆文化のうちに取り込まれて希薄化され、その固有の良さや意義を喪失してしまうのではないか。
また「教養」を大衆文化に開くことは、本書が強調してきた「文化の享受を通じた人格の陶冶」という日本型「教養」の性格を喪失させる結果をもたらすとも考えられる。もちろん、近代化の進行とともに、そのような「古き良き教養」のあり方が失われていくのはやむを得ないことであろう。しかし、ただ教養文化を大衆文化に接続させるだけでは、そのような傾向をより後押しする結果にのみ繋がるのではないかと思われる。「古き良き教養」のあり方が失われていくこと自体についての評価は人によって意見が分かれるところだが、もし教養が「人格陶冶」という出自的性格を喪失していく中でなお、現代社会に生き残る道を模索するのであれば、何かそれに代わる新しい教養の理念とも言うべきものが必要とされるはずだ。そして「この新しい教養の理念とは何か」という問いこそが、「教養の未来」を考えるうえで最も重要な問いであろう。
評者自身は、教養文化と大衆文化の相互浸透という本書の示す処方箋を否定するつもりは毛頭ないが、それと同時に、教養を学ぶことそれ自体の面白さや意義を残していくこともやはり大切なことであると思う。そのためには教養を学ぶことそれ自体の面白さや意義を実感・共有できる「場」を作っていく/残していくことが大事になるのではないか。京都アカデメイアもまた、そのような「場」のひとつとしての役割を果たしていければ、と考えている。
(評者:百木 漠)
更新:2013/10/10