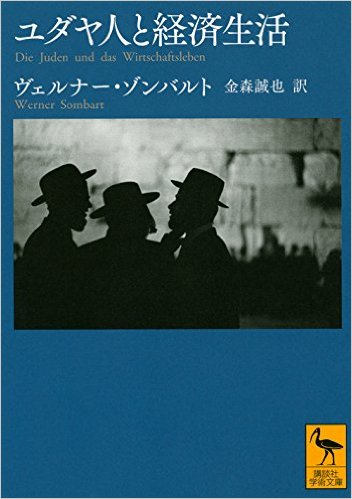 | 書名:ユダヤ人と経済生活 著者:ヴェルナー・ゾンバルト 訳者:金森誠也 出版社:講談社学術文庫 出版年:2015 |
1 ゾンバルトと資本主義成立をめぐる議論
著者ヴェルナー・ゾンバルト(1863-1941)はドイツの経済史家で、マックス・ヴェーバーの盟友にして論敵としても有名である。「資本主義」という用語が学術文献の中で頻繁に用いられるようになったのは、ゾンバルトの『近代資本主義』(1902)という著作の影響によると言われる。ゾンバルトは、マルクスに接近した時期もあったが、「唯物論」からの脱却をはかり、企業家に見られる「資本主義的精神」の展開が資本主義の発展に果たす役割に着目した。この「資本主義の精神」をめぐる議論はあのマックス・ヴェーバーを触発するところが大きく、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の成立(1904/1905)を促したと見られている。
ゾンバルトとヴェーバーは、その後、ヴェーバーの死まで著作上で資本主義の起源をめぐって議論を交わすことになる。ヴェーバーが、近代資本主義の成立にあたってはプロテスタンティズムこそが重要だったという立場を生涯堅持したのに対して、ゾンバルトは様々な要因を多様に描きだし、それゆえ様々なテーゼを並べていった。例えば、『恋愛と贅沢と資本主義』(1912)において、禁欲ではなく、王侯の贅沢や彼ら相手の奢侈品生産が資本主義の発展を促したと主張したのが有名である。今回取り上げる、『ユダヤ人と経済生活』(1911)では、ゾンバルトは、ヴェーバーの見解を踏まえつつ、「プロテスタンティズムと名づけられているものは、その本質的特徴においては、もともとユダヤ教ではないか」と言いながら、資本主義発展にあたってユダヤ人が果たした役割の大きさを示そうとしている。
今年(2015年)この『ユダヤ人と経済生活』が講談社学術文庫に新たに収録されたこともあり、今回これを取り上げたい。必ずしもアクチュアルな意義があるとは思われないが、「資本主義の起源・動因は何だったのか」、「ヴェーバーはプロテスタンティズムの倫理が資本主義の展開を促したと言っているが本当か?」「ユダヤ人と資本主義の関係は?」といった関心がもしあるなら、一読しておいた方がよい古典的著作である。
あらかじめ誤解のないように言っておくと、ゾンバルトはユダヤ人こそが資本主義発展の原因であるとして重視しているわけではない。彼は「あれかこれか」に議論をつきつめるタイプではなく、「あれもこれも、そしてまたそれも」と多様なものを列挙していくタイプの人間である。ゾンバルトにとってのユダヤ人は、資本主義の発展の大きな要因ではあるが、多数ある要因の中の一つである。彼は、ヴェーバーがプロテスタンティズムにこだわったほどにはユダヤ人やユダヤ教にはこだわってはいない。両者の叙述や分析の方法の違いに関して、ヴェーバーは解剖学者に、ゾンバルトは風景画家に例えられる。資本蓄積の合理的な方法化に近代資本主義の精神を見るヴェーバーは、これにひたすらメスを入れながら、その要因としてのプロテスタンティズムを取り出してくる。ゾンバルトは、資本主義的なものを求めて多量の文献を渉猟して歩きながら、「資本主義的」な「風景」をみつけだし、そのつどふさわしい色彩で描きだす。それぞれの風景は、一貫した方法論で描かれる訳ではない。ゾンバルトの研究は相互に矛盾するところもあるが、首尾一貫性のなさゆえに無価値になるわけではないだろう。彼が描き出した資本主義の諸相の重要な一つとしてみた場合の『ユダヤ人と経済生活』の意義を以下で確認しよう。
2 『ユダヤ人と経済生活』
概観
ゾンバルトは、本書で、「ユダヤ人」をもっぱら資本主義に関連する限りにおいて取り上げ、その「経済生活」と資本主義の発展に果たした役割について論じている。この意味でまず、「ユダヤ人」の全体を論じる書ではないとまず指摘しておきたい。ユダヤ人の経済生活を包括的に論じるとすれば、遊牧民としての生活も、農耕民としての生活も検討する必要があるだろう。ゾンバルトのユダヤ人像は、商人・企業家としてのイメージに特化しており、それについて本書はユダヤ人への偏見を強化するものだという評価もしばしばある。ゾンバルトはいわゆる反ユダヤ主義者ではないと見られるが、強欲なユダヤ人のイメージを創り出すことには加担していたことには注意するべきである。
本書は日本では第二次大戦中に訳されている。そのときの訳者は、ナチスの迫害の背景に、ユダヤ人の経済力への反発が大きいと見ていたが、ゾンバルトの著作がユダヤ人の資本主義への影響力を明らかにしているとして、紹介していた。今回書評として取り上げるのは、講談社学術文庫に収録された、金森誠也訳の『ユダヤ人と経済生活』である。本書は三部からなっているが、文庫版では、第1部「近代的国民経済形成へのユダヤ人の関与」の中の一部(第6章「経済生活の商業化」第7章「資本主義的経済観念の形成」)と第三部「いかにしてユダヤ的本質は成立したか」が割愛されている。ここでも、第一部、第二部の議論にしぼって紹介したい(第一部で割愛された内容については、本書評末尾で紹介したい)。ごく大雑把に言うなら、第一部が歴史・資料編であり、第二部が理論編である(ユダヤ人の概念的把握がなされる)。著述のスタイルも内容も、大きく異なっているため、全体の意義づけは、それぞれを簡単に概観したあとで行いたい。
第一部
第一部は、抽象的な理論を打ち出すのではなく、歴史的な資料をもとに、ユダヤ人が近代資本主義形成において果たした役割を概観している。資料は中世から近代にいたるまで非常に多数のものが用いられており、「近代植民地経済の建設」「国際商品取引」「近代国家の建設」といった観点に即して整理されている。王室や国家の金融業者としてのユダヤ人の役割など、広く指摘されることのみならず、ゾンバルト独自の主張も含まれている。
その中で興味深いのは、例えば、経済の中心が16世紀以降、地中海からオランダやイギリスなど北へと移ったことを、ユダヤ人の移動と関連づける議論である。イタリアやスペインから、オランダ、イギリスへと経済の中心が移動したことをめぐる議論は、経済史の中では大きなテーマであるが、ゾンバルトは、これに関して、例えばアメリカ大陸との三角貿易などよりも、端的にユダヤ人の移動が重要だったと見ている。また、アメリカ合衆国のユダヤ的性格についての指摘も目を引くものである。ただし第一部全体を通じて、他の民族が果たした役割との比較が足りなく、またそもそもデータとそこから主張されることの間にあるべき分析が弱いために、説得力が十分とは言い難い。
文庫で割愛された第6章では、債権の商品化にユダヤ人が果たした役割が推測され、第7章では、中世においてユダヤ商人がキリスト教徒たちの経済の中でなぜ、虚言者、キリスト教徒の妨害者、生業の簒奪者とみなされていたかが分析されている。それぞれ興味深いので、後で簡単に紹介したい。
第二部
第二部では、第一部での叙述も踏まえつつ、ユダヤ人の「資本主義的経済人」としての適性について論じている。『ユダヤ人と経済生活』を書くにあたって、ゾンバルトはヴェーバーの議論を意識していたと自ら語っているが、ヴェーバーの議論と関わるのは主にこの第二部である。ゾンバルトは、ヴェーバーの議論を認めつつ、ピューリタニズムの起源にユダヤ教があると論じ、「ピューリタニズムはユダヤ教である」とまで結論づける形で、「資本主義の精神」に親和的なユダヤ人あるいはユダヤ教を見いだしてくる。第二部は第一部以上に玉石混淆でムラのあるもののように思われる。特に興味深い点を中心に以下で簡単に概観したい。
ゾンバルトは、まず第8章において、ユダヤ人と資本主義を関連づけるにあたっての前提を論じている。ゾンバルトによれば、資本主義において重要なのは、営利の理念—―前払いした利益の確保と「利益」の獲得――と経済的合理主義――経営の組織化、合目的性と計算(複式簿記の成立に着目される)の重視――である。この資本主義的理念へのユダヤ人の適性が第2部全体で論じられるのだが、その際に、ゾンバルトは、歴史の中である集団や民族が果たした役割を論ずるときの注意点を指摘している。ここには傾聴すべきものがある。
例えばある民族や、集団が資本主義の形成に大きな意義をもったとする場合に、その集団がおかれた客観的状況が寄与したのか、集団が備えている主観的適性が寄与したのかを整理するべきだと彼は論じている。例えば、ヴェーバーがもっぱらプロテスタンティズムのもたらす「精神」に着目する場合、内面が歴史を牽引したと論じているように見えてしまう。そして、それに対しては、プロテスタントが資本主義的精神をもっていたから資本主義的に成功したのではなく、旧来の身分制では居場所がなかったため、商業によって身を立てる他なかったがゆえに資本主義的に成功したという異論も出てくる。どちらが正しいかということはひとまずおくが、環境もあわせて検討しなければ、歴史的現象の分析としては不十分になるということは言えるだろう。ゾンバルトは、ある意味でこのような問題意識をもっており、ユダヤ人の「精神」が牽引したものと、ユダヤ人がおかれた「環境」が彼らに促したことを区別して論じようといっている。
第9章では、資本主義の精神に則った経済人についての自らの分析を提示する。ここでの議論はほぼ同時期に書かれた『ブルジョア』が詳しい(邦訳あり)。
第10章では、ゾンバルトがユダヤ人のおかれた「状況」と資本主義への適性について大きく四点にまとめて論じられている。(1)その「空間的拡散」のゆえに、「国際的商業・信用協力の拠点」に同一家族の一員が散らばったために、金融取引などで有利な地位を占めたられこと。(2)各地で少数派であったことで、その取引がつねに異邦人との間になされたものだったこと(「異質性」)。(3)土地によって様々ではあるが、なんらかの法的な制限下におかれ(「半端な市民性」)、ギルドなどの団体から閉め出されたことで、「自由主義」的思考あるいは「自由貿易」志向を育てたこと。(4)「富」を蓄積していたがゆえに、王侯や勃興する国家に貸し付けを行えたこと。これらについてはユダヤ人について語る際に彼らの「本質」のように語られることもあるものだが、ゾンバルトは「状況」として説明している。「本質」を設定してそれによって現象の説明を行ってしまうなら、歴史的状況・歴史的環境は無視されてしまう。ゾンバルトの「状況」の重視は、こうした弊に陥らないために重要な指摘であろう。例えばヴェーバー的な「理念型」による議論に欠けがちな点を補完する視点でもある。
ゾンバルトの議論で問題を感じるのが、第11章「ユダヤ教の経済生活への意味」である。ユダヤ教の聖書や聖典に、「資本主義の精神」の萌芽が見いだされていくのだが、「資本主義」的に見えるものが手当たり次第に旧約聖書などから取り出されるような印象がある。
ゾンバルトはこの章ではヴェーバー・テーゼを意識しているように見える。ヴェーバーは、「禁欲」を旨とするプロテスタンティズムが、逆説的に資本主義的な資本蓄積を展開するというプロセスを描きだしていた。プロテスタンティズムにおいて世俗的な富の増加は、神の「召命」=「職業」に邁進したことの証として受け取られた。だが、ここで得られた所得は、散財や享楽にではなく、もっぱらさらなる職業活動のために「禁欲的」に運用されなければならなかった。
ゾンバルトの論証は、このヴェーバーの議論に比べるなら、逆説性もない、わかりやすすぎるくらいのものである。ゾンバルトは、ユダヤ教において地上的な富は神の恩恵にあずかっていることの証としてあることを指摘しているが、ヴェーバーが論じるプロテスタントと違って、ユダヤ人における富の蓄積の論理はもっとストレートである。ゾンバルトはユダヤ教では宗教的掟が神との「契約規則」としてあり、この遵守に関して合理的な判定がなされていることを論じる。神に対する「義」(契約履行)と「罪」(契約違反)とが量化されて把握され、「義」なる行いは、神によって勘定されて死後にまで積み立てられる。そして、プロテスタントとは違って、世俗的な富の追究は端的に擁護されている。以上のようにゾンバルトは論じる。彼によれば、ユダヤ人はユダヤ教の是認もあるがゆえに、利益追究に非常に親和的であった。この辺りの議論は、わかりやすいものだが、単線的で含蓄が感じられず、牽強付会的な引用がなされているような印象もある。この章での議論は、全体として、自身の資本主義的精神—―合理化、利益追求—―に見合ったものを引っ張り出してくることに終始している感じがあって、ヴェーバーの議論のような執念はみられない。
第2部最後の第12章では、以上の内容も踏まえて、「ユダヤ人の特性」についてまとめている。「資本主義は」「すべての質的なるものが純粋に量的な交換価値との関係に基づいて消滅してしまう」がゆえに「そのもっとも内的な本質からすれば抽象的である」とゾンバルトは理解しており、これに、ユダヤ人の「主知主義」「目的論」「主意主義」「可動性」が適合しているとみている。
まとめ
ゾンバルトの『ユダヤ人と経済生活』は、焦点が絞りきられていない印象もあり、例えば、同じく講談社学術文庫に入っている他の著作の方が、評者としては面白かった。ユダヤ人論としても、もっぱら商業・資本主義との関係から扱うが故に、強欲な資本家としてのユダヤ人という固定観念を生み出しかねないという問題点も目に付く。だが、資本主義の起源や、宗教と経済の関係といったテーマに関心があって、一見不毛な遠回りも洞察のための糧となると思える方にはおすすめしたい一冊である。経済史的・ユダヤ史的知識を得る上でも、少なからず参考になる。また、ヴェーバーを交えた当時の資本主義成立論の構図を理解するためにも必読の書だといえる。ちなみにヴェーバーの『ユダヤ人と経済生活』に対する評価は辛く、ユダヤ人は近代資本主義に対しては大きな影響をもたないと反論している。ヴェーバーは、ゾンバルトのユダヤ教に関する論証も評価していない。ゾンバルトは本書でユダヤ人を論じるとき古代イスラエルを考察の外においているが、ヴェーバーは『古代ユダヤ教』を詳細に議論している。両者の観点や議論がいかに異なってくるのかを対比するのも面白いのではないだろうか。
資本主義成立論に関して付け加えると、ヴェーバーとゾンバルトのように「精神」を強調する視点に対しては批判もある。「精神」の合理化・近代化が資本主義の発展を促したという議論に対しては、まずはマルクス経済学からの批判がある。生産関係の資本主義化がいつ、いかなる形でなされたのかを問題にせずに、精神だけを論じるのは、不十分だと指摘される。また、ウォーラーステインにはじまる世界システム論でも、世界経済全体の状況分析ぬきに、「精神」のみを論じることは斥けられている。ヴェーバーの遺産を引き継ぐ立場からは「経済決定論」よりもヴェーバーの思索に深みがあるという主張もなされる。残念ながらこれらの異論をぶつけあって、資本主義成立に関しては何を重視すべきかを検討する議論は多くないようである。評者が見るところ、ヴェーバー、ゾンバルト、マルクス学派、世界システム論のいずれも、(近代)資本主義の本質として、資本の増殖が合理的になされるようになることに見ている点では一致している。お互いに聞くべき所は聞きつつ、それぞれの力点を主張しながら生産的な議論ができるのではないだろうか。ゾンバルトの著書も、こうした議論の活性化の一助となるものだろう。
補遺
文庫ではおそらく分量の問題で割愛されている第6章では、16世紀〜19世紀にいたるまでの有価証券、証券取引所、株式会社などの発展においてユダヤ人が果たした役割が様々に指摘されている。近代資本主義の条件として、ゾンバルトが重視しているのが、脱人格化、事物化という事態であるが、ユダヤ人がこれに親和的だったということが様々な形で繰り返し示される。その中でも印象的な、有価証券取引とユダヤ人をめぐる議論を簡単に紹介しておこう。
ゾンバルトによれば、ローマ法やゲルマン法において、債務関係は当事者個人に帰せられるものとしてあった。債務の請求権が他人に譲り渡されたり、証券債権がそれ自体物件として売買の対象とされたりすることはなかった。債権を脱人格化(「事物化」)することによって、これを有価証券として売買するアイデアをもたらしたのは、ユダヤ人だとゾンバルトは推測している。ゾンバルトはあくまで推測としてのべていて、これが実証されうるものなのか、すでに誤りとされているのかは筆者には未詳である。しかし、一読して興味深いものと思える。
同じく割愛されている第7章では、中世・近世においてキリスト教徒からしてユダヤ人が「違法」と映っていたことやそのときなされた非難をもとにして、この「違法」の意味を明らかにしている。キリスト教徒の商人は法によって定められた身分を越えずに、同業者組合やギルドの範囲でもっぱら活動した。ここにある理念は各人の「生計」の保護であり、「自由競争」はなかった。現在では当たり前の宣伝による購買者獲得は恥知らずな行為とされ、各自は与えられた範囲でやってくる客に売るべきものとされ、商品は生産にかかる費用を基準とする「適正価格」で売るべきであって値下げ行為は同業者の顰蹙をかうものだった。こうしたキリスト教的商業の慣習をともにしなかったがゆえにユダヤ人は批判されたとゾンバルトは論じている。
彼らは自分たちの商品を積極的に宣伝して、街で客を引き、「適正価格」以下の値で売ること(薄利多売)で利潤を獲得していった。キリスト教徒の慣習を共にせず、身分機構・国民経済的理念の外にあったがゆえに、自由に利潤を追求したのがユダヤ人だったとゾンバルトは見て、資本主義的な心性は、ユダヤ人に発するものだと示唆している。
ゾンバルトの著作(おすすめのもの)
『ユダヤ人と経済生活』(金森誠也訳)は、荒地出版社から1994年に出版された『ユダヤ人と経済生活』(金森誠也監修・訳、安藤勉訳)の抄録になっている。また、第二次大戦中には『ユダヤ人と資本主義』の題で第一部が訳されている(長野敏一訳)。この当時は、日本でも、ソ連や連合国の背後にユダヤ人の暗躍を見る「ユダヤ禍論」が(あるいは「日猶同祖論」も)唱えられていた。
『近代資本主義』の第二版(1916年)や晩年の『ドイツ社会主義』(1934年)まで、主要著作のかなりの部分は邦訳されている。資本主義成立・発展をめぐる議論としては、講談社学術文庫に収録されている『恋愛と贅沢と資本主義』が、コンパクトかつ示唆に富んでいて気軽に読むのに面白い。他には金森訳で『戦争と資本主義』『ブルジョア』も出ている。
(評者:小林哲也)
更新:2015/08/21