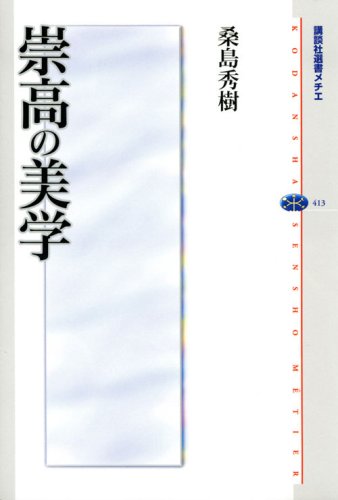 | 書名:崇高の美学 著者:桑島秀樹 出版社:講談社選書メチエ 出版年:2008 |
■ 啓蒙と崇高
以前の書評(奥井智之『恐怖と不安の社会学』)で主題とした「恐怖(terror)」は、現代の国際政治秩序や、それと連動した社会学的な水準での自由の危機状況(高度な管理型社会の出現)を考えるうえでの中心概念であると同時に、じつは現代芸術を考えるうえでも重要なキーワードである。というのも、近代の美学は古典的な調和や均斉美には還元できない「崇高なもの(the sublime)」への注目とともにはじまったともいえるが、この崇高とは一義的にはひとに恐怖を催させるものを意味してきたからである。たとえば、崇高の伝統的な表象として挙げられるのが、「畏怖すべき神(dieu terrible)」である。人知を超えた存在は、ときに自然法則を宙づりにするかのように破局的な自然災害を通じて人間の高慢を罰し、その意志は人間の理性(ないし知性)によってはうかがい知ることなどできない。1755年のリスボン大地震も一般にはこうした視点から神の天罰と受け止められ、民衆にたいする教会の支配をいっそう盤石なものにするはずだった。啓示宗教としてのキリスト教は、超自然的な奇蹟をポジティブな神の恩寵としてとらえる一方で、最後の審判を待望する終末論的世界観のなかでは破局をもたらす神の怒りの表現としても理解した。これにたいしてヴォルテールに代表される18世紀の啓蒙主義者たちは、人びとを無知蒙昧のうちにとどめおく民衆支配の道具だとして、カトリック教会による「迷信」の濫用を批判した。たとえばパンと葡萄酒がイエスの血肉に変わるという実体変化(聖変化)の教説は、錬金術よろしく自然法則をまったく無視した「非科学的」な信念として痛烈な非難を浴びることともなった(ただし、一方でニュートンをはじめとする当代一流の科学者・哲学者たちが錬金術の可能性を信じ追究したことも記憶すべきであろう)。しかし、それでは啓蒙主義者たちがキリスト教を総体として否定したのかといえば、多くの場合そうではなかった。神の意志は自然界の秩序に否定的に介入することによってしめされるのではなく、その驚くべきデザインのうちに内在的に表現されているという、ローマ教会とはことなった主知主義的で自然宗教的なキリスト教解釈も、また可能なのである(このあたりについては以前に論じたことがある。上野大樹「ジャン=ジャック・ルソー:「市民」であるとはどういうことか?」大澤真幸編『3・11後の思想家25』、左右社)。
こうした啓蒙運動の過程で、キリスト教の神はみずからを自然の秩序性ないし法則性をつうじて提示する合理的な存在であることに強調点がおかれ、さらに歴史的には摂理(providence)として顕現される神の愛から示唆されるのは、神が愛情深く寛大な存在であるということであった。この穏和な理想によって、もっぱら怖れるべき崇高な存在として神を表象する見方は、啓蒙の世紀にはどちらかといえば後景に退いたといってもよいだろう。けれども、では啓蒙的人間は古典的な調和的世界のうちにすっかり安らいだのかといえば、もちろんそうではなかった。たしかにこの世を超越した超自然的な存在に恐怖することは少なくなったかもしれないが、近代人の主観は、今度は自然そのもののうちに崇高な対象をふたたび見出したのである。ここに近代美学が誕生する。その嚆矢となったのが、政治思想の歴史にあっては保守主義の元祖とも目されるエドマンド・バークである。
■ 「内在的超越」の運動における主観的感情としての崇高
近代的な美学カテゴリーとしての崇高の中核にある特徴として本書の著者がとり出すのは、もっとも広い意味での内在的な体験としての性格である。もちろん、崇高の語義には人間世界をはるかに超越した絶対的存在を示唆するところがあり、現世的なものの全面肯定のなかに崇高な性質が宿りえないことはいうまでもない。しかし、筆者がとりわけ注目する近代的崇高の核心部分には、そうした超越的で絶対的ななにかがこの主観のうちに生起するというモーメントが存在している。上にみた神学的崇高概念にあっては、世俗的なもの(此岸)と超越的で永続的なもの(彼岸)、現実的なものと理念的なものは実体的に二分され、世俗の人間世界が崇高の領分から絶対的に隔絶されていることが強調されていた。これにたいし、近代美学における崇高のカテゴリーはむしろ「内在的超越」として、つまり超越性という確固とした実体ではなく、自分自身を超え出るような何ものかに向かおうとする、志向性をもった運動として把握されるといってよいだろう。しかも、ここには明確なベクトルがある。崇高はあくまで内在世界がより高きところに超越せんとするダイナミズムのなかで経験されるのだ。これが崇高が主観に定位する感情だという所以である。「人間の認識能力の限界に立ち、そこから先にある「あちら側の」世界を遠望・憧憬しつつ、やはりその臨界点を越え出ずそこに踏みとどまり、ただじっとその臨界点を凝視し続けること。とはつまり、「こちら側」すなわち地上的かつ此岸的な世界で経験される「肉」の苦悩の問題として「崇高(なるもの)」を語るということ」(45頁)なのである。
また、神学的伝統にあっては超越と内在の実体的二分法のもと、人間が崇高な領域へとアクセス可能かどうかをめぐっては、あくまで(人間の)理性や(神の)知性にかかわる問題としてとらえられた。ところが、いまや問題となっているのは主観的な感情の体験である。「事物と人間とのあいだに生まれる感覚作用ないし内的感情」(同)に焦点があてられる。このことは、近代美学の歴史のなかではじめて本格的に崇高に着目した、偽ロンギノスの仏訳者ニコラ・ボアローにも認められる。崇高を「作品享受のさいの強い感情効果」、すなわち「悲劇や大叙事詩を鑑賞する際にしばしば経験される、快と苦の混合感情にともなう心的な高揚状態」(47頁)としてとらえる視点である。
本書で強調されているわけではないが、このようなかたちで人間の情動の動きに注意をむけるモラリスト的といってもよいであろう観察眼こそが、近代美学を成立させたともいえるように思う。というのも、そもそもエステティクスは美学と訳されるが、一義的にはそれは「感性の学」というべきものであり、カテゴリーとしては美よりも崇高に親和的だと考えられるからである。古典的な美の理想は、それが数学的な調和や均整としてとらえられていたかぎりにおいて、感性的認識というよりも理性的認識にかかわっていたとみるべきである。そうだとすれば、美が直接にかかわるのは論理学(合理的哲学)という「上級認識の学」であって、エステティクスという「下級認識の学」(3頁)ではなかったと考えられる。かくして、美のカテゴリーだけにとどまっていたのでは、おそらく美学(すなわち感性の学)は誕生しえなかったとさえ推察することができる。
■ 山岳の崇高美
17世紀のボアローが修辞学の文体論の文脈で崇高をとりあげたのに対し、18世紀につながっていくような自然界のなかの崇高は、とりわけイギリス貴族の子弟の慣習となっていたグランドツアー(大陸旅行)におけるアルプス越えの体験に由来する。人間を圧倒するアルプス山塊のもつ「醜悪さ」は、ルネサンス教養人の修辞学的伝統のなかではたんに嫌悪されるだけのものだっただろう。トマス・バーネットも理性の観点から「神の配列などまったく及んでいない未整理の自然」にたいする否定的評価を一方で共有し、「地球上の凹凸すなわち自然界の大山脈や大渓谷あるいは深い海底は、旧約聖書の大洪水の結果としての「壊れた世界の廃墟(The Ruins of a broken World)」」であって、「罪深い人間にくだされた神のおおいなる鉄槌」とさえ見ていたという(50頁)。だがバーネットは他方で、感性的認識の次元においては「野生の自然」や「広大無辺な山々」に畏怖と崇敬の念を抱いてしまう。アンビバレントながらも自然界に崇高なものを認めるこの感覚が、その後の崇高美学の展開の根底にあると本書はとらえている。
18世紀には、商業社会の発展と市民社会の勃興を背景にサロンやコーヒーハウスで美学談義をふくむ洗練された社交の世界が花ひらく。ただ評者には、このような文明社会の空間のなかで崇高というトピックをどのように位置づけるべきか、やや判断に迷うところもあった。というのも、政治思想の方面では顕著であるが、たとえばポーコックが17世紀の公民的人文主義から18世紀の(とりわけスコットランド啓蒙の)商業的人文主義への変容というかたちで描きだしたように、男性的な荒々しい共和主義思想は、17世紀の革命=内乱をへて商業社会にかなう穏和な観念へと換骨奪胎され、政治言語の焦点も徳(政治的なもの)から作法(社会的なもの)へと移行したとされるからである。こういった趨勢のなかで、穏やかさの理想に容易には回収されえない崇高概念の浮上は、一種例外的な現象にも映じる。
修辞学的崇高論と山岳崇高論という本書の弁別を敷衍するならば、18世紀の社交空間をどう見るべきかという問いにもある程度の応答の方向性をあたえることができるかもしれない(修辞学的崇高については、玉田敦子「18世紀フランスにおける「修辞学的崇高」の成立」、『貿易風』2号を参照)。本章で紹介されているなかでいえば、ジョゼフ・アディソンや第三代シャフツベリ伯、サミュエル・ジョンソンなどはどちらかといえば修辞学的な系譜のなかで仕事をし、全体的な傾向性としては穏和さの理想をもってテイスト(趣味)と作法の洗練・文明化を追求したといってよいように思われる。彼らがあくまでそういった枠内で崇高をいわば飼い慣らそうとしたとすれば、バーネットの山岳美学をより直接に引き継ぐような系譜の崇高論も18世紀には存在した。それがたとえばジョン・デニスであり、ジョナサン・リチャードソン父、そしてジョン・ベイリーであったといえそうである(51-63頁)。峻厳なアルプス登山によって経験されるような崇高の感情は、サロンなどにおける洗練された社交生活に容易に統合できるような代物ではないだろう。
デニスが山岳体験を伝えようともちいた表現を列挙すれば、「歓喜にみちた恐怖」あるいは「恐怖にみちた喜び」、「古い世界の廃墟」であると同時に「新しい世界の最も偉大なる驚異」、「ただ巨大なばかりでなく、恐ろしく忌まわしくぞっとさせるような廃墟」、「大自然の放縦さ」等々。他方デニスもホメロスやウェルギリウスといった古典文芸にも参照を求め、それを読むときに感じる「熱狂の感情」に言及する。アディソンも実際には調和的な美の範疇にはおさまらない「壮大なるもの」を視覚とのかかわりで重視する見解を「想像力の快」論のなかで展開し、「開けた平原」、「広漠たる不毛な砂漠〔荒野〕」、「巨大な山脈」、「高い岩山や絶壁」、「ただ広い水面の広がり」などの例を挙げるとともに、「嵐の大洋」に「是認しうる恐怖」を感受する。
リチャードソン父の絵画への着目は、山岳の崇高美をサロン空間のなかに導入しようとする重要な試みであったようにもみえる。本書によれば、彼は「まず常套的に偽ロンギノスにならって、人間の尊厳ないしは思想の偉大さの反映として、文芸面で「崇高な語法(the language of the sublime)」がもつ重要性を指摘」し、そのうえで絵画も「「快」ではなく「驚異」をあたえるように描かねばならない」、つまり「たんなる自然の正確な模倣ではなく、人間の経験すべてを超越したものの観念、すなわち「完全さをしめすオリジナルな観念」を「創造」しなければならない」と論じる。最後に、ベイリーは穏和でよく陶冶された文明人の理想を掲げる「保守的啓蒙」の路線とはあきらかに異なるかたちで崇高を提起する。崇高は、「「魂の高揚感」ではなく、「行為の端正さ」(decorum of actions)に関連するもの」である徳とは明確に区別されるべきものだというのである。
■ 山岳美学からバークへ
評者なりの視点も加味しつつ以上に詳しくみてきた崇高美学の流れのうちにバークの崇高論をとらえ返すことで、カントへの継承関係にもっぱら注目するだけでは十分に見えてこない、バーク固有の意義をあきらかにすることに本書は成功しているようにみえる。
その核心は、感性的認識における崇高にいたる感情のダイナミズムを明確に描ききったことにあるといえるが、先だってやや付随的ではあるが次の点にも注意をむけておきたい。すなわち、五感にもとづく感覚主義的な美学という特質である。たとえば前述のベイリーは「魂の高揚感」を生じさせうる感覚として視覚と聴覚を重視し、嗅覚、味覚、触覚は崇高とは無関係であると論じていたが(63頁)、これにたいしてバークが展開したのは、趣味にして味覚でもある「テイスト」の論理学であった(65頁)。本書が特に注目しているのは、絵画よりもむしろ詩に注目するなかで、バークにおける崇高が触覚的な特質あるいは感覚的な「関心性」と密接に結びついていた(その点で美感的判断における「無関心性」を強調するカント的な美学とは異質である)という点である(92-95頁)。
さて、均斉(proportion)や調和(harmony)を基準とするスタティックな美の観念とは対照的な、感性的次元において崇高をもたらす快苦のダイナミックな動きとはどのようなものか。ひと言でいえば、諸要素の相対的なバランスのよさが生みだす美がストレートに快をあたえるのとは対照的に、崇高とはいったん苦という否定的な契機を経由することでいっそう高次の快が実現されるという過程をともなうものである。しかもそこでの苦とは美しいものを構成する諸要素の相関性・相対性を一挙に失効させるような、巨大で途方もない性格をそなえていなければならない。恐怖を惹起するそうした苦を除去することによって、美の快とは質的にことなる歓喜(delight)が出来するというのである(65-67頁)。おそらく、人間精神の深い内部観察によって析出されるこのような主観のダイナミズムは、修辞学的な伝統からだけでは把握することは困難だったのではないだろうか。文体論とは多少とも異なったところに現れた、自然のなかに崇高を見出す感受性の伝統が、バークのダイナミックな崇高美学を可能にした最大の要因だったようにもみえる。
本書は次に、崇高論の潮流のなかでもっともよく知られ、引き合いにだされることの多い『判断力批判』でのカントの議論を紹介する。これについては比較的一般的な解説であり、ここでその記述をさらになぞるようなことはしない。むしろ注目したいのは、カントとバークの比較をつうじていわゆる「カンティアン」的な体系化の枠にはおさまらないような論点を析出し、そこから19世紀の「カントの人倫的崇高を迂回する道」や、20世紀の表象不可能性を核とする現代美学の諸問題へとつながっていく水脈を浮き彫りにしている点である。
ただし、イギリスの経験論を旺盛に吸収しながらもやはりどちらかといえばそれを大陸合理論の伝統のうちに統合することで哲学的綜合を実現したと目されるカントも、美感的判断をめぐっては、特に崇高の分析論においてその主観的な側面を重視している。趣味判断はカントにとって、主観的な判断について普遍妥当性を主張している点が肝要である。20世紀になってアーレントも政治哲学の方面で注目したように、普遍法則をただ個別事例に適用するだけの「規定的判断」ではなく、あくまで個的経験から出発して普遍にむかおうとする「反省的判断」がここでは問題となっている(cf. リュック・フェリー『ホモ・エステティクス』)。そのかぎりでカントも主観性の水準に定位しているのであり、そこにおいて「絶対的な大きさ」や「荒々しい力」、あるいは「無限定性」や「没形式性」が通常の認識を困難にしてしまうような独特の事態が、崇高体験として描かれているといえる。
とはいえ、人間の認識能力には収まりきらないような大自然の驚異に直面して感じとられる崇高の感情も、最終的には、そうした恐るべき自然をも克服してしまう人間存在の崇高さや偉大さ・尊厳へと議論が回収されることになるという点も、やはりカントに特徴的な部分だといわねばならないだろう。このカント的転回を迂回するような崇高論の系譜を描こうとする点に、本書の特質は見出される。そして、このカントを迂回する道において本書がとりわけ注目するのが、ジンメルの山岳美学である。
■ ジンメルの山岳美学にみる崇高
崇高を人間存在の特質へと転回させるカントの人間主義的な理解をいったん括弧に入れるとき、崇高という概念を「もういちど人間を取り巻く神秘の大自然の側にぴったりと寄り添ったかたちで捉え返」そうとする、19世紀の「山岳」と「大地」をめぐる美学思想への流れが見えてくる。カントの人倫的崇高とは別様のあり方、すなわち「地上あるいは地下世界に存在するモノのしっかりとした凝視から立ち現れる、物質的=肉的な「崇高」概念の可能性」である。本書では、ジンメルの「山岳美学」とラスキンの「地質学的美学」に焦点があてられる。
ここではジンメルについて扱われた箇所のみ、議論を要約しておきたい。「人間」と「山岳」を作品のモチーフとしてみたとき、次のような対比が見出せるとジンメルは論じる。「人間のほうは、巨大な彫像でも細密画でも表現できる。だから人間は「さまざまな寸法において常に美的価値を失わずにいる」形式=かたちをもつ」。対するに、アルプスを考えてみると、形式を無効にする圧倒的なその量感にこそ、アルプスの唯一の本質=形式(エイドス)は認められる。そしてそれゆえ、「どんな絵であろうと、アルプスの圧倒的容積の印象に匹敵することはできない」(「アルプスの美学に向けて」)。日本とスイスの国交樹立150周年を記念した2014年の展覧会が記憶に新しいホドラーやセガンティーニの山岳画では、洗練された様式化と卓越した技巧によって「アルプスが本来的にもっている「表象(=形式化)不可能性」が首尾よく回避・矯正され――「美しいアルプス」という去勢されたかたちで――表象されているだけだ」と、ジンメルは手厳しく批評する。だが逆に、そうした技巧的な様式化をともなわないならば、今度は没形式のアルプスの山塊など、形式の統一性を重んじる画家たちにとっては「我慢のならないオブジェ」にしかすぎないということになる(114-6頁)。
こうした行論は、一見すると前述のカントの崇高論に近い。人間とは対照的にアルプスは形式に収めることのできない無限の量をその本質とするというのは、カントでいえば「数学的崇高」に相当するだろう。けれどもジンメルは、そこから「力学的崇高」を介して人間理性の崇高化へとは向かわない。山岳に数学的崇高を見出すその自然観察は、超感性的な領域(道徳)へのステップとしてではなく、あくまで感性的な領域における「限界」の経験にとどまってこれを注視するというしかたでなされている――たぶんこう言ってよいだろう。「ジンメルの考察がむかうのは、人間の側の「精神」性ではなく、アルプスの側の「自然」性ないし「物質」性のほう」(118頁)だった。
こうして、ジンメルのアルプス美学は「徹底して具体的な山岳景観のもつ諸相をめぐる空間的・力学的印象分析に終始する」(同頁)。アルプスが見せる景観は、三つの空間へと区別される。(1) 山塊上部=万年雪の山頂、(2) 山塊下部=岩と氷の山腹・岩壁、(3) 牧草地の背景としての山岳全景=山麓、この三つである。おそらく一般に山々の崇高さとは、(2)の山塊下部から垂直方向のクローズアップ・アイで山頂を遠望する眺めとして、まずイメージされるのが普通だろう。だがジンメルは、隆起と侵食という垂直方向に働く強い力を感じさせる(2)の景色だけでなく、それとは対照的に「もはやダイナミックな要因が働く余地を感じさせない」(3)の山頂からの眺めがあわさって、山岳美の本質が構成されていると考える。「絶対的な高さ」を感覚させる山頂の光景に、ジンメルは「神秘的な崇高」を認める。「アルプスの際立った高さ、崇高さというものは、万年雪の風景においてあらゆる峡谷、草木、人間の住居等が消え失せてしまったときになってはじめて、つまり、高さの印象の必要条件と思われたものがすっかり視界から除かれたときになってはじめて、まざまざと感じられる」(「アルプスの美学に向けて」)というのである。
この崇高な風景は、「完全に「完成してしまった」もの」である。それは「芸術的観察や造形をつうじてのいかなる完成も、救済も求めず、むしろ、みずからの存在そのものの圧倒的な重みをもって、その種の観察や造形に対抗している」(同)。山腹から山頂をめざしているときには感じとられるであろう垂直的ダイナミズムを喪失してしまっているがゆえに、この万年雪の風景は、夏も冬もない「絶対的に「非歴史的な」光景」だとジンメルは述べる。それは「時間における没形式」を体現している。天高く聳える山塊のもつ崇高さは、かくして、造形芸術によって再現(=再現前化)されて完成される必要のないもの、あるいは芸術をとおして完成させる余地など存在しないものだということができるだろう。
他方、(3)の山麓に広がる「森と牧場」ないしは「渓谷と小屋」といった下界ののどかな風景は、アルプスの崇高さにかかわるものではない。麓に広がる平原を中心とした景色のなかでは、アルプスの山塊は「風景の冠」として戴かれるにすぎず、それは「美しいアルプス」ではあっても「崇高なアルプス」ではありえないとされるのである(120-4頁)。
カントとの対比をいったん括弧に入れれば、こうしたジンメルの分析もやはりずいぶんと観念的に聞こえるかもしれない。だが、ジンメルのスタンスは、あくまで徹底して感性的な世界にとどまり、そこで立ち現れてくる光景をつぶさに観察し描写するというものだ。留意すべきなのは、そうした態度と狭い意味で経験論的で実証主義的な態度とは、区別されねばならないという点である。実証主義的な視点を前提としてしまえば、ジンメルの観察も思弁的だということではカントと大差ないと判定されてしまうだろう。ところが、そうした実証主義的なスタンスの実態は、比較的単純な形式と図式を前提として、その図式に沿って切りとられた観察結果を蓄積していくだけのプロセスである。これに対してジンメルがめざすのは、徹底した自然の描写(description)のなかで、そこに内在するかたちで観察の前提である図式・形式そのものを無化してしまうような体験の水準が立ち現れてくる――そうした描写であり観察なのである。
■ 廃墟・アルプス・海
アルプスには、一方で、茫漠たるカオスをなして不連続に連なる巨大山塊が体現している「地上的なもの」が、他方で、山腹中央から天にそびえる岩峰や氷壁、山頂にみられる万年雪の銀世界が象徴する「天上的なもの(=超越的なもの)」が、二様に見出される。一方は「どのような形式にも不足なもの」であり、他方は「どのような形式をも凌駕するもの」である。こうした二種類の対照的な没形式性が、アルプスには存在するとジンメルはいう(118-9頁)。彼によれば、「形式=かたち無きもの」は、生命も意味も持たない。アルプスのもつ「生からの疎遠さ」のうちに、「高山アルプスの与える印象の窮極的な秘密」はあるという。これは、「生の象徴」でありダイナミックな「生の形式」の極みである海がもつ特徴と、対照的である。絶えざる運動と流動のなかで生命が躍動する海とは正反対に、アルプスは「生の形式たる時間的動性からの無縁さの象徴」であり、そこでは「生成し消滅する人間の運命との観念連合が断ち切られている」というわけである(119-120頁)。
他方、アルプスは「廃墟」と似ている。『哲学的文化』のなかの廃墟論は、建築というものの本質を指摘するところからはじまる。「精神の意志と自然の必然性とのあいだの闘争に和平がもたらされ、上方をめざす塊と下方に働く重力とが決算されて厳密な方程式が成立するのは、ただひとつの芸術、すなわち建築においてのみである」。だから、美しいバランスをしめす建築が崩壊し廃墟と化していくとき、「自然そのものの諸力が人間の作ったものを支配しはじめる」。そしてこのバランスのずれは、「やがて宇宙的な悲劇へと転化する」。(なお廃墟論の前世紀から続く水脈をめぐっては、富永茂樹「廃墟の18世紀――あるいは甘美な憂鬱の夢について」(『都市の憂鬱』、新曜社に所収)をぜひとも参照されたい。)
廃墟とアルプスに共通するのは、したがって、「没形式性」だといえる。それはすなわち「造形芸術化不可能性」であり、「作品化(制作)不可能性」である。著者はここからさらに、廃墟とアルプスとには共通して「「自然(ピュシス)」ないし「素材(ヒュレー)」に潜在する「力」の優位が認められるのではないか」という、興味深い示唆をおこなう(124-6頁)。私見では、それ自体は動力をもたない惰性的=慣性的存在(inertia)として質料をとらえ、いわば形式のうちにはめ込まれることではじめて形をとる(デュナミスからエネルゲイアへ)と考えるアリストテレス主義の目的論的自然観は、近代科学の機械論的自然観によって超克されたと一般に考えられているが、たとえばスピノザ主義の流れを念頭におくと、事態はそれほど単純ではないだろう。イデア論(形而上学)批判ないし目的論批判は、静態的に構造化された目的論的宇宙を欠落させた「力の思想」、「潜勢力の思想」、さらには「マルチチュードの思想」の方向にも展開され、おそらく非目的論的な有機体の観念は、ジンメルをひとつの起点とする「生の哲学」の潮流を形成することにもなると考えられるからである。この論点については、18世紀から19世紀へのスピノザ主義(特に情念の力学と統治術を焦点とする政治的なスピノザ主義の流れ)の転回をフレームワークとして、さらに考察を深めていけるのではないかというのが評者の考えである(この流れを19世紀から20世紀に延ばして考えれば、ベルクソンからベルクソニアンとしてのドゥルーズへという系譜関係まで問題とすることができるだろう。この点については、千葉雅也『動きすぎてはいけない』の書評も参照のこと)。
ちなみに、ジンメルが近代登山における精神主義と人間中心主義を嫌い、初期のころからそれとは異なるアルプス論を構想しようとしていた点にも、本書は簡単に触れている。アルペンクラブに属する多くのスポーツ登山者が共有していた「物質の抵抗に対する人間精神の勝利」といった精神主義は、カント的な人間主義を通俗化したものの一形態だとみることもできるだろう。著者によれば、「ジンメルは、だから、彼らスポーツ登山者のもとにある「主観的で、エゴイスティックな(山岳)享受」を、本来的な「修養=成長」(Bildung)――いっぱしの「おとな」に成長するための地上的な受苦・試練のプロセス――と見ることを認めません。彼の目からみれば、こうした冒険的登山者は、賭博師と同様に、「純粋に主観的な興奮と満足のために、みずからの存在を賭ける」軽薄なものたちにすぎないのです」(127頁)。マッチョな克己的精神の理想とは異なる、しかしなお崇高というべき山岳体験を、どうにか言語化しようとジンメルが考察を重ねたことがわかる。
■ 崇高の否定神学
ジンメルに続けて、本書(第3章)ではラスキンのJ. M. W. ターナー作品の批評にみられる「地質学的美学」が論じられ、さらにその「天」よりも「地」――岩や渓といった大地そのもの――を志向し愉しむ美学の観点から、日本の近代登山の歴史が読み解かれていく。話題となるのは、『日本風景論』を著した志賀重昂におけるジオ=グラフィと和漢詩学の融合、近代主義的な登山の理念としてのピーク・ハンティングの展開と第二次大戦前後の遠征調査登山(京都大学学士山岳会の今西錦司、西堀栄三郎、桑原武夫、梅原忠夫たちや、慶応大学山岳部の大島亮吉、槇有恒ら)、木暮理太郎やワーズワース研究者田部重治の『日本アルプスと秩父巡礼』にみられるような――冒険的登山へのカウンターパートとしての――自然融和的でバーバリズム的な山歩きの美学、秘境・黒部を下降する景観にピーク・ハンティングとは異なる魅力を見出した冠松次郎の渓谷美学、等々である。
一点だけやや気になるのは、近代日本の山岳美学を評価する基準が、あまりにラスキン=ターナー的視点に寄り添いすぎているように見受けられる点である。アルプスでの山岳体験と秩父でのそれとを比較する田部の山岳美学に確認できる「山の頂き(ピーク)ではなく、森林のなかへ、さらには渓谷の底へ」というベクトルには、たしかに、天ではなく地へとむかう地質学的美学のまなざしが認められる。しかし「自然克服型」とは真逆の「自然融和型」の森林逍遥には、まったき物質=肉の世界にあって経験される「苦」との直接的対峙が欠落しており、自然の混沌や不可解さの体験、存在の根幹を揺さぶる「脅威」や「畏怖」の念が不在だとされる。なぜなら、そこでは「すでに山は、すぐさま温かく包み込み、一体化を呼びかける安住すべき「母性」」だからである(173-5頁)。
ラスキン=ターナーの美学は、天ではなくあくまで地に沿いながらも、その大地と死の世界(地下世界)を凝視するまなざしの徹底において、逆説的に「天上なる超越世界の「聖性」との出遭い、すなわちキリスト教的な「神(ゴッド)」の現出が最終的に期待されている」。対して、日本の自然融和的な美学では、「野趣に富む大自然のなかで「生」の充溢とそのダイナミクスに埋没し、融解し、陶酔してしまっている」。「生身の人間には達しえない超越的な天上世界(ないし、地下冥界)という観念をもたないため、自分が「肉」をもつ有限者であることなど意識せずに済むというわけ」である。おそらくその背景には、「山岳体験のなかに森の発する「雲気」すなわち生命エネルギーの産出をみる東洋的自然観の伝統」も存在しているだろう。田部や冠の地へ向かう山岳美学にあっても、厳しい「西洋キリスト教世界の神(ゴッド)の観念――天上の超越世界と地上の感性世界といった厳然とした区別――が欠如している」といわざるをえないというのが、著者の見立てである(184-5頁)。
この区別じたいは、評者にはたいへん重要な指摘に思われる。此岸と彼岸の区別に立脚する西洋の神学・形而上学の伝統を表面的には否定したカント哲学ばかりでなく、地上から天への志向自体を逆転させた19世紀山岳美学の潮流にあっても、じつはいわば裏返されたようなかたちで(一神教的な)超越性の痕跡が回帰している点にこそ、西洋的「崇高」の理念の核心はあるように思われる。だから、いくら西洋に由来する近代・現代文明が伝統的な超越性の前提を破棄したように思われても、そもそもの絶対的な区別を欠いた多神教的世界のなかのポストモダンとは、根本のところでどこか異なってくるのである。現代思想にいう否定神学的/郵便的の区別を、ここに重ね合わせてもよいだろう(詳しくは、内田樹『他者と死者』の書評を参照)。それゆえ、西洋近代の思想や法・社会制度がいくら普遍妥当的に見えたとしても、それを根幹で支えている崇高や尊厳といった観念を皮膚感覚として理解するという課題まで視野に収めるならば、ヘブライズムの一神教的伝統の深い理解が実際には欠かせないのである(こうした相違が、東洋的伝統においては「人間の尊厳」が(あまりに)容易に「生命の尊厳」へと移行しうるという事態をも部分的に説明するだろう)。
だが、たとえばヒュームが『宗教の自然史』で論じたように、多神教から一神教への人類学的な進化過程を想定して両者の質的断絶を埋め合わせるようなことは、こんにち容易に是認することはできない。表面的には非西洋圏でも受容されつつあるようにも見える(見えた)近代的な制度や理念も、それを真に「受肉化」できているかどうかが問われざるをえないような局面では、文明論的な基底における差異がふたたび顕在化せざるをえない。そうなると、美学の領域においても、形而上学的要素を最大限に斥けながらもなお否定神学的に観念されるような「崇高」の理念を基準として、そこに到達しているかどうかでさまざまな美的世界観の評価をくだしていくことには、やはり慎重でなければならないだろう。
評者も参加している「尊厳」概念のアクチュアリティをめぐる科研費の共同研究プロジェクト(代表者は加藤泰史・一橋大学教授)では、おそらくカントに由来する尊厳と崇高の概念的結びつきも念頭におかれながら、自然美学をめぐるワークショップが継続的に企画され、これまでマルティン・ゼール、ジェーン・ネラー、ヴォルフハルト・ヘンクマン、エヴァ・シュルマンらが招聘されて講演を行った。そのなかで評者が個人的に感じるのは、一時期ポストモダン旋風を経験したフランスのアカデミズムと比較しても形而上学的伝統の色濃いドイツの哲学界との対話では、――もちろん明示的には哲学的伝統の神学的伝統からの峻別を強調するが――宗教文化の水準をも射程に収めた一種の文明論的な議論が欠かせないということである。たとえば近代の(形式主義的で普遍主義的な)人権思想の“鍛え直し”が問題となるときには、法権利論的な水準にとどまらず、そこから精神的・倫理学的・価値論的な水準にまで遡っての考察が必ずや必要となる。そこでは、いわば人権を背後で基礎づけるような次元にある、尊厳や崇高の観念が問題となってくる。この次元での哲学的考察を主題とするとき、長期の文明的特質を大きく規定する宗教や信仰の問題も、やはり考察の対象から除外することはできないのではないだろうか。
(評者:上野大樹)
更新:2016/07/11