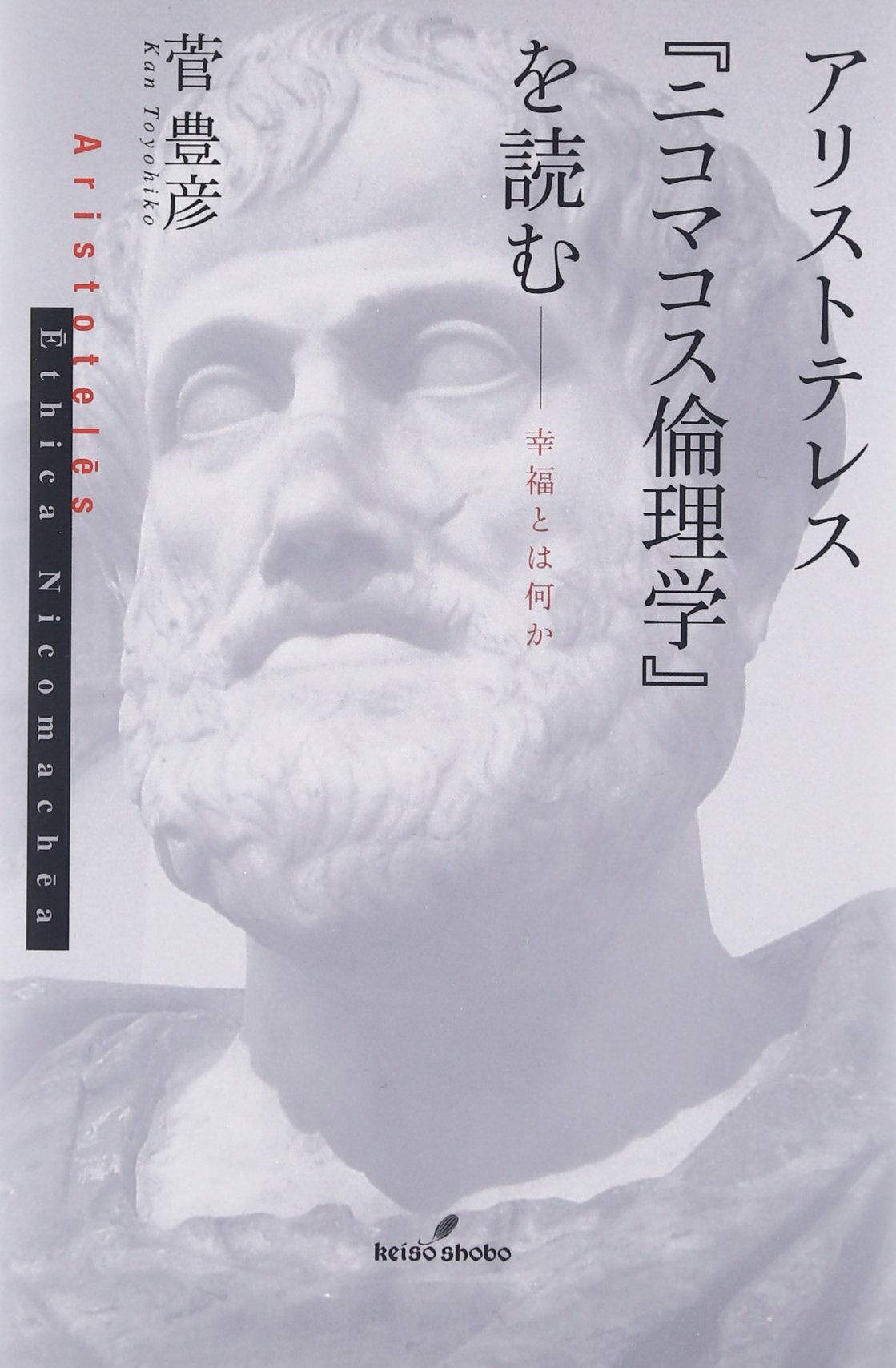 | 書名:アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む――幸福とは何か 著者:菅豊彦 出版社:勁草書房 出版年:2016 |
◆ アリストテレス・ルネサンスとは?
思想史の領域では、文芸復興(ルネサンス)における政治的人文主義・古典的共和主義への関心の復興がケンブリッジ学派を中心に生じているが、現代の規範理論の領域でも、政治哲学におけるコミュニタリアンや倫理学における徳倫理の台頭はめざましく、そのすべての中心にいるのがアリストテレスである。その意味で、やや意外なことに、アリストテレスの現代的復興は、今日の人文諸学にあって数少ない領域横断的な特徴になっているといえる。
ところが、そういうわけでいざその最大のテキストの一つである『ニコマコス倫理学』を紐解こうとしてみると、多くの人は難渋し壁にぶつかることになる。古代哲学や古典文献学の専門家でもなければ、なおさらである。苦心して精読し、個々の章の内容理解はある程度までできてきたと感じられても、なおその全体像が結ばれることはなく、なんともつかみどころがないという印象が残る。どうやらその一因としては、普遍的知識人であるにせよアリストテレスもやはり古代人であって、近代人とはかなり根本的なところで違う世界を生きている、相当に異なった世界観をもって事態を眺めているということがあるようだ。個々のピースをかりに多少とも理解できても、それらをそこに位置づけるべきフレームが的外れでアナクロニズムに陥っていれば、それらが全体として一つの絵を描くことはないだろう――。
そこで、虚心坦懐に原テキストを読み解こうとする姿勢をまずはいったん括弧に入れて、アーレントやシュトラウス学派といった、現代のすぐれたアリストテレス読みを導きの糸としながら全体的な解釈フレームをそれなりに構築し、そのうえであらためてテキストの個々の論述に立ち返って再帰的にフレームを微調整していく(一種の反照的均衡)という戦略が浮上する。もちろん、現代政治理論の研究者にしばしば見られるような、アーレントやシュトラウスだけでアリストテレスのイメージを完成してしまってそもそも原テキストをろくに読もうともしない姿勢は論外であるにせよ、観察の理論負荷性からいっても完全に虚心坦懐な読解というものがありえないのだから、現代の有力なアリストテレスの読み手にまずは頼って、全体的フレームについての暫定的な仮説的理解を得ることは、至極まっとうなことである。ケンブリッジ学派の最大の大家のひとり、J.G.A.ポーコックでさえ、近世ヨーロッパにおけるアリストテレスの影響を文脈主義的なしかたで――そのかぎりで実証的に――検証としようとするときに、じつはそれらを眺めるための(さしあたりの)眼鏡をアーレントに大きく影響されるかたちで構築したことを告白している。ところが、共和主義の思想史研究で注目が行きがちな『政治学』ならともかく、『ニコマコス倫理学』となると、そうしたアーレント製の眼鏡ではどうもピントがずれているのではないか、あるいはアーレント的なアリストテレス解釈ではこれまで蓄積されてきた専門的なアリストテレス倫理学の研究(日本のアリストテレス研究はたいへんな厚みを有する)の多くに整合的にアプローチできないのではないかという疑念が出てきてしまうのである。
本書の特徴的な点は、とうぜんアリストテレス倫理学に徹底的に内在する研究でありながら、従来の研究よりも『政治学』との関係性を意識し、『ニコマコス倫理学』における実践的(活動的)生の自立的で固有の意義を明確にしながらテキストの包括的な理解を提示しているところにある。「〔アリストテレスは〕「倫理学」を「政治学」の一部と見なしていると言える。これは個人の「善き生」や「幸福」はポリス(国家)全体の「善きあり方」をまってはじめて可能になるという考えに基づいており、現代と異なり、古典ギリシアにおいては、倫理学は政治学と一体のものと捉えられていた」(23頁)。こうした意味で、古代哲学の専門研究という視角からだけではなく、むしろアリストテレスをしっかりと理解しなければいけない近世史の研究者や現代政治理論・倫理学研究者にとって、『ニコマコス倫理学』にアプローチするための格好の手引きとなるのがこの本である。
◆ 共和主義・コミュニタリアニズム・徳倫理学――アリストテレス復興の諸相
本書の各章の内容に入っていくまえに、アリストテレス(主義)をめぐる今日の議論状況にかんしてすこし外在的な言及をしておきたい。冒頭で触れた現代のアリストテレス復興が重要な影響をおよぼしている倫理学(徳倫理)、政治哲学(コミュニタリアニズム)、思想史(近世共和主義)の三つの領域で、相互の参照関係が比較的薄いというのは、少々驚くべきことである。とりわけ、(歴史研究それ自体ではなく)現代の規範理論の探究を中核とする点で共通するはずの徳倫理学とコミュニタリアニズムのあいだで、それぞれの領域での研究の進展が他方の領域にあまり影響を与えているようには見えないというのは、不思議な現象である。両分野でいまなお共通して頻繁に言及されるのは、もはや古典となった『アフター・ヴァーチュー』を著したマッキンタイアくらいではないだろうか。
まず徳倫理学と共同体主義の関係性を見てみると、(評者が政治哲学畑のため後者の観点から前者を眺めているという感じは否めないが)徳がその核心において共同的で社会的なことがらであるという点を思いのほか重視していない傾向が、現代の徳倫理学の多くの議論には見受けられる。その原因としてはおそらく、徳倫理学が先行する義務論(カント主義)や功利主義に対する対抗関係のなかでみずからの倫理学理論を打ち立てようとしたという文脈があるため、行為の帰結(功利主義)や行為それ自体(義務論)に道徳的重要性を見出すのではなく、そうした行為をなす主体の性格特性ないし人格に道徳性の源泉を認めるのが徳倫理だという構図が前面に出てくるという事情があるように思われる。人格(行為主体)/行為/行為の帰結という三者のなかでどのアスペクトに重きをおくか、こうした観点から功利主義や義務論と並んで徳倫理の特質が把握され、整理される。そして、倫理的判断が求められる種々のケースにかんして、それぞれの規範理論的立場から考えるとどうなるのかが問われることになる。そうした倫理学の典型的な問題設定に乗っかる以上は、義務論や功利主義と同じく、ある所与の状況にあって各人は(あるいは「あなた」は)どう判断し行動するのが正しいのか、善いことなのかという問いが主題となり、各個人、とりわけ「わたし」や「あなた」という主体がある問題状況や道徳的ディレンマに直面するという構図自体は、徳倫理においても前提となる傾向が生じてしまうのである(ただし善さの行為者相関性は、徳倫理学の枠組みでも十分強調される)。ところが、主体の性格特性としての徳というとらえ方は、もちろんそれ自体では古典古代哲学の特徴の把握として誤りではありえないものの、このとらえ方が同時に、有徳な人間は(少なくとも人間存在の本質的なあり方の一つにおいて)共同的な存在者であり、美徳は共同社会ぬきには考えることもできないという認識と表裏一体であるという点にも着目するならば、現代の倫理学の問いの設定自体が問いなおされなければならなくなるだろう。アリストテレス主義倫理学は、すぐれてコミュニタリアン的に理解されたとき、現代の徳倫理学の主流よりもよりラディカルに、現代倫理学の問題設定そのものを批判するものとなる。また、善と徳の多元性にもかかわらず、あらゆる徳に根源的な特質として、名誉や尊厳(あるいは公共空間への「現れ」)がクローズアップされることにもなる。
次に、コミュニタリアンの政治哲学と思想史における共和主義研究との関係性についていえば、テイラーやサンデルに顕著なように、一定の参照関係が確認できるのはたしかである。ただ、たとえばサンデルなどは、家族や地域共同体の意義を重視することと共和主義的な理念とのあいだにあるギャップに必ずしも敏感だとはいえない。共和主義の歴史研究の観点から見れば、人間の社会性と人間の政治性との区別、つまり人間が社会的・共同的動物であることと政治的動物であることとの差異と連関には、もっと意識的である必要がある。共和主義の伝統には、一面である種の反家族主義・反部族主義の要素もふくまれているからである。人間は第一次集団としての家族を形成し、さらに家族が集まって氏族や部族(あるいは地縁集団としての地域共同体)を形づくるが、文明の最高段階においてはそれらがさらに集合してポリスという政治共同体を建設する。氏族・部族共同体とポリス的共同体のあいだには決定的な相違があるというのが、多くの古代ギリシア人たちの考えである。なぜなら、ポリスは人間の政治的動物としての本性を実現しうる唯一最高の共同体であり、善く生きること(ト・エウ・ゼーン)を目的とするのに対し、人びとが家族や部族共同体を形成するのは、基本的にはただ生きること(ト・ゼーン)をより効果的に達成するためだからである。言いかえれば、ポリス共同体は「政治的動物」としての人間の本性を表現するのに対して、部族共同体はたかだか「社会的動物」としての人間本性を実現したものにとどまり、それは――エルゴン・アーギュメント(本書の第1章を参照のこと)からすれば――人間の種差的な本質を実現するものというより、ほかの動物と共有する性質の反映にすぎない。アガンベンが強調したビオスとゾーエーの対比に、この区別を対応させてもよいだろう。
ただし、たとえばアーレントが古代ローマ的伝統に見出した社会的動物の観念と近代に勃興する「社会的なもの」とをもっぱら重ね合わせるのに対し、ポーコックがしたように、18世紀における政治的なものから社会的なものへの重心移行を(徳から作法へと読みかえて)何ほどか積極的な事態としてとらえ返すことで、近世共和主義の商業人文主義的な変形と穏やかな共同体主義を結び合わせることはできるだろう。すなわち、人間の本性的な「社交性」を(さらにはその「遊戯性」を)強調する議論である。ここでの――サロンやカフェを舞台とする――穏やかな社交や遊戯は、それ自体で目的であるという意味で、政治的行為・言論活動にも等しい幸福(エウダイモニア)の営みであるにもかかわらず、それは喧噪の絶えない共和国の討議=闘技空間からは多かれ少なかれ切り離された、穏和な商業社会を舞台とするものとされるのである。だがそれでも、スコットランド啓蒙に典型的にみられる商業的人文主義によるシヴィック・パラダイムへのこうした応答(≠マンデヴィル的な拒絶ないし無視)にもかかわらず、古典的共和主義者の商業主義(重商主義)批判はなお鳴り止むことはなく、一定の影響力をもちつづけた。(プレブスとパトリキのあいだの)分裂と不和がもたらす、公民的というよりは群集(multitude)的な共和国の活力を古代ローマの繁栄と拡大の源泉とするマキァヴェッリ的共和主義は、今日でも、共和主義的な「政治的なもの」の概念を社交や作法といった新たな「社会的なもの」へと還元してしまう穏和な人文主義的理想から、みずからを差別化しようと企てているのである(cf. サンデル『公共哲学』、ウォルドロン『立法の復権』など)。
◆ プラトン的/カント的合理主義の批判――個別的状況の重視と慣習による性格形成
本書の中心にある論点は、アリストテレス倫理学とプラトン的および近世的な普遍的合理主義とのあいだの重大な差異を看過する従来の解釈への批判である。たとえば、近世のカントや功利主義では、ある行為が道徳的であるかどうかは道徳の一般原理との合致によって判断されるが、アリストテレスはそもそも徳や性格特性をそうした形で基礎づけようとしていないことが強調される。道徳的な行為は、究極的には、道徳の一般法則を個別の事態に下方的に適用し特殊化されたもの、カントの判断力論でいえば規定的判断に相当するものであるというのが、カントと功利主義に共通する特徴である(三段論法のオートマティックな推論を想定すればよいだろう)。こうした「普遍的な規範」を「個別的な事例」に適用するという図式は、アリストテレスの思慮(実践的推論)の解釈にもしばしば適用されてきたが(注1―省略)、著者はこれを批判し、「「思慮」は「思慮ある人」が具体的な状況に直面して、その状況を捉える知覚的把握(小前提把握)を通して示されるという見解」を採用する。この見解は、「われわれが、伝統的に受け継がれてきた文化のなかで「性格の徳」や「思慮」の概念を習得していくことを強調する「内在主義」と結びついている」(vii-viii頁)。
「規範-事例」型の推論解釈との対比のなかでアリストテレスの倫理学を特徴づける著者の解釈は、近世倫理学との違いだけでなく、ソクラテス・プラトンとアリストテレスの違いをも同様に説明するものと思われる。つまり、行為者が対峙する個別的状況を重視するアリストテレスの内在主義は、ソクラテスやプラトンの普遍主義・理性主義との対決を通じて培われたという議論である。プラトンの「善のイデア」論は、もっとも一般的で普遍的なものからすべてのより個別的で特殊的なものは演繹的に導出されるという点で、先の「規範-事例」型の道徳理論とパラレルだといえる。アリストテレスはプラトンのこの議論を批判し、善にはさまざまなカテゴリーごとに質的に異なる固有の善さというものが存在すると述べ、そうしたそれぞれに自立的な性格をもつ諸善が単一の善のイデアに収れんするという主張を論駁する(29-31頁)(注2―省略)。今日の徳倫理学ではしばしば善や徳の多元性・還元不可能性が強調されるが、これはプラトンと比較した場合にアリストテレスに顕著な見方だともいえる。また、プラトンが倫理的な探究においても経験的なものに縛られることのない超越的なイデアを志向したとすれば、アリストテレスは善や徳、最高善としての幸福を探究するなかでも、経験的なものを重視してそこに到達しようとしている。すなわち、経験を超えて無媒介的にエピステーメ(真理の知)に向かうのではなく、ドクサの一種であるエンドクサ(人びとが抱いている定評ある見解)を導きの糸とするのである(31-2頁、83-4頁)。
プラトンやカントの理性主義・普遍主義との対照を通じて浮かびあがるアリストテレスの内在主義・個別主義は、徳の定義や本質ではなくその時間的な形成・発達に注目していく彼の徳論にも決定的に反映されている。「どのように子どもを善き人へと育てるか」(17頁)という徳の教育論がアリストテレスの基本的視座であり、かくして経験的・実践的で歴史的な要素が徳の理解にとって根本的であることになる。本書は、こうした視角から、思慮を(普遍的な理性法則との合致のような)理性主義に近づけて解釈する議論ではしばしば軽視されがちな「性格の徳(倫理的な徳、エーティケー・アレテー)」がアリストテレス倫理学に占める意味を重要視し、諸々の性格の徳をつかさどる位置にある「思考の徳(ディアノエーティケー・アレテー)」としての思慮にかんする第6巻での議論も、あくまで先行する第2巻から5巻までの性格の徳についての経験的アスペクトを重視した議論からの延長線上に位置づけて、把握される。こうした読解は、思慮についての近代的解釈とは異なる本書の説得的な解釈を可能にしている。すなわち、思慮は「学問的知識」と同じ思考の徳であるにもかかわらず、演繹的推論(規範-事例型の推論)とは構造的に異質な実践的推論において働き、個別具体的な状況の感覚的把握を実現する徳性であって、思考の徳ではあっても理論的・観想的な思考とは決定的に異なる、実践的で実存的な徳だという把握である。そしてその意味で、性格の徳ばかりでなく思慮という徳も、伝統的に受け継がれてきた共同体の文化のなかで時間をかけて習得されていくものだということが強調されることになる。
◆ 慣習的に習得される(実践的な)徳としての「性格の徳」
以上の視角から、まずは性格の徳についての検討が本書第2章で、続いてそれらと思慮との関係についての考察が第3章で、順に展開される。人間の魂は「ロゴス(理性・言葉)をもつ部分」と「ロゴスをもたない部分」に分かれるが、両者は明確な二元論的区分ではなく、後者は父親の言葉に耳を傾けるように「ロゴスに耳を傾ける(がそれ自体はロゴスをもたない)部分」である。「ロゴスをもつ部分」の徳が思考の徳であり、対して「ロゴスに耳を傾ける部分」の徳が性格の徳である。前者の、とりわけ思慮の徳に導かれるかたちで、後者における「欲求(情念)」には、成長とともに次第に「ロゴス(理性)」の働きが浸透していくととらえられる(61-3頁)。
「性格の徳」は習慣から形成されるのであり、「性格の(エーティケー)」という呼び名もこの「習慣〔ないし習俗〕(エートス)」から少し語形変化させてつくられたのである。/それゆえ、明らかにまた、「性格の徳」はいずれも自然によってわれわれにそなわるものではない。というのは、自然によって存在するものはどれも、他のあり方をするように習慣づけられることはできないからである。……/それゆえ、「性格の徳」がわれわれにそなわるのは、自然によってではなく、また自然に反してでもなく、われわれがそれらの徳を受け入れうる資質をもっているからであり、われわれは習慣を通じて完全なものになるのである。……/たとえば、人は家を建てることによって建築家になり、堅琴を弾くことによって堅琴奏者になるのである。これと同じように、われわれは正しいことを行うことによって正しい人になり、節制あることを行うことによって節制ある人になり、また勇気あることを行うことによって勇気ある人になるのである(同書65頁/『ニコマコス倫理学』第2巻1章、1103a17-b2)。
この引用にあるように、人間は実際の経験のなかで「同じような活動の反復」(第2巻1章、1103b21)をすることによって有徳な人へと次第に成長していく。この経験的で発達論的な徳論は、次のように述べられている点で、「徳とはなにか」という本質規定を問い「徳は知なり」とするソクラテス的な理性主義と、はっきり対抗的な関係にある。「そのような行為を為さなければ、誰も善き人になることはできないだろう。それなのに、多くの人びとは、こうした行為を行うことなく、議論に逃げ込み、議論することが哲学することであり、議論によってすぐれた人間になれると思いこんでいる」(第2巻4章、1105b11-14)。
アリストテレスは、有徳な人になるには、「幼児期において「正しい感受性」をもつようにしつけておく必要があり、「正しい法」のもとで育てられなければならない」と考える(第10巻9章、1179b31-1180a4/本書67頁)。本書が注目するのは、この有徳な人にむけてのしつけ、ないし訓練の方法として、「罪と罰」よりも「恥の意識」を通じた教育をアリストテレスが重視していることである。若者は「過ちに対する「恥の意識」を通して「不名誉に対する恐れの意識」をもつようになっていく」のである(68頁)。人は美しいもの、有益なもの、快いものの三者に惹かれ、そうした行為を選択するものである(73-5頁)。とりわけ本書で重視しているのは、「美しさ・立派さ(カロン)」をめぐる議論である。「徳に基づく行為は美しく、また美しいことのために為される」(第4巻1章、1120a23-24)。このカロンは、性格の徳全般に共通する特性である。「「カロン」という表現は「勇気」、「節制」、「親切」といった個々の「徳」の概念に並ぶ概念ではなく、具体的な状況において、そのような「性格の徳」の遂行をうながす働きをもっている。言い換えれば、勇気ある行為であれ、親切な行為であれ、それが徳ある振る舞いであるためには、それらの行為は「カロンな行為」として捉えられていると言える」(140頁)(注3―省略)。
先に長めに引用した性格の徳についてのアリストテレスの記述は、本書では必ずしも強調されているわけではないが、性格の徳の涵養が(現実社会を超越した理性的な道徳法則ではなく)人びとが関係をもち交流する共同体の存在と本質的に結びついていることをもしめしている。エーティケー・アレテーの「性格」ないし「倫理」とは「エートス」であるが、さらには『ニコマコス倫理学』の「エティカ」も「エートスにかかわる」という意味であり、そしてこのエートスとは個々の主体の性格特性であるとともに、社会的な習慣、さらには共同体の習俗を意味する言葉である。人間主体の性格の習慣ないし習性といった側面は、たしかに現代の徳倫理学で強調されるように、個々の行為ではなくその反復によって次第に形成されていく性格特性こそ、道徳にとって重要であるという含意を照らし出すだろう。しかし、エートスが共同社会の習慣ないし習俗であるという側面にも注目するならば、アリストテレスのいわばコミュニタリアン的な要素が浮かびあがってくる。本書でも次のような指摘がある。「「エンドクサ」の吟味を通して「幸福」を追求するアリストテレスは、過去から受け継いできた「徳の価値空間」という「ノイラートの船」に乗っており、倫理的価値(徳)を「内在的に」追求している」(84頁)。
◆ 性格の徳と思慮との関係
第2章の最後で、中庸説をより深く理解することにより、性格の徳の形成にはすでにして思慮という思考の徳が決定的に関わっていることがあきらかにされる。よく知られたアリストテレスの徳の中庸説は、実際にはより一般的な徳に関する規定の、ひとつの特殊ケースであると本書は論じる。徳の一部については中庸によって説明できるが、アリストテレスは中庸の図式では説明できない徳も含めて、すべての徳の一般的規定を提示しているのだという。たとえば「勇気」であれば、恐れという情念の過剰=「臆病」と、その不足=「無謀」のあいだの適切な中間として定義できる。しかし、たとえば正義や正直や友愛といった徳の場合、それに対応する情念の適切な量としてそれらを規定することは困難である。こうした「量による分類」ができない諸徳と、勇気や節制、温厚といった量的に中庸を考えることのできる諸徳の両者をともに説明できる、より一般的な徳の定義をアリストテレスが提示している点に本書は着目する。「メソテース(中庸、中間)とは、「ロゴス(道理)」によって、しかも思慮ある人が中庸を規定するのに用いる「ロゴス」によって定められるものである。すなわちそれは、二つの悪徳の、つまり過剰に基づく悪徳と不足に基づく悪徳との間における中庸なのである」(第2巻6章、1106b36-1107a3)。この後段の定義(量的な中間)は、一文目の一般的な定義の特殊ケース、つまり対応する情念を挙げることのできるようなタイプの徳にかんして妥当するより特定的な徳の定義として理解できるというわけである(76-80頁)。
そうなると、性格の徳(「選択にかかわる〔=ある行為を進んで選択したり逆に忌避したりさせる〕性格の性向」)の核心的な規定は、「思慮ある人が中庸を規定するのに用いるロゴスによって定められる」ところの中庸だということになる。ここで重要なのは、性格の徳の定義において「思慮」あるいは「思慮ある人の判断」が本質的な役割をはたしているという点である。「「しかるべき時に」、「しかるべきものについて」、「しかるべき人々に対して」、「しかるべき目的のために」、「しかるべき仕方で」こうした情念を感じることは、中間の最善の状態によるのであり、これこそまさに徳に固有なことなのである」(1106b16-23)と述べられるときの、「しかるべき」を判断するのが、思慮の徳の役割であるといえる。そして、この「しかるべき」の判断は、(1)「行為の主体に相関的に決まってくる」ものであり(たとえば節制にかんしていえば、運動選手の適切な食事の量と普通の人のそれとはおのずと違ってくるだろう)、(2)同時に「行為者が置かれた状況」に相関的でもあるのである(81-2頁)。
こうした性格の徳と思慮との不可分性は、次の第3章の2節「第二の自然としての、性格の徳と思慮」で次のように述べられている。「子供は「カロン(美しい・立派な)」といった言葉、あるいは「アイスクネー(みにくい、恥ずかしい)」といった言葉を対象や行為に適用する仕方を学び、「美しい、立派な」、「みにくい、恥ずべき」といった事態を徐々に了解できるようになっていく。その結果、「美しい、立派な」行為へと動機づけられ、「恥ずべき」行為を退けるようになる。したがって、どのような現象や行為を「カロン(美しい)」と捉えるかに習熟していくことは「思慮」の能力と密接に結びついており、「思慮」の機能の成立は情念や欲求の訓練と切り離すことはできない」(104-5頁)。ところが、「普遍主義的解釈は、「思慮」を情念や欲求から独立なカント的「理性」能力として捉える傾向がある」。これに対して本書は、思慮を「小前提における具体的な状況を把握する知覚能力」ととらえるアリストテレスの説明を重視し、こうした知覚能力としての思慮が性格の徳と切り離せない点を強調する。「行為者は、直面する状況で彼が最も突出した事実(the salient fact)として立ち現われてくる相貌を知覚するのであり、どの相貌を捉えるかはその「性格の性向」に基づいている」からである。たとえば、「「友人が悩みを抱えて訪れてきた」と知覚し、「パーティをキャンセルして友人の悩みを聞こう」と判断するのは「思慮」の働きである。しかし、その「思慮」を導いているのは、たとえば、「親切」といった「性格の徳」である」(106-7頁)。
◆ アクラシアと徳倫理
本書ではほかにも、思慮の徳の内在主義的な解釈に対応した、アクラシアをめぐる説得的な説明のほか、実践活動の生(活動的生)と観想活動の生(観想的生)のそれぞれについて、アーレントのように両者の連関を問うことなく独立的に論じるのではなく、アリストテレスの倫理学体系のなかでどのように整合的に折り合わせることができるのか(かつ、実践活動の生を単に観想に従属させるという伝統的な解釈への批判とも両立させることはどのようにして可能になるのか)といった重要な論点についても、足掛かりとなるような考察が展開されている。
またアクラシアについていえば、現代の徳倫理においてカント的義務論との差別化が図られるときに、徳が抑制(continence)からも区別された心の調和された状態(≠絶えざる克己的な努力)として定義される点にしばしば注目が集まっている。カントをはじめとする近代の倫理学は、義務・責務・行為の正しさなどにもっぱら関心を集中させ、動機づけの問題を副次的にしか扱えないため、行為の理由と同期のあいだでの恒常的な分裂に苦悩する「道徳的スキゾフレーニ」(ストッカー)を招来してしまっているとときに批判される。動機を――自然的傾向性として――理性・理由による抑制・抑圧の対象と位置づけるのではなく、人間のエートスの学としての倫理学のなかで、友情や愛、誠実といった価値を適切に扱いうるような思考が、このスキゾ状態を克服するには必要とされるだろう。抑制する者が実際に抱いている欲望と正しい行為を行う理由とのあいだの対立が、どのように超克されていくかを、発達論的に解明した業績として『ニコマコス倫理学』を読むという視点は、本書が本格的に提示した新たな方向性として、今後さらなる検討を重ねるに値する問題であるように思われる。
(評者:上野大樹)
更新:2016/09/26