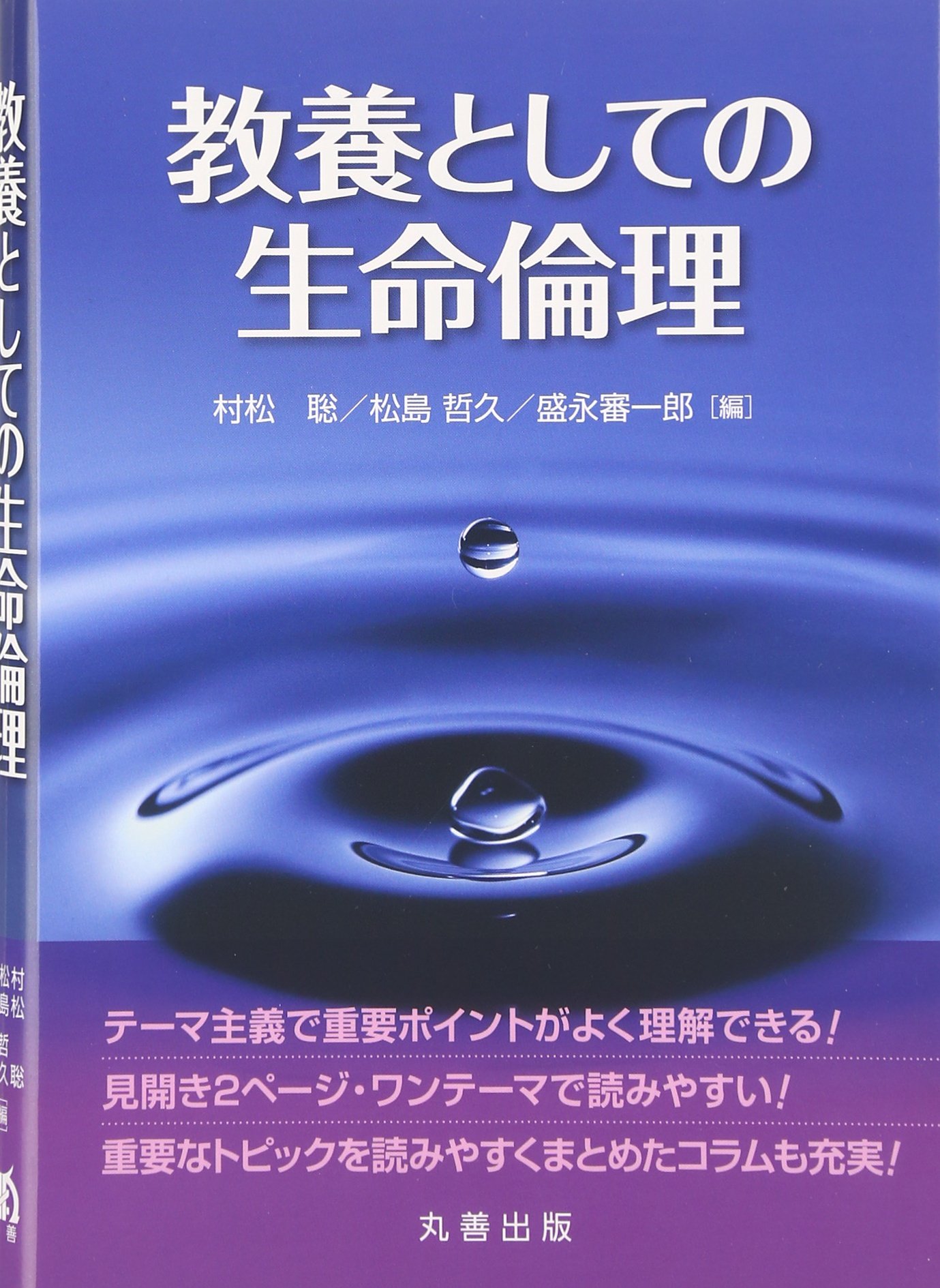 | 書名:教養としての生命倫理 著者:村松・松島・盛永編 出版社:丸善出版 出版年:2016 |
◆ 社会倫理学の現在
生命・医療倫理、環境倫理、ビジネスエシックス、情報倫理、技術倫理をはじめとする応用倫理学(applied ethics)は、こんにちの人文系諸分野のなかでとりわけ社会的な注目を集めている領域だといえるでしょう。ひとつ目の生命倫理(bioethics)・医療倫理(medical ethics)をめぐる議論の現状を俯瞰的に理解するために有益なガイドブックとして、ここでは昨年公刊された『教養としての生命倫理』(丸善出版)をとりあげたいと思います。以下では、関連する種々のトピックに言及するごとに、同書の対応する章や項目を括弧内に指示します。それぞれのトピックについてさらに詳しい議論や情報を知りたい場合には、まずは本書の該当項目から入っていくのがよいでしょう。
応用倫理学興隆の背景にあると考えられるのは、現代文明を特徴づけている未曽有の科学技術の発展です。ごく単純化していえば、技術進歩のあまりの速度に、一定の定常性を暗黙の前提としてきた人間社会の倫理的・規範的な基盤が大きく揺らぎはじめているのがこんにちの状況だとまとめることができます。たとえば、ヒトゲノム計画以降の遺伝子情報解析(DNA解析)のすさまじい進展は、かつてならあくまでSF小説のなかだけの話として済ませることのできたユートピアにしてディストピア的でもある思考実験の世界を、なかば現実のものとしつつあります【10章1「遺伝子診断・治療」】。
これだけの急激なテクノロジーの変化をまえにして、じゅうらいの倫理学的な議論や、それらがほとんど与件としてきたような道徳上の諸前提をげんざいの状況にそのまま当てはめることが困難になってきているというのは、容易に想像のつくところです。理論的には、いまやサイボーグ(改造人間)もアンドロイド(人造人間)もかつてアニメやSFが想定していたのとほとんど同じ水準で実現可能となっているのです。前者についていえば、「宇宙空間や海底などの特殊環境に順応できるように、人工臓器でからだの一部を改造した人間」(大辞泉)という定義の後半からは、こんにちの再生医療がすぐさま想起されます。ES細胞、ついでiPS細胞の研究がこの分野の主役に踊りでていますが、さかのぼれば20世紀末に誕生したクローン羊のドリーは、世界的なセンセーションを巻き起こしました。再生医療はとうぜんクローン技術の進歩と不可分であり、このことが意味しているのは、再生医療はその端緒からして(サイボーグばかりでなく)アンドロイドの製造可能性というきわめてセンシティブな倫理的問題とも切り離すことができないということです【10章3「ES細胞とiPS細胞」および4「クローン技術」(横山陸)】。
◆「何でも自己決定」の限界
こうした状況を眼前にして、倫理学的・道徳哲学的な考察が要求されるさまざまな新しい問題が出現してきています。少しまえまでならば、道徳や倫理というものは、人間がそのなかで生活する外部環境――社会状況や技術的条件、情報環境など――からは独立に規定され、探究していくことが可能なものだという理解も一定の説得力をもったかもしれません。カントに代表されるアプリオリ主義(超越論主義)の規範倫理学がその典型例です。この方向性がなお追究するに値する種々の論点を内包している点は否定しがたいにせよ、しかし、現在われわれが直面しつつある「外部環境」の劇的なまでの変容は、あくまでそこから超然としたかたちで倫理・道徳の領域を擁護するというスタンスを、少々的外れなものに見せてしまっているということもまたたしかです。こうした変数をあくまで外部的なものとして処理してしまうのでは、われわれが実際に現実社会を生きるなかで直面する諸問題に適切に対処していくうえで、道徳や倫理はもはや有益な枠組みを提供してくれるものではなくなっているのではないか、という疑念を払拭できないかもしれません。
他方、アプリオリな規範理論の見地というよりもむしろ、倫理問題は基本的に個人的で主観的なことがらなのだから、社会環境の変化にいちいち反応する必要はなく各人がそれぞれに判断すればよいという立場から、実践的な応用倫理学に懐疑的なまなざしをむけることもできます。この種の批判はいまなお重要です。というのも、のちほど少しくわしく触れますが、応用倫理分野は危機に瀕する人文諸学のなかで例外的に活況を呈しているフィールドであり、「そこには社会的に問われるべき重要問題がある」と述べることに特定の利害の傾きを有していると言わなければならない面があるからです。そのうえで、しかし、「何でも自己決定」一辺倒では、いまや理論的にも実践的にも限界があることはあきらかになっていると思われます。
原理的にいえば、個人主義的リベラリズムの基本テーゼである「他人に危害を加えないかぎり何をしてもその人の自由である」という考え方にしても、「他者に危害(harm to others)をあたえる」という事態の内実を一義的なしかたで決めることはできません。第一に、何を危害とするかはその社会で共有されている共通理解や慣習などに依存して可変的だし、それが歴史的な進化の過程でごく限定された解釈へと収斂していくという見方も、現在のところあまり説得的な見解として受け入れられているとはいえません。また、「自己保存」を脅かすきわめて深刻な物理的危害にかぎっては、文化や慣習のちがいを超えてそれを人類共通の「最高悪」とみなしてその回避を至上命題とすることが普遍的に正当化可能であるとするホッブズ主義が、ひじょうに有力な立場として考えられます。しかし、こうしたミニマリズムの道徳原理では、日常的ないし実践的に生じるような道徳判断が求められる場面のほとんどにおいて適用が困難です。明白に危害だと認定できないかぎりはどのような行為をするのも個人の自由であると判断することはできますが、そこまでいくとおそらくかなりの人は、実際の社会生活で行われている道徳的な営みから自由主義的原理が大きく乖離しており、われわれの道徳実践を首尾よく説明するものではないと感じるでしょう(こういう視点は一般に「記述倫理学」と呼ばれます)。さらには、こんにちの宗教的原理主義の問題をとりあげるならば、それが自己の生命の保存に勝る価値はないという近代社会の基本前提にたいする深刻な挑戦を突きつけるものであると考えてみることもできます。じつはこの問題は、あとで見るように先進諸国内部でも、終末期医療における医師介助自殺をふくむ安楽死や尊厳死といった論点として、近年浮上してきているのだということができます。安楽死では、グレーゾーンではない明白な他者による危害をどう正当化できるのかということが、重大な問題となりえます。
第二に、危害を加えられる対象としての「他者」をどう規定するかということがあります。これもじつはアプリオリには定義しがたい部分があり、これまでは社会的に緩やかに共有されていた常識を前提にすることができたために、大きな問題として浮上することはなかったといえるでしょう。ところが、先端的な生命科学とバイオテクノロジーの発展が、この定義問題の重大性を顕在化させたのです。たとえば、ES細胞の作製のためには受精したあとの卵子であるヒト胚を破壊する必要があり、そのために大きな倫理的問題を生じさせました【前掲、横山執筆項目】。こうした問題を回避できると考えられているiPS細胞にしても、実際の研究過程ではES細胞との比較研究が必要となり、ことはそう単純ではないという事情も横山が指摘するところです。また、再生医療に先行して人工妊娠中絶の技術も同様の問題を惹起し、とりわけアメリカでは大きな社会的論争を招来しました【7章「生殖医療と生命倫理」】。
第三に、そもそもこうした自己危害原理が、多くの人びとや社会・共同体によってどこまで道徳的判断基準として共有され受容されるのか、という問題があります。この問いは一見して奇妙に響くかもしれません。共同体や社会による干渉や同調圧力にさらされることのない個人の自由な領域を確保することにこそ、この自由主義的原理の眼目があると考えられるからです。しかし、テイラーやサンデルに代表されるコミュニタリアンのロジックにしたがえば、そうした原理も決してアプリオリに保証されるわけではありません。集団的介入や社会的画一性から自由な私的領域における個人の活動には比類なき価値があり、尊重されるべきであるとするリベラルな信念(思想信条や良心の自由など)そのものが社会的に共有されているということが、リベラルな社会の成立条件だというわけです。というのも、濃密な価値の共有を強く期待してくる共同体の領域からは区別されて、個人の自由な領域が存在するべきだという価値観じたいが、第二階の共同体(メタ共同体)の水準において社会的規範として共有されていなければならないからです。そうした規範を有しない社会は容易に想定できますし、リベラルなメタ規範を有する社会がそれを持たない社会よりも道徳的に優越することにアプリオリな理由はないと、コミュニタリアンは考えます。こうしたリベラルな価値規範をあらゆる社会が潜在的には共有しているか、やがて必ず共有することになるであろうと考える理由もまたアプリオリにはあたえられていないのであり、それゆえに、経験的な世界において少しでもそうしたメタ共同体の規範や政治文化を価値あるものとして広めていくことこそが、リベラルな政治の課題であると考えるのです(この課題はおおむねローティによっても共有されています)。この論点にかんしては、重田園江『社会契約論』の書評でも詳しく検討しました。
(なお、この三番目の点にかんして一例だけ挙げておくとしたら、生命倫理とはべつのmoral issueとなりますが、同性婚の場合がわかりやすいのではないかと思います。同性婚を認めるかどうか、これも各人それぞれの自由な判断に任せればよいのではないかと「自己決定」の論理に即していえそうですが、実際にはその方向で議論がだいたい収斂しそうな社会もあれば、そうでない社会もあるというのが実情です。つまり、同性婚問題の領域でリベラルな自己決定を適用するかどうかじたいが、広範な社会的合意の有無という要因によって規定されているのです。おおよその目安ではありますが、イギリスなどのように全体の7割近くが同性婚に寛容な世論を形成している国では、法的には同性婚が合法化され、道徳的にも同性婚の是非を社会として判断する必要はなく、それぞれの個人の価値判断にゆだねればよいという“社会的”な道徳上の合意がおおよそ成立しているといってよさそうです。しかしその状況は、それは私的な問題だから社会全体がとやかくいうべきではなく、公的にそれを禁止したり奨励したりもすべきでないという判断じたいが、社会に広く共有されているという事実に依存しているわけです。そのような合意が形成されていない国もとうぜんあります。そしてそれにはアメリカ合衆国や一部の先進的キリスト教国がふくまれているわけですから、文明が進めばおのずとそうした合意が確立されてくると考えることも難しいのです。)
◆ 再生医療の応用倫理
以上にみてきたような原理的問題は、実践的な考察の場面でもとうぜん生じてきます。たとえば、万能細胞研究の是非についてもクローン技術の使用の是非についても社会的に判断することはせず、各人それぞれの判断にゆだねればよい、と試しに考えてみるとどうでしょうか。おそらく直観的に、自己決定の論理がそのまま適用できそうな領域とそうではないと思われる領域とが存在し、この問題は後者に属している可能性が高そうだと考える人が多いであろうと推測されます。それでも敢えて、自己決定の論理をつらぬく方向で考えてみることもできます。ただそうなると、先ほどの「他者に危害を与えないかぎり」という条項をどう解釈するかが一義的に定まらなくなり、結局のところ、倫理上の判断基準について社会的に議論し一定の合意を構築するということが避けられなくなるのです。この場合、だれが自己でありだれが他者であるのか、なにが危害であるのかといったことがつねにすでに社会的・共同体的に媒介されて規定されることとなり、純粋な“自己”決定というものは原理的にいって困難であることがわかります。
先述のサイボーグの辞書的な定義をもう一度みてみましょう。「宇宙空間や海底などの特殊環境に順応できるように、人工臓器でからだの一部を改造した人間」という規定を眺めてこのなかに倫理的に許容しがたいような要素を感じとるのだとすれば、それは何なのでしょうか。
身体器官の一部を人工物によって置き換えることそれじたいが道徳的に容認されえないと考えるならば(そう考える人も一定数いるでしょう)、身体障害者が義足をもちいることも道徳的に否認されるでしょうし、万能細胞を用いて作製した網膜色素上皮シートや心筋シートの移植も認められないということになるでしょう。逆に、障害者が義足を使用したり、身体の重大な障害を再生医療によって補おうとしたりすることは道徳的に是認されるともし考えるならば、そのひとは人工物による身体の一部の置換や補完そのものを一般的に否定しているわけではないといえます。だとすれば、義足などの利用を肯定しつつサイボーグについては認められないとする道徳判断を原則的に一貫したものとみなすためには、さきのサイボーグの定義の前半にある「特殊環境に順応できるように」という部分に、否定的な判断をくだす要因が存在していると考える必要がありそうです。ここで「科学技術白書(平成27年版)」での再生医療の定義をみると、「病気やけがで失われたり損傷したりした臓器や組織に、体外で培養した細胞等を移植し、失われた機能を補うもの」とあります【10章2「再生医療」】。ふたつを比較してみると、バイオテクノロジーを利用して作製された人工物を移植するさいの目的が、通常とは異なる特殊環境にも対応できるように身体機能を増強することなのか、それとも通常環境のもとでの従来どおりの活動可能性をとりもどすために喪失した身体機能を補うことなのか、という点のちがいによって、道徳判断が変わってきていると推定することができます。かりに、傷病などで失った機能を回復ないし補完するための義肢や人工臓器の使用は是認できるが、前記の定義にみられるようなサイボーグは道徳的に是認できないという判断があるていど一般的だとするならば、その背景にこうした倫理上の判断基準(道徳原理)が存在しているのだと考えることができます。これは一般にエンハンスメントの問題性として議論されていることと、おおよそ重なるといってよいでしょう【序章2「市民の倫理としての生命倫理」、10章6「脳科学と脳神経倫理学」】。
応用(社会)倫理学は、さまざまな具体的なトピックについてのありうる複数の道徳判断――社会的に広く共有される単数ないし少数の判断が存在している場合もありますし、多数の判断が競合している場合もあります――を記述し、その(それぞれの)判断の背景にある道徳理論・原理を析出することを重要な任務とします。そして、その道徳原理や基準をさらに基礎づけたり正当化したりする原理やロジックはないか、さらには、ほかの関連するケースにおける道徳判断にかんしても同様の道徳原理・基準をもちいて首尾一貫した説明をあたえることができるのかどうか、こうしたことを検討していき、全体としてできるだけ整合的に説明できるような道徳体系を構築していくことがめざされます。上記の例にかんしてですが、自己決定の定義問題と同じように、適応すべき環境が特殊なものか(身体機能は適応のために改変され増強される)、それとも通常のものなのか(身体機能は再適応のために回復されるか代替される)という区別じたいが社会的合意に大きく依存することになるので、この区別についての安定的な共通了解がどこまで獲得できるかという点も、きわめて大きな意味をもつことになります。
◆ 応用社会倫理学から実存主義的倫理学へ
応用倫理学とはいったいどういったことをする学問なのかという点にかんしては、ひとまずこれで大まかなイメージは了解されたかと思います。
そのうえで、しかし、わたし自身は日本の倫理学界隈のさいきんの動向にたいしてはある不満をおぼえてもいます。ここまで概観してきたような、集合的な社会的選択――「どういった政策、法体系、社会制度を構築していくべきなのか?」――に資するための応用倫理的諸課題への応答を応用社会倫理学とよぶとすれば、倫理学はそれとはべつに、広い意味での「実存」の問題として倫理的な問いを引き受け、これに応答しようとする領域をもそなえておかなければならないように思われます。実存主義的倫理学、あるいは(この語がサルトルらのフランス哲学を排他的に想起させてしまうとすれば)実存論的倫理学とでもよぶべきものです。(応用)社会倫理学が、社会(の一員)としてのわれわれがどういった選択や決定をおこなうべきなのかというかたちで主語をたてるとすれば、実存論的倫理学は、あくまでまずはこの「わたし」が窮極的な倫理的判断をせまられたとき、状況のなかでいかに行動すべきなのか、と問いを立てる営みです。実存の問題として立てられた倫理学も、必ずしも主語を一人称単数に限定するものではないと考えていますが、一人称複数の主語が立てられるときでもそれは「このわれわれ」であり、そこには「このわたし」が決定的なしかたで含まれているはずです。
哲学の領域では、とりわけハイデガー以降、このような視点の重要性はいくどとなく唱えられてきたようにも思われるのですが、どういうわけか実践的な倫理学の世界では前者の立ち位置が知らぬまに採用されてしまい、実存にかかわる問題として倫理的な場面に身をおくという態度がとられにくくなっているようにみえるのです。人間の現存在としての性格が避けがたく要請するような意味での「当事者性」の欠落、あるいは希薄化です。例外は哲学・倫理学史的な研究におけるレヴィナスとヨナスへの言及ですが、こうした原理論と応用倫理の接点は、あまりに弱いものだといわざるをえません(レヴィナスについては馬場智一『倫理の他者』、ヨナスについては品川哲彦『正義と境を接するもの』がぜひ読まれるべき文献でしょう)。
これまでみてきた再生医療を例にとるならば、その“社会的”な意義と重要性は否定すべくもないものです。したがって、生命操作の危険を重くみてその大幅な制限を主張する議論もふくめて、iPS細胞・ES細胞研究の展開と人間社会の倫理的基盤の維持・再構築とをどのように折り合わせていくかという論点が社会全体にとって喫緊の最重要課題であると述べることにも、大きな異論はないでしょう。しかしながら、公式的な言説としてほとんどの人はこのことに反対しようとしないにもかかわらず、このあまりにもっともな公式言説はやはりどこかある種の「お題目」や「建て前」として受けとられてしまい、それをその身に切迫してくるような「我が事」としてとらえかえせるようなひとはごく少数なのではないでしょうか。そのかぎりでいえば、疑問をさしはさむ余地もない「お説」を拝聴しながら、どこか話半分に、あるいはどこか上の空で聞いてしまっているというのが実情ではないでしょうか。ことは再生医療にかぎりません。人工妊娠中絶を中心とする生殖医療【7章「生殖医療と生命倫理」】や脳死と臓器移植の問題【第8章「脳死・臓器移植と生命倫理」】にしても、そうした問題の社会的な重みはだれも真っ向から否定しないにもかかわらず、多かれ少なかれ「他人事」だと感じているのがじつは社会の多数であるということは否めません。
社会学者などとちがって、応用倫理の研究者のかなりの部分は、こういった実態に思いのほか無頓着であるようにみえます。この問題を指摘されれば、政治哲学者が政治に無関心な若者を説教するのと同じように、これらの問題の社会的な重要性にいまだに注意をむけていない一般人に、たんなる啓蒙の不足を認めるだけかもしれません。けれども、倫理学者と一般世間のあいだのこうした意識のギャップは、後者にばかりその責を帰すことはできないようにも思えます。公共的意義や社会的有用性というそれじたいではまったく妥当な基準を、しかし「錦の御旗」に掲げて、世間の意識の遅れを一方的に裁断するような資格は、倫理学者にもないでしょう。というのも、一般に近代社会にあっては、社会の全体にかかわることがらをまるで古代のポリス市民のように我が事として受けとめ、これに主体的に関わろうと市井の人びとがおしなべて考えるはずだと、あるいはそうあるべきだと想定することは、不合理だからです。これは「想像の共同体」としての国民社会にもかかわる問題です。近代社会の構造的な特質をふまえないままに、規範理論をいわば超越的な高みから振りかざすようなことは、そのような倫理学の無知と不合理をさらけだすものにほかなりません。
人工中絶、選択的中絶や遺伝子診断をふくむ出生前診断などがもたらす「命の選別」の問題、臓器提供とも結びついた脳死の規定をめぐる論争や、生体間移植にまつわる倫理的諸問題など、これらが市民としてのわれわれが真摯にとりくまなければならない重大な問題領域であるのはまちがいありません。ただ他方で、研究者は社会的な重要性の高まりという決まり文句に安住しがちな面があります。倫理学者たちが実存論的視点とのかかわりを掘り下げることをしないまま、そうした重大問題への社会的な取り組みをただ規範的に正当化ないし批判したり、あるいは先端的なケースに新たに直面して従来の法体系や政策との論理的な整合化を探求したり既存秩序を部分的に修正し(てより全体の体系性を高め)たりする、といった作業のみに専心するのでは、アカデミズムと世間のあいだの隔たりの責任は前者にも求めなければならないでしょう。反省的均衡であれ何であれ、第三者としてただ「パズル」を解くように現今の道徳的ジレンマにむかいあっているのでは、倫理学としてはあきらかに片手落ちなのです。
応用倫理の世界で社会的・公共的意義が強調されるわりに実存論的な問題構制のほうは希薄なのは、次のような事情もあるかもしれません。哲学・思想・歴史といった伝統的な人文学は現在、グローバル競争と社会的有用性・効率性を求める社会情勢のなかで、その存在基盤が大きく揺るがされています。そのようななかで、応用倫理の分野はむしろ興隆をきわめつつある例外的な領野です。ところが、そうした背景が、社会の先端的なニーズにいちはやく応えられている分野としての自己アイデンティティを、応用倫理学にもたらしてもいるようです。グローバルな社会の要請のもと重要課題に解決を見出し、適切な交通整理をおこなうというところばかりに自己の存在意義をもとめるならば、社会的意義に直接には結びつかず、場合によってはそうした“社会実践への応用可能性”としての有用性の視点から倫理学研究を正当化していこうという動きに冷や水を浴びせることにもなりかねない実存論的倫理学には、うかつに手をださないほうが賢明だということにさえなるわけです。御用学問だとまではいわないにせよ、「結局、生命倫理学は、商業的・科学的活動のために倫理的認可を必要としている研究者・製薬会社と、認可・承認のための場所、専門職的使命、公共的役割に生きる道を見出した哲学者たちとの間の「不健全な同盟から生じた」」というN.ローズのシニカルな見方も、あながち否定できないかもしれません。
◆ 当事者からの倫理学――生殖医療と終末期医療
当事者性の問題は、人工妊娠中絶の是非をめぐる論争に焦点をあてるとより明確に浮かびあがるように思います。中絶の問題は、日本では残念ながらかなり多くの人にとって、社会的には重大な争点であるらしいが自分自身にはたぶん直接は関係なさそうだ、という感覚で受けとめられているふしがあります。これに対して、アメリカを中心とする欧米諸国では、生命倫理の最重要トピックといえば人工妊娠中絶だという理解がながらく続いてきたようです。その理由を、欧米のほうが中絶の当事者がたんに実際上多いからだとするのは、さすがに無理があるでしょう。この反応のちがいにはあきらかに宗教・文化的背景の相違があり、アメリカのようなキリスト教文化圏では、ある面では中絶を認めるか否かは――かりに自分自身や家族ら近しい人が中絶にかかわりがなかったとしても――決して他人事ではありえず、みずからのアイデンティティの核心部分にかかわる問題として、まさに当事者として思考し議論し判断せざるをえないことがらなのです。もちろんこう述べたからといって、べつに欧米人のほうが一般的水準でも生命倫理の問題を自分自身の問題としてとらえていて、道徳的に秀でているなどといいたいわけではありません。そうではなく、社会的に重要だとされる応用倫理上のテーマが、「このわたし」にとって実存的に深い意味をもっている――それにたいする応答次第で自分自身のアイデンティティが何らかの重要なしかたで変容してしまうような問いかけとして立ち現れている――と観取されるかどうかは、文化的にも大きく規定されるのであり、社会倫理学を実存論的にも再構築しなければならないとすれば、アメリカ人にとっての中絶問題のように多くの日本人にとってまさに我が事として考えずにはいられないような倫理的テーマをとりあげる必要があるのではないか、ということです。
中絶の倫理的問題を論じるとき、日本では比較的リベラルな人びとであればそれは女性の自己決定権が尊重されるべきだから容認されなければならないと考え、逆に保守的な人びとであれば中絶は自然や生命にたいする人間精神の高慢の表れであり、あるいはあるべき自然な家族のあり方を揺るがすがゆえに拒絶されなければならない、と考えるでしょう。実際には、構図はそう単純ではありえません。少し考えてみれば、女性の自律vs自然性による他律といった素朴な図式にはおさまらず、女性の自律vs胎児の自律という内的なアンチノミーが生じていること、反対に反中絶論にしても、実際には生命の尊厳や自律の論理に大きく依拠して立論されていることなどがわかるわけです。プロライフvsプロチョイスの論争を、自律か他律かという単純な二分法で平面的に理解するだけにわれわれがとどまっているとすれば、その理由の一端は、この問題をわたしたちの存在や意味に強くかかわってくるような問いとはみなせない、ただそれが重要な争点だと“社会”によって言われているからわたしもそれが重要だと考えているにすぎない、といったところにあるのではないでしょうか。
このとき、問題に解を出そうとする応用倫理的視座の拠ってたつところは、せいぜい「可哀そうなマイノリティ」のための倫理学となってしまうのではないかと感じます。そうではなく、自分自身がまさにその立場に立たされうるのであり、その道徳的苦悩とジレンマは自分自身の置かれた状況でもあるのだと何らかのしかたで考えられなければ、倫理は実存とはなりえないでしょう(“不幸な境遇に見舞われている震災や自然災害の被災者”についても同様でしょう。ところが、日本列島では誰もが近い将来、それを我が事として受け止めざるをえない状況に容易に投げこまれうるのであり、われわれもさすがにそのことに気づきはじめているのです。もちろんそれは、たんにもしものときのリスクに備えよ、といった即物的なはなしではありません)。
日本の文脈では、中絶は自分自身や身近な存在がそれで実際に苦悩することがなければ、いくら公的議論のなかでその社会的重要性が説かれても(そして誰もその重要性じたいには表立って異を唱えることはなくても)、やはりどこか他人事なのです。そのうえで、恵まれない家庭環境や境遇におかれた女性がいて、少数者としての彼女たちは気の毒なことに中絶を選択しなければならない、そしてわれわれはそれに同情しなければならない云々、と推論が進んでいくわけです。代理出産や脳死・臓器移植、再生医療、薬害・医療事故などについても同じです。それらもまずは別世界での出来事であり、一部の可哀そうな人びとに起こるそうした遠くの出来事にできるだけ同情し共感するように、われわれは人間的能力を発揮し涵養しなければならない、ということになるのです。
倫理を「この自分」に立ち現れる実存の問題として引き受けるためには、応用倫理学がもたらしがちであるこうした基底的な構図をやはり乗り越えなければなりません。超高齢化社会の日本で、社会倫理を応用可能性の観点(だけ)からではなく実存論的なしかたで問うためには、ひとつ、尊厳死・安楽死の是非が大きな争点となる「終末期医療」の場面から問いをはじめるということが、有効な指針となりうるのではないでしょうか【9章「終末期医療と生命倫理」】。なぜなら、それは日本人のほとんどだれもが否応なく「この自分」自身にやがて訪れる場面として、この問題と向き合うしかないということをいまや自覚せざるをえないからです。
(評者:上野大樹)
更新:2017/02/19