月別アーカイブ: 2025年8月
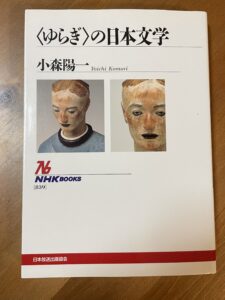
最近読んだ本
おひさしぶりです、村田です。暑いですね。
ひさしぶりにブログ書きます。
たまたま、日本近代文学に関する本を続けて読んだので記録&紹介です。
***
■ 小森陽一『〈ゆらぎ〉の日本文学』NHKブックス、1998
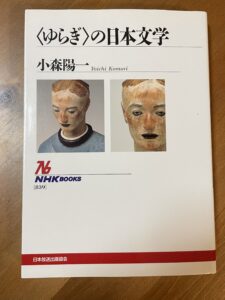
ずっと積ん読状態であったのをやっと読みました!
「日本=日本人=日本語=日本文学」という四位一体を再生産し続ける装置でもあった「日本近代文学」の中に、その等式の「ゆらぎ」となりうるものを見つけていく……という本です。
少し前(1998年って「少し前」でええんかな…)の本であり、これ以降も「日本」の非自明性はさかんに言われてきたことであるとは思いますが、「『純粋な日本人』でない」と見なされた芥川賞作家にヘイトがぶつけられる……などということも起こっている現在、未だ重要な切り口でしょう。
漱石、荷風、谷崎、賢治……etc、さまざまな作家が扱われていますが、特に、最終章と中島敦の章が勉強になりました。
中島敦は「戦時の影響を受けなかった孤高の作家」と高校生のときは習ったのでしたが、その後その南洋滞在経験を知り気になっていたので。
「山月記」は高校教科書に採用されて広く知られていますが、本書は『古譚』のひとつとして読むことを重視します。「山月記」をそこから切り離した国語科教育の道徳的解釈、すなわち、李徴の「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」に注目して物語を知識人の自意識や文学者の業に回収する解釈は、山月記の「歴史性」を隠蔽しているのでは? とします。そして、「人間性」を前提としたうえで李徴の虎化を「人間性の逸脱」とする戦後の受容に対して、次のように問います。
しかし中島敦が小説を書いた戦争の時代において、はやして、戦後的視点からの「人間性」なるものが、どこにあったのだろうか。あるいは『古譚』に収められた他の三作が、人間が人間であるがゆえに、血で血を洗う権力闘争と侵略戦争をしつづけてきたことを、人類の歴史の起源にまで遡って記述していることをどうとらえるのだろうか。(p.252)
■ 宮下隆二『イーハトーブと満州国――宮沢賢治と石原莞爾が描いた理想郷』PHP研究所、2007
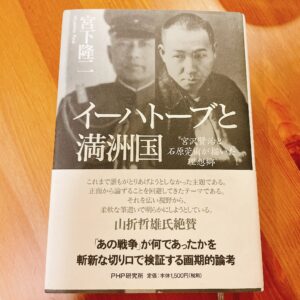
YU3
宮沢賢治の「イーハトーブ」と石原莞爾の思い描いた満州国を、日蓮宗(国柱会)という二人の共通のバックボーンから考察し、ひいては日本の近代、日本の戦前戦後を考える、という本でした。賢治のことも莞爾のことも国柱会のこともぼんやりとしか知らなかったので読んでみました。
イーハトーブという理想郷を追い求めて農村の変革を目指したものの、限界に阻まれた賢治。一方、満州に新たな国家を建設することでユートピアを求めようとした軍人の石原。石原にとっての満州国もまた、政治的意味をもつと同時に法華経に基づく宗教的ユートピアであり、「王道楽土」「五族協和」は石原にとって宗教的理想だった、とされます。それが瓦解したのは政治的軍事的理由であると同時にやはり「この世に存在し得ない理想」(p.208)であったからとしつつも、「賢治が光で石原が闇という単純なものではない」(p.202)というのが筆者の主張。
終盤の章では、賢治の内なるユートピアと石原が外に求めたユートピアを止揚していくことが現代の課題であるとして、現代文明批判に至ります。しかしこれらの章は近代以前の日本(江戸)をちょっと美化しすぎでは、とも感じました。「ニート」「フリーター」の話も2007年当時の語られ方という感じで、今なら違う書き方になっていたかも。
賢治作品って好きだけどよく分からんしちょっと怖いな~とずっと思ってきたので、法華経的観点からの読解の章が勉強になりました。「有機電燈交流」は「万物は縁起によって存在する」という大乗的な存在論である、等。
■ かまど&みくのしん『本が読めない33歳が国語の教科書を読む』大和書房、2025
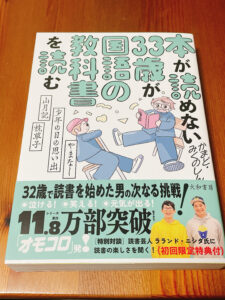
上の二冊とはちょっと違うタイプの本ですが。
ウェブメディア「オモコロ」発の「読書実況」本。ウェブライター(注)だが読書が苦手、というみくのしんさんが、読書好きの親友兼同僚のかまどさんにサポートされながら本を読む様子を収めたシリーズの二作目。一作目(『本を読んだことがない32歳がはじめて本を読む』)でファンになったんでこれも読みました。
注)フルーツサンドの記事が好きです。
「本が読めない」とはどういうこと? と思いながら読み始めたはずがいつしか、いやむしろ「読める」とはどういうこと? 「読める」と思っていたのは本当に読めていたのか? と考えさせられる点は前作同様。みくのしんさんはおそらく文章から映像が広がったり登場人物の声がきこえたりするときに「読める」と感じていて、いったんそれが始まるとその想像力は留まることがなく、彼の脳内のスクリーンを一緒に見せてもらっているような感覚が本書の楽しさのひとつです。
たとえば「山月記」(また「山月記」だ!)を読む章では、序盤の用語の難解さにキレつつも、
気が付くと、手先や肱のあたりに毛を生じているらしい。
少し明るくなってから、谷川に臨んで姿を映して見ると、既に虎となっていた。
自分は初め眼を信じなかった。
から、「川を覗くとトラの顔がゆら~っと映ってて……。そんな自分を信じたくなくて水面をバシャッって殴るんだけど、その手もトラの前足になってて……」(p.176)と李徴のトラ化をつぶさに想像し、
時、残月、光冷ややかに、白露は他に滋く、樹間を渡る冷風は既に暁の近きを告げていた
から、「湿った空気が涼しくて、霧雨っぽく視界がぼんやりしててさ。ざぁざぁ……って葉っぱが擦れる音も聞こえて、遠くで笛のようなフクロウの鳴き声が聞こえてて……」(p.198)とイメージを広げ、終盤は李徴に叫びながら語りかける。「アツい」読書なんですが、かと思えば、多くの者が共感するであろう「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」のくだりは、通り過ぎる悩みだよ、とサラッと流しているのがクールです。
■ 石原千秋『打倒!センター試験の現代文』ちくまプリマ―新書、2014
アンチセンター試験のセンター試験本です。センター試験はもう無いですが(現在は「大学入学共通テスト」)。
上掲本(『本が読めない33歳~』)がとにかく自由に本を読む!読書に正解なんてない! という書であるとすれば、センター試験というのはその逆。五択の中から唯一の正解を選ぶことを求められ、そのためにできるだけ一定の読み方をすることが要求されます。
一定の読み方とは、「できるだけ解釈を入れない・できるだけ字義通りに近い読み方」ということ……のはずなんですが、そして本当にそうであれば一定の意義はあると思うのですが、しかしできるだけ字義通りに近い読み方を求めるなら本文をそのまま記した選択肢が正解になってしまうのであり、それを避けるためにあれこれ工夫することで国語の選択式試験は必然的に悪問になってしまう……。で、「できるだけ解釈を入れない・できるだけ字義通りに近い読み方」を目指していたはずが、結局「出題者の意図に沿う読み方」を目指すことになってしまう……。
仕事でセンター試験(共通テスト)の説明をすることがあるのですが、「作品の読解を伝えている」というよりはだんだん「出題者をなだめている」「出題者の擁護を(何の義理もないのに)している」という気分になってくることがあります。つまり「変な問題だし納得いかないけど許してあげてね、たぶん出題者はこうこう考えてこんな問題を作らはってん、出題者も苦労してはるねん、分かってあげてね」みたいな。センター試験(共通テスト)は、出典の選定には出題者の魂を感じて感心することがある一方で、せっかく良い作品が選ばれていても悪問奇問で台無しになっていることがあり、これじゃ、出題者・受験生・作品の作者、だれも幸せにならないよ……とよく思います。
なんかただの愚痴になりましたが、そのような機微もふまえたうえで、本書で特に面白かったのは「センター試験の小説問題が解釈を許容するのかしないのか」(p.82)というところでした。解釈を入れず単に傍線部を「翻訳」(言い換え)しているだけの選択肢があればそれを「正解」とする、というのが基本ではあるのですが、年度によってはむしろ出題者の解釈が入っている年度もあり、著者によるとそれはその年の出題者によって異なるとの由。そしてその際、それ(出題者の解釈が入っていること)を、「少しだけ文学になっている」と著者は表現しています。
センター試験が「文学」ではないことを示す(「文学」は解釈から始まるから)というのが本書の主旨ですが、その過程で、センター試験がちょっとだけ「文学」であることもあることが分かる、という本になっているのです。
その他面白かった箇所:
「作問するときには『正解』とは逆のダミーを作りがちだし、ダミーがたくさん作れないときには、苦し紛れにセットになるようなダミーの選択肢を作ってしまいがちなのである。人間は四回も嘘をつくようにはできていないものだ」(p.79)。至言。たしかに五択って単に受験生の時間を奪うためだけのシステムだし、作問者もつらかったと思います。今年度は四択になったので、嘘の重圧から一つ分だけ解放されたかな……と想像します。