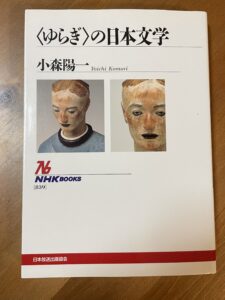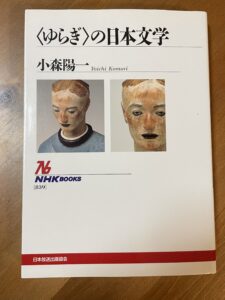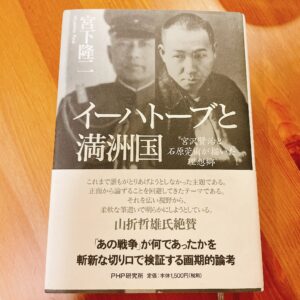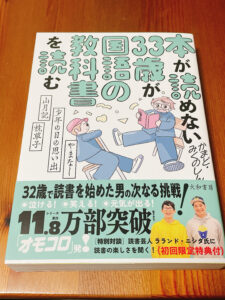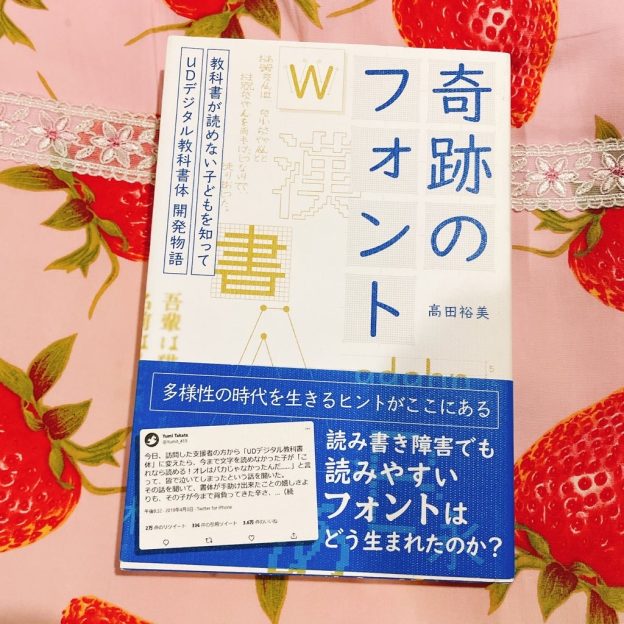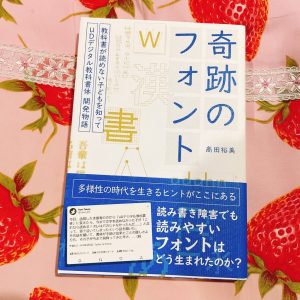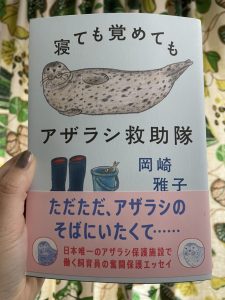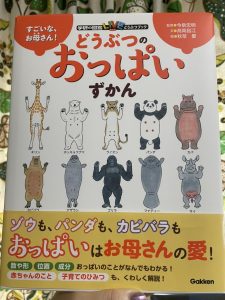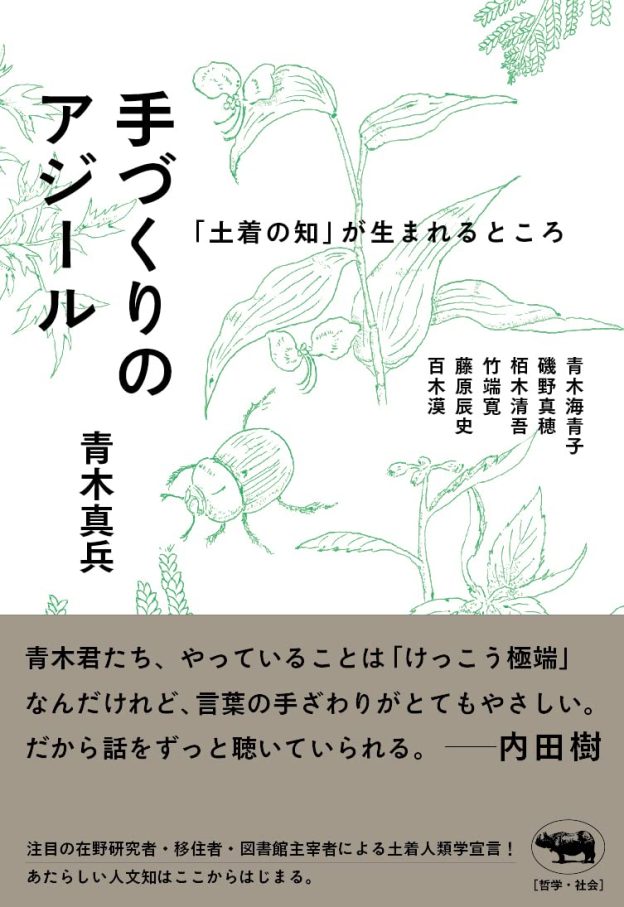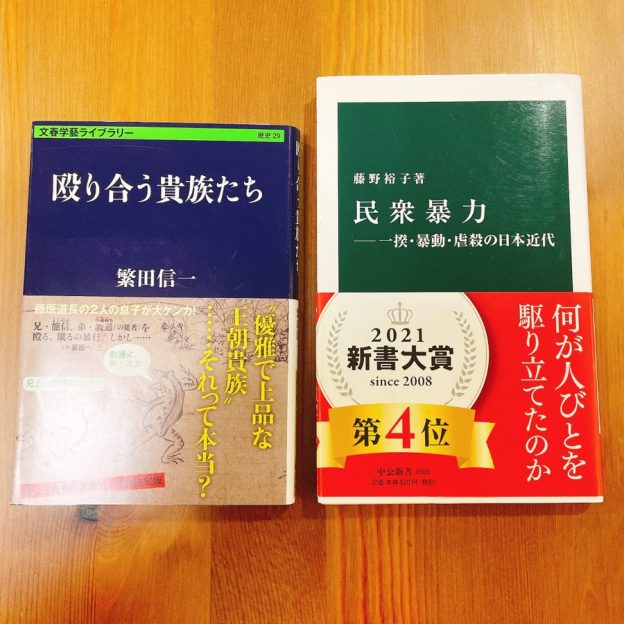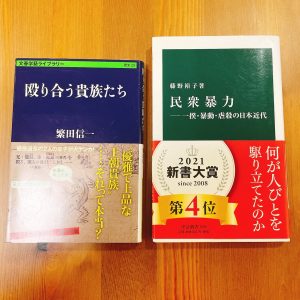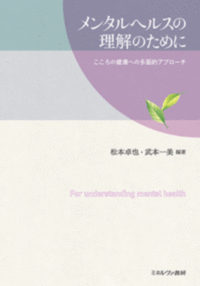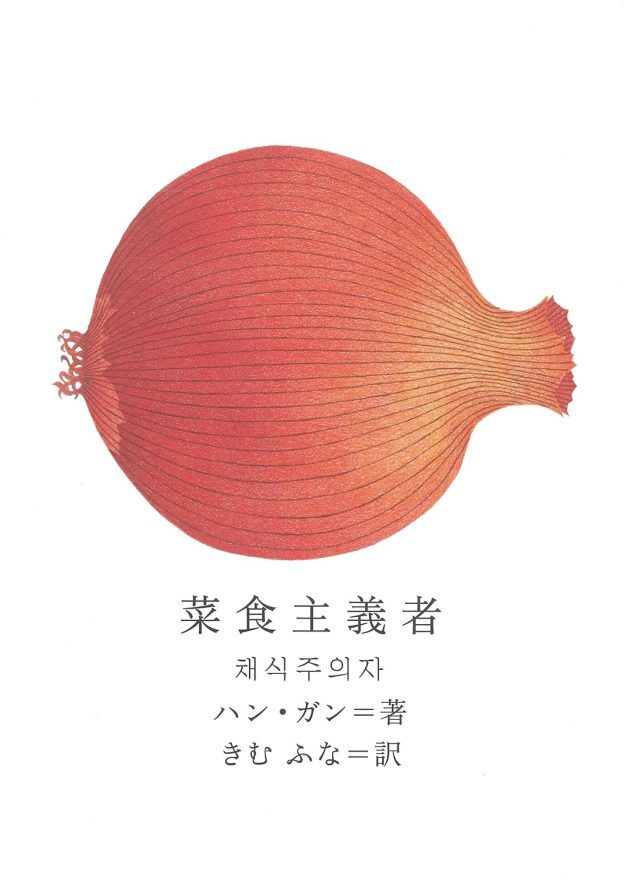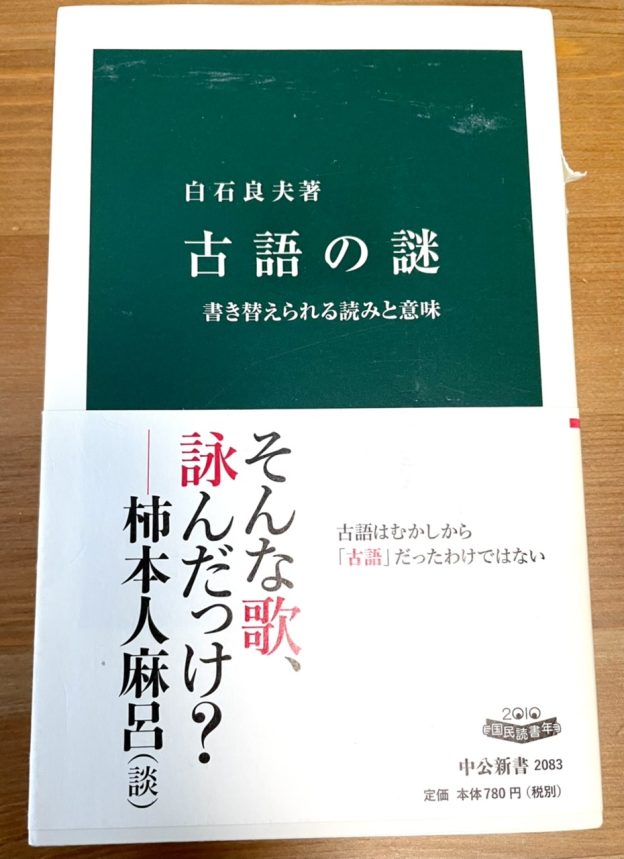おひさしぶりです。村田です。メリクリです。
「陰謀論」に関する本をいくつか読んだので紹介します。
● 烏谷昌幸『となりの陰謀論』(講談社現代新書、2025)

今年出た本でよかった本です。
様々な陰謀論が紹介されており、本書で初めて知るものもありました。たとえば「鳥は本物ではない運動」とか「ゴム人間陰謀論」とか。ネーミングを聞くだけでついつい「いやちょっとwww」と言いたくなってしまうのですが、本書はそうした説を揶揄するのが目的ではなく、陰謀論をグラデーションとして捉えようとする良書でした。
陰謀論には、多数の人に信じられているものと多数の人が荒唐無稽と感じるものがあります。前者はケネディ暗殺陰謀論など。後者は「は虫類人」「平面地球」など。著者もかつて、昨今は否定されているケネディ暗殺陰謀論を信じていたとして、陰謀論をスペクトラムで考えねばならないことに思い至ります。そして人々は皆、そのスペクトラムのどこかに境界線を引き、境界を超えた向こう側に対しては「烙印を押された知識」の態度を取っているのだとします。
これは自分の実感に照らしてもよく分かる考え方でした。たしかに、私から見て「陰謀論者」に見える人もより極端な陰謀論に関しては「自分はあんな陰謀論者じゃないですよ」的な言い方をすることがあるし、また私の世界観も、別の人から見れば陰謀論的に見えることでしょう(私はお金持ちとかはだいたい悪いことをしていると信じています)。
陰謀論を個人的誤謬でなく社会的問題としてとらえ、それは人々の「世界をシンプルに把握したい」欲望や剥奪感(大事なものが奪われる感覚、たとえば「外国人によって土地が奪われる」みたいなやつ)によって増殖するのだ、というのが本書の一貫した主張です。そのとき政治的立場は関係ありません(左右問わず陰謀論は広まりうる)。
一方、重要であるなと思ったのは以下の点。
「留意すべきは、陰謀論者が常に針小棒大な論理で物を考える事実があるにしても、現実政治において陰謀や謀略の果たす役割をあまり軽視し過ぎることも問題であるということです」(p.38)
実際に「陰謀論だと思っていたら本当に陰謀だった」パターンもあるわけで、だからこそ難しい。
では、何をもって「陰謀」と「陰謀論」を区別すればよいのか? といえば、「認識論的権威」に拠るしかないが、今日もはや「認識論的権威」が機能しない状況――大統領となった人までもが自らの影響力を高めるため陰謀論を利用する状況――があり、それこそが陰謀論の興隆を可能にしているのであると本書は言います。
もうひとつ重要なのは、
「陰謀論の内容が馬鹿げていることは、かえって恐ろしい効果を生み出す」(p.159)
というところ。
荒唐無稽な陰謀論に「いやちょっとwww」と言いたくなる、と冒頭で書きましたが、しかし実はそれらは荒唐無稽だからこそ、「踏み絵」として機能するということ。
著者はナチスの例を挙げていますが、たしかに「馬鹿げた言説にのれるかどうか」で忠誠を試す踏み絵は、身近でもいろんな集団で用いられますよね。わざとけったいな新人研修をさせる企業とか理不尽な部活のルールとか。
● 雨宮純『あなたを陰謀論者にする言葉』(フォレスト出版、2021)
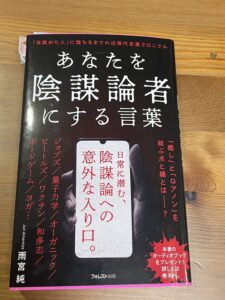
こちらは陰謀論ウォッチャーによる、最新の陰謀論とその周辺の見取り図が描かれた本です(といっても4年前の本なのでここからまた状況は変わっているのでしょうが……)。
表紙には「ジョブズ」「量子力学」「ビートルズ」「ボードゲーム」といった、それ自体では陰謀論と関係ないワードも書かれており、陰謀論への入口が意外なところに潜んでいることが示されています。同時に、狭義の陰謀論だけでなく、カウンターカルチャーやニューエイジへ、ニューソートから自己啓発へ、というムーブメントの系譜が示され、現在「陰謀論」と呼ばれるものが複数の流れの融合の上にあることが分かります。
ひとつひとつの事項の解説は完結ですが、大きな見取り図として勉強になりました。
とりわけ私が関心があるのは、「スピリチュアルが右翼も左翼も包摂するのはなぜか」ということと「精神性を追求するはずの自己啓発が金儲けと結びついてしまうのはなぜか」ということだったんですが、本書がそれを整理する一助になりました。
マメ知識的にも初めて知ることが多く興味深かったです(特に、「『金持ち父さん貧乏父さん』ボドゲや『七つの習慣』ボドゲが存在して多くのボドゲ会で持ち込み禁止になっている」という話)。
余談ですが、ビジネス書(?)をメインで扱っている出版社のようで、この本に挟まっていたチラシに、本書で触れられている「引き寄せ」を唱える人が載っていたのがちょっと面白かったです。
● 斎藤貴男『カルト資本主義 増補版』(ちくま文庫、2019)
上の本で知って読んだルポ本です。2000年の文庫の増補版なのでベースになっている話は古いものが多いのですが、大変勉強になりました。これについては長くなりそうなので、また別に書きたいと思います。
『あなたを陰謀論者にする言葉』では、「大企業が悪いことをしている」という価値観が陰謀論につながる一面を持つことが指摘されていますが、本書では、大企業が超能力研究や永久機関研究に関わっていたり、大企業の経営者がニューエイジやニューサイエンスに接近していたり、という一面が取材されています。
上述の「精神性を追求するはずの自己啓発が金儲けと結びついてしまう」という現象や、上掲書で雨宮氏が昨今のヨガや瞑想ビジネスのターゲットとして挙げている(かつての反近代合理主義者とは違う)「既存の体制や保守的な価値観からは自由になろうとしますがテクノロジーは大好き」な人々、「資本主義や市場経済を否定することは」ない人々、という類型がずっと気になっていたのでしたが、まさにそうしたことについて書かれていました。
詳しくはまた。