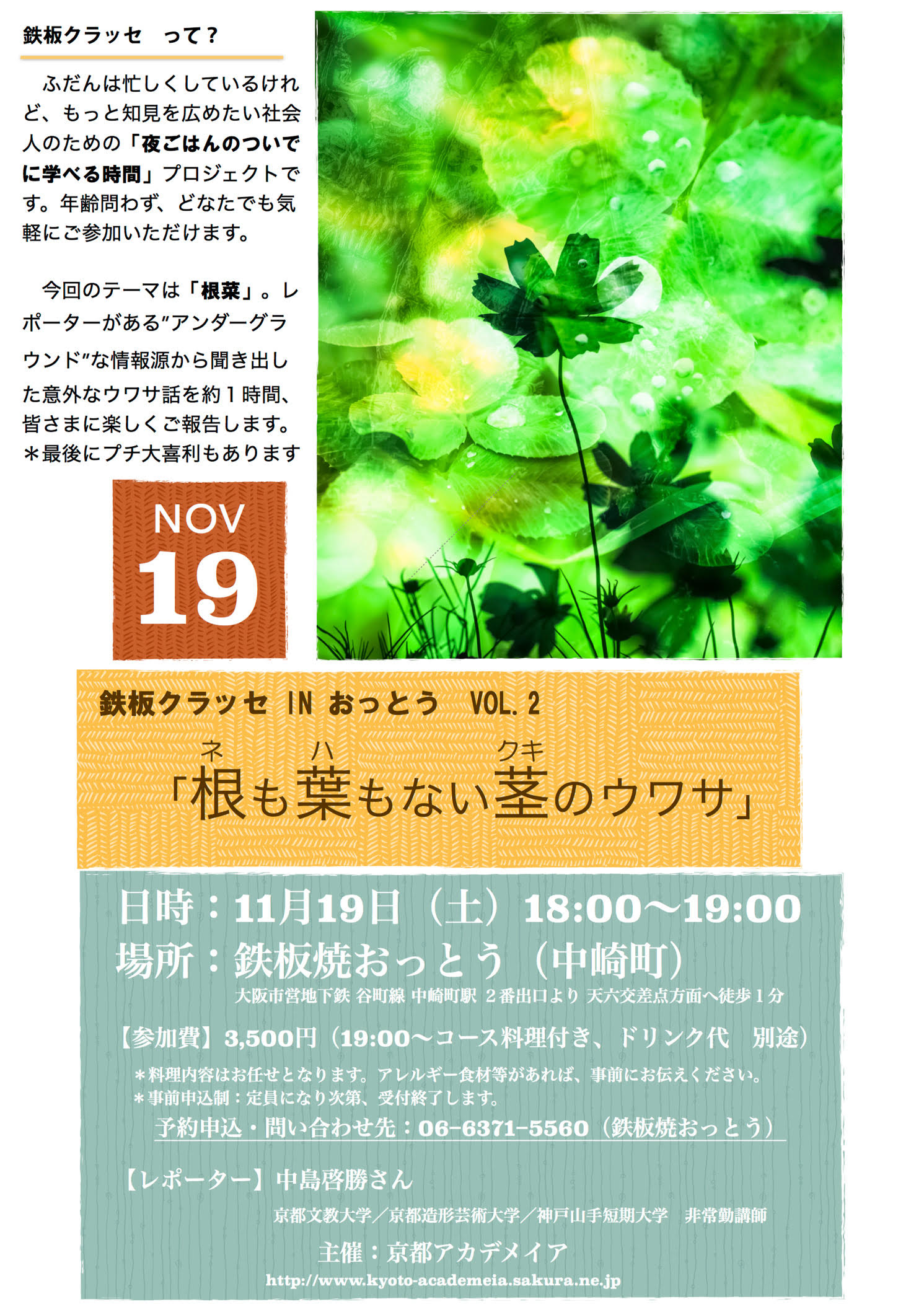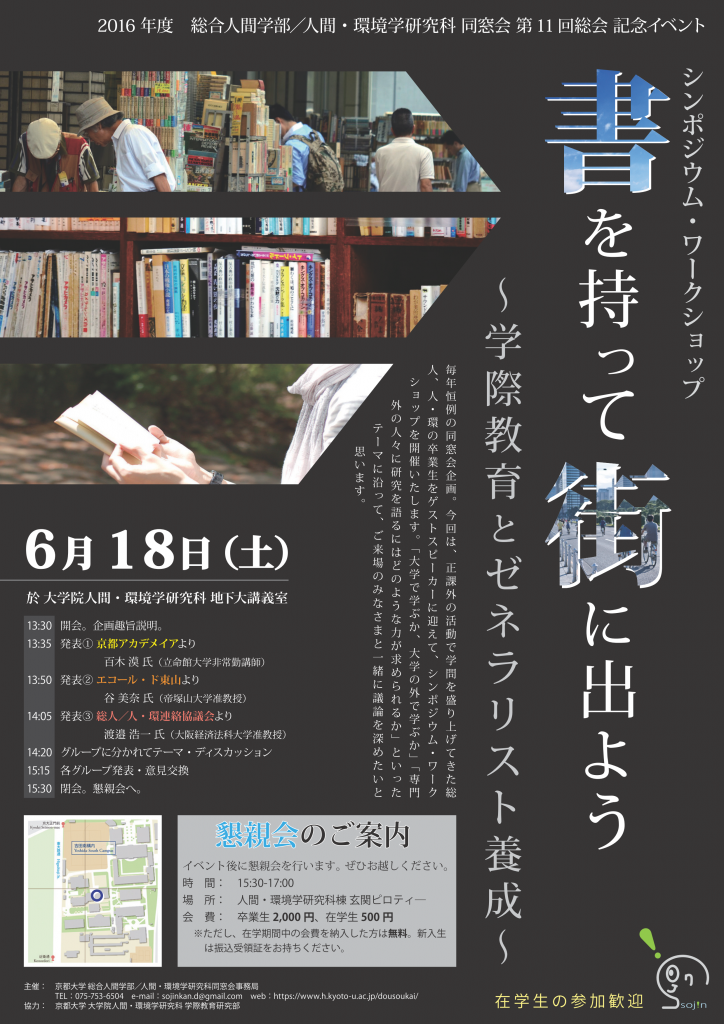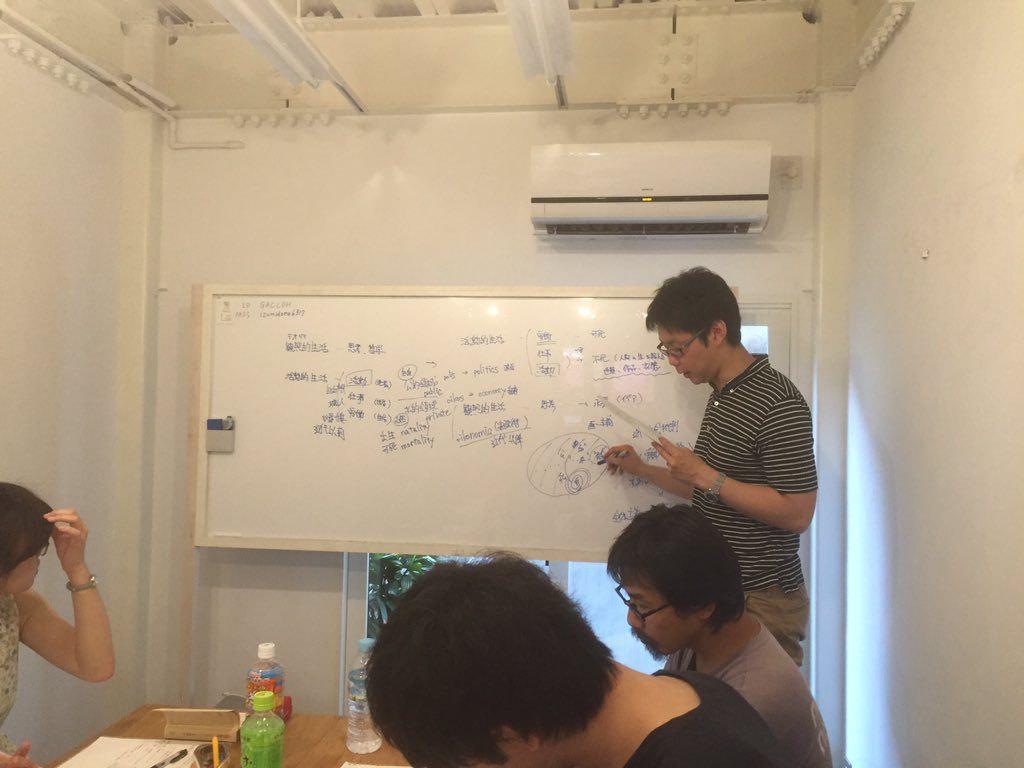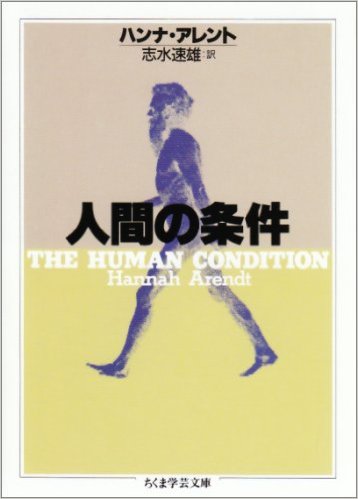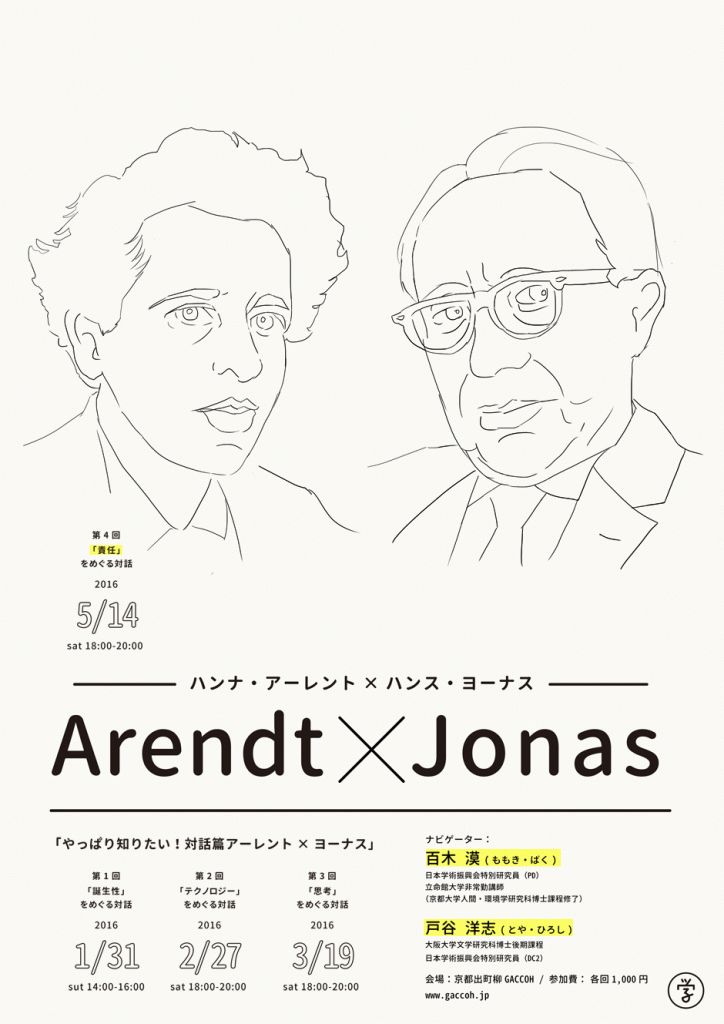会員の中島啓勝です。
さて、突然ですが、昨年7月に京都アカデメイア主催で、私が出演するイベント「鉄板classe in おっとう」が大阪で開催されたことを、覚えていらっしゃる方はおられますか?
いない?はい、わかりました。
開催されたのです。
このたび、待望(!)の第2弾が開催されることになりました。
大阪梅田からすぐ、中崎町駅前にある鉄板焼き店「おっとう」さんで、食材をテーマにトークとディスカッション、そしてディナーを一気に楽しんでしまおうという欲張りなイベントです。
いつもの京アカイベントとは趣を異としますが、ご興味のある方は奮ってご参加いただけたら幸いです。
「週末ちょっと外食するついでに、のぞいて見ようかな」くらいの気軽さで足を運んでいただけたらと考えております。
詳しい内容は下記の通りです。
事前予約制で、問合せ先は京アカではなく会場の「おっとう」さんになっておりますので、ご注意ください。
それでは、よろしくお願い致します。
中島 啓勝
~ご案内~
《イベント名》
美味しく学べる♪
鉄板 classe in おっとう
vol.2『根も葉もない茎のウワサ』
《日時》
2016年11月19日(土)夜
17:30~受付開始
18:00~レポート
19:00~ごはん&プチ大喜利
《会場》
鉄板焼おっとう
大阪市北区中崎2-2-27
*大阪市営地下鉄 谷町線「中崎町」駅から徒歩1分
https://www.facebook.com/teppanyakiottou
~鉄板 classe (テッパン・クラッセ)って?~
ふだんは忙しくしているけれど、もっと知見を広めたい社会人のための「夜ごはんのついでに学べる時間」プロジェクトです。年齢問わず、どなたでも気軽にご参加いただけます。
今回のテーマは「根菜」。レポーターがある”アンダーグラウンド”な情報源から聞き出した意外なウワサ話を約1時間、皆さまに楽しくご報告します。
レポーターからの話のあとは、おっとうの美味しい料理も召し上がっていただき、頭もお腹も、いっぱいになって帰っていただければ幸いです。
*プチ大喜利も開催しますので、ご興味ある方はご参加ください。
《レポーター》
中島啓勝 (京都文教大学・京都造形芸術大学・神戸山手短期大学 非常勤講師)
《参加費》
ごはん(コース)付き 3500円 ドリンク代別
《予約・お問い合わせ先》
鉄板焼おっとう
TEL 06-6371-5560
*事前予約制ですので、お電話でご予約ください
《主催》
京都アカデメイア