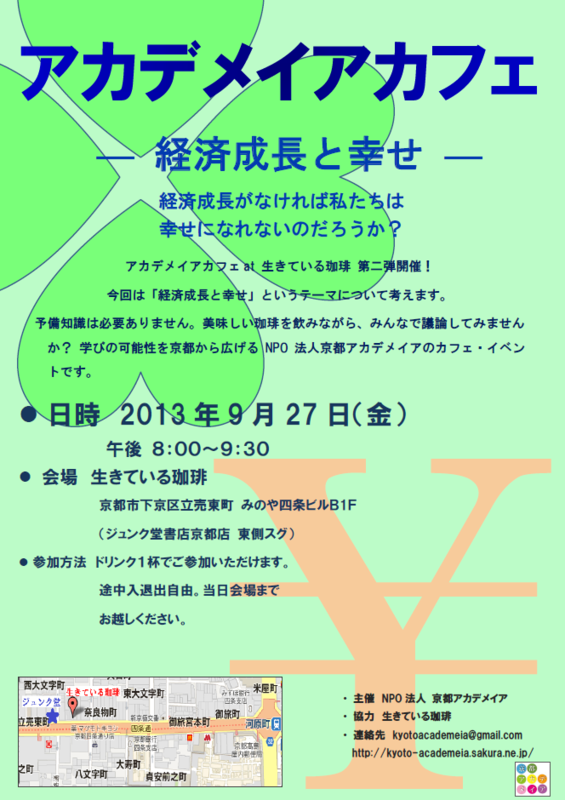次回イベントのお知らせです。
「アカデメイア・カフェ」は、毎回決められたテーマについて、参加者が自由 に議論しあうイベントです。
毎回幅広い年代、職業の方に参加いただいています。予備知識なし、はじめての方大歓迎です。
今回のテーマは「ベーシックインカム」
ベーシックインカム勉強会関西さん、ベーシックインカム勉強会いしかわさんとの共催イベントです。
いま新しい社会保障の仕組みとして世界的に注目されている”ベーシックインカム”。じつはベーシックインカムにつながる考え方は、約200年以上前から、トマス・ペイン、J.S.ミル、フリードマンなど、左右を問わず、多くの人びとによって繰り返し論じられてもきました。 ”最適限度の所得をすべての国民に無条件で保証する”というアイデアは、現代に実現できるのか?
今回は、ベーシックインカムについて基礎から一緒に考えます。
プログラム
・前半:レクチャー(中村さん/ベーシックインカム勉強会いしかわ、高橋さん/ベーシックインカム勉強会関西)
・後半:ディスカッション
「ベーシックインカムはみんなのものです。みんなで話せる感じになれば嬉しいです。なるべく分かりやすく説明しますので、少しでも興味のある方はどなたでもご参加ください」
(なかむら&たかはし)
日時:2015年04月19日(日)18:00-
場所:GACCOH(京阪電車「出町柳駅」2番出口より徒歩5分)
※会場費として一人当たり300〜500円徴収いたします。
当日会場までお越しください。
たくさんのご参加 お待ちしております。
お問い合せはこちらまで
kyotoacademeia◯gmail.com(◯を@に変えてください。)