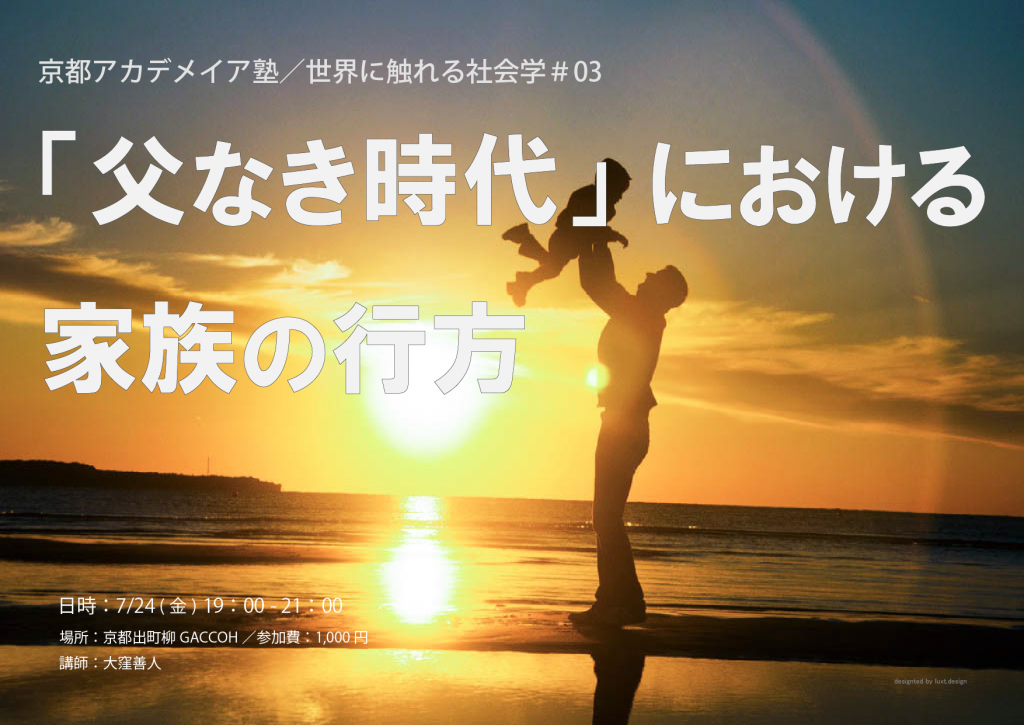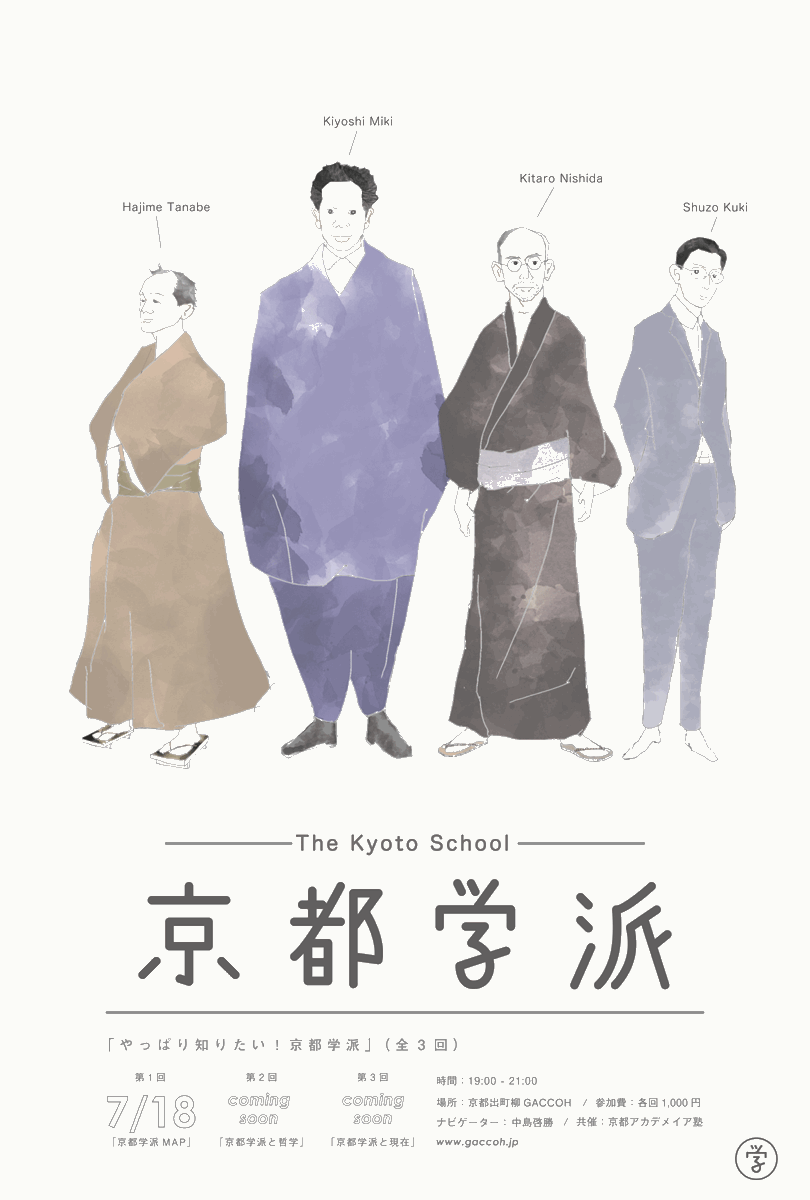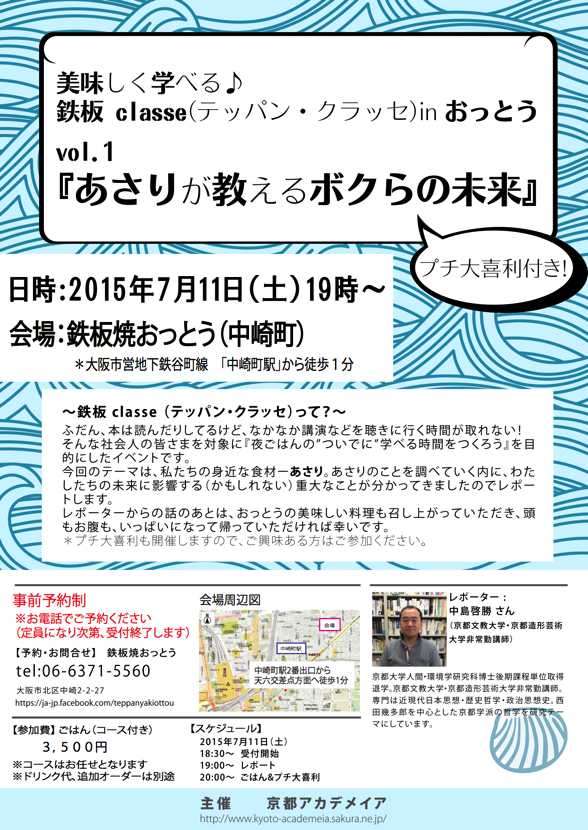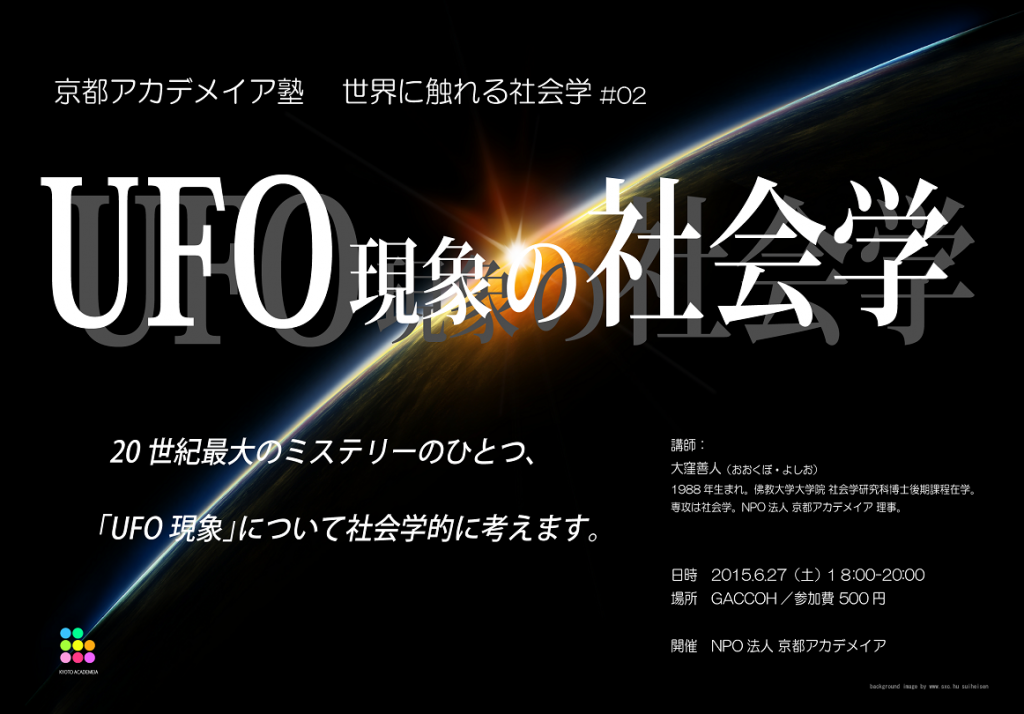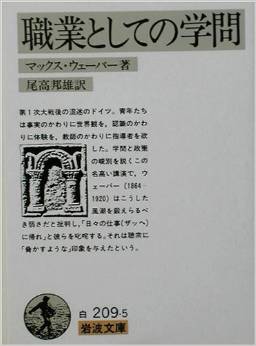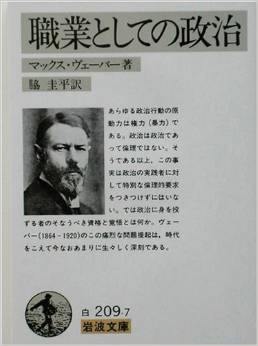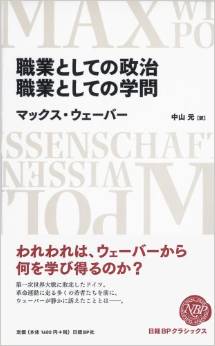去る5月17日に雑誌『nyx(ニュクス)』エコノミー特集の読書会を開催しました。この読書会は、編集者さんの希望で一般告知は行わず、京都アカデメイアのメーリングリストのみで告知をさせていただきました。(こういうケースもあるので、ぜひ京都アカデメイアのメーリングリストにご登録を!今後のイベント情報などお伝えします)
『nyx』は2015年1月に創刊されたばかりの新しい思想雑誌です。若い力で現状の閉塞したアカデミズムに風穴を開けようという意志と気概が感じられる創刊号になっています。第一特集は「〈エコノミー〉概念の思想史 アリストテレスからピケティへ」、第二特集は「現代ラカン派の理論展開」。若手の俊英研究者たちの論考とともに、ピケティ・アガンベン・ナンシーなど海外の著名な研究者の翻訳論文も掲載されていて、非常に充実した内容です。
(参考)堀之内出版blog記事:新思想誌『nyx(ニュクス)』創刊
産経ニュース:実学偏重、業績主義の傾向強まる中、若手研究者が思想誌「nyx」創刊

当日は『nyx』エコノミー特集の主幹をつとめられた佐々木雄大さんと編集者の小林えみさんをお招きしてのイベント開催となりました。
まず私(百木)から『nyx』についての全体的な感想や疑問、そこから発展させた私なりの問題関心などをお話しさせていただきました。次に佐々木さんからそれに対するレスポンスをいただき、さらに参加者全員でディスカッション&質疑応答タイム、という段取りでした。
最後は会場全体で佐々木さんを質問攻め&リクエスト攻め、のようなかたちになってしまって少し申し訳なかったのですが、全体的に議論は盛り上がり、参加者の方の満足度も高かったように感じています。個人的には、図らずも「東京vs京都」の価値観や思考方法の違いが浮き彫りになって面白い化学反応が起こったのではないかなと思ったりもしています。
大きな論点になったひとつのポイントは、「そもそも今『エコノミー概念の思想史』を特集することの意義はどこにあったのか」ということでした。この特集では、古代から現代に至るまで「エコノミー」概念がどのような思想的変遷をたどり、それぞれの時代・社会でどのような役割を果たしてきたかということが詳細に検討されています。「エコノミー」と聞いてわれわれが真っ先に思い浮かべるのはもちろん「経済」(とりわけ市場経済・貨幣経済)という意味ですが、実はこの「エコノミー」という概念はそれだけに収まらない多様で豊潤な意味(役割)を持っていたことが示されます。
例えば、古代ギリシアでは「エコノミー」の語源になった「オイコノミア」は「家政術」を意味する言葉でしたし、中世社会では「オイコノミア」は「神による統治」「神が定めた配置・配剤・秩序」といった意味合いをもっていました。さらに近世社会では「自然のエコノミー」「動物のエコノミー」といったかたちで、自然・生物に与えられた秩序を意味するものでもありました。われわれに馴染み深い「(市場)経済」という意味での「エコノミー」という語が用いられるようになるのは、あくまで18世紀後半以降の傾向にすぎません。
このような「エコノミー」概念の多様性・豊潤さを知るうえではこの特集はとても有用です。しかしそのような概念史的変遷を踏まえたうえで、ではその知見をさらにどのように発展させていくことができるのか、そもそも何のためにこの特集が組まれたのか?というところにまで多くの読者の思考は及ぶことでしょう。その部分に対する明快な答え(方向性)が見えないことが、この特集に対するひとつの物足りなさに繋がるかもしれない、ということを(僭越ながら)述べさせていただきました。
個人的には、現代の「エコノミーの過剰」に対する問題意識がこの特集の背景にあるのではないか、という勝手な推測をしています。ここでいう「エコノミーの過剰」とは、ひとつには「政治」に対する「経済」の過剰の問題であり、もうひとつには「主権」に対する「統治」の過剰という問題です。例えば、前者は1970年代以降の新自由主義の展開として名指されているものであり、後者は大竹弘二さんと國分功一郎さんの対談本『統治新論』などで問題視されているものです。
これらの「エコノミーの過剰」問題に立ち向かうためのヒントを「エコノミー」概念の思想史を辿ることによって掴むことができるかもしれない。あるいは、そのことによって現在の「エコノミー」とは異なる、別の「エコノミー」の可能性(オルタナティブ)を探ることができるかもしれない。この点に「エコノミーの概念史」特集を行う意義があったのではないか、というのが私なりの解釈でした。
そのような「別のエコノミー」の可能性を探るヒントとして、私が個人的に最も関心を持っているのは、佐々木雄大さんの論考の最後に触れられている、バタイユの一般エコノミー論(普遍経済学)です。バタイユは、近代における「市場経済」あるいは「貨幣経済」としてのエコノミーを「限定エコノミー」と呼び、それよりもより包括的で普遍的なエコノミーのあり方を「一般エコノミー」として構想します。ここでいう「一般エコノミー」とは何か。私はバタイユに関しては素人なので精確な説明を与えることはできないのですが、例えばそれは、太陽から降り注ぐ熱エネルギーや、自然・生物がもつ生命エネルギーや、人間社会に内包される諸々の「力」の存在などをも対象とした、〈生産に限定されない消尽・贈与をも考慮に入れた〉より広範囲な「エコノミー」のあり方を構想するものです。
このようなバタイユの「一般エコノミー」論は、現代の「限定エコノミー」がもつ限界(あるいは「限定エコノミー」の過剰化問題)を突破するためのひとつの重要な参照点になるのではないか、というのが私から佐々木さんに投げかけた問いでした。この問いに対して、佐々木さんはひとつひとつ丁寧に答えてくださったのですが、そのなかでも個人的に印象に残っているのは、「しかし、太陽から降り注ぐ熱エネルギーを『純粋な贈与』として捉えるバタイユの視点は、実は、オイコノミア神学の捉え方にほとんどそのまま重なるものでもありうる」というご指摘でした。バタイユの一般エコノミー論に従来の「エコノミー」概念を突破する契機を見出そうとしたところが、実はその試み自体もまた伝統的な神学枠組みのひとつのバリエーションにしか過ぎないのかもしれない。あるいは近代的な「統治パラダイム」(生政治)に対抗して「無為と栄光」の意義を換骨奪胎(脱構築)しようとするアガンベンの試みにも同じようなことが言えるかもしれません。
最後の方はやや専門的な議論かつ説明不足で分かりにくいところがあったかもしれませんが(あるいはより専門的に見れば不正確な記述もあるかもしれませんが)、あくまで実際に行われたディスカッションへのメモということでご容赦ください(もし記述に不正確な部分があればそれはすべて私・百木の責任です)。ひとまずこうした雰囲気で濃密な議論が参加者のあいだで交わされたということが伝われば十分です。
こうした濃密な議論ができたのも、何より若手研究者の方々が中心になって『nyx』という思想誌を創ってくださったからですし、またゲストの佐々木雄大さんがどんな質問やツッコミにもひとつひとつ真摯にお答え頂いたからだと感謝しております。またときどき、こういったかたちで「東京vs京都」の交流イベントができればお互いにとって刺激的な場になるのではないかと考えています。はるばる東京から京都までお越しいただいて、快く議論に参加してくださった佐々木雄大さんと小林えみさんに感謝しつつ、また今後の『nyx』の展開にも期待をしております。また京都アカデメイアでもそれに負けないようにいろいろなイベントを企画していければと考えていますので、今後ともよろしくお願いします。

当日は20名ほどの方に参加いただきました。

東京vs京都(?)の構図。

読書会を終えて佐々木さん&百木で記念撮影。