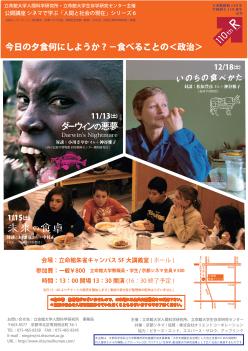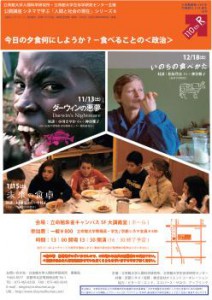百木です。
遅くなりましたが、先日のNF祭イベント・公開討論「いま、大学で〈学問〉する意味」にお越しいただいた皆様、どうもありがとうございました。京都アカデメイアとして初めての公開イベントで、いろいろと至らぬ点はあったかと思いますが、ひとまず無事にイベントが終了し、スタッフの一員としてほっとしております。ゲストに来ていただいたチャーリーさん、信友さん、玉置さんも本当にありがとうございました。
当日回収させて頂いたアンケートや質問用紙の中から、いくつか頂いたご意見を紹介したいと思います。
「大学内で閉じた議論という印象で残念」
→今回最も多かったご批判です。この点はパネリスト・スタッフの間でも反省する点も多いです。プレゼン力が未熟でこちらの意図をうまく伝えられなかったということもありますし、議題の立て方や進行の仕方などをもっと工夫すべきだったと思う点もあります。ただ、今回は大学と〈学問〉の意義を再考するということが一番大きなテーマだったので、大学内から見た議論が中心になったのは止むを得なかったかなと感じる部分もあります。せめて第二部では「大学を超えて〈学問〉する可能性」の話、つまり〈社会〉の側から見た議論をもっと展開できればよかったのですが、こちら側の力不足でそのテーマを十分に論じられませんでした。そのなかでも、学部生の田中さんが〈社会〉に出てからも〈学問〉する可能性を発言していて好感を持てた、という意見も多く頂きました。
「議論が拡散している・パネリストが多すぎ」
→この点はやや欲張りすぎた面があるかもしれません。議題を4つ設定したのですが、大学の就職予備校化・高学歴ワーキングプア問題・社会に出てから〈学問〉する可能性・京都アカデメイアの今後と、観点や規模の違う話を4つ盛り込んだので、議論が拡散した印象を持たれた方もいらっしゃったと思います。ただ、いっぽうで「大学や学問に関する幅広い議論が聞けて面白かった」「大学や教養の意義について考えるきっかけを得た」「大学とビジネスの関係について気付きがあった」など肯定的な意見も多数頂きました。議論の幅を広げることで面白いと感じていただける方もいれば、もっと絞ったテーマで深い議論を聞きたかったという方もいらっしゃったと思います。この点も反省すべき点を見極めてスタッフ間で話し合い、次回の企画に生かしていきたいと考えています。
「Ustream中継やtwitterのハッシュタグ設定を行ってほしかった」
→この意見もいくつか頂きました。Ustream中継については、今回は機材を揃えられなかったこととオフレコ話ありのライブ感を演出したいという意図から実施しませんでした。ただビデオ撮影は行いましたので、後日一部(か全部か検討中)をYouTubeにアップする予定です。アップロードしましたらまたブログやtwitter上でお知らせします。ハッシュタグについては、会場でiPhoneが圏外ということもあり、特に設定しなかったのですが数名の方から要望を頂きましたし、実際にハッシュタグを設けて中継してくださった方もいらっしゃったので(ありがとうございます)、次回このような機会があればハッシュタグは設けるつもりでいます。Ustream中継については主に機材面と技術面の理由から次回も実施するかどうかは不明です。
「文系と理系の間で距離を感じた。理系の意見が十分に取り入れられずに残念」
→この点は反省するところが大きいです。本当はパネリストの一人に理系の方をいれられれば良かったのですが、都合のつく方がおらず断念しました。次善策ということで、当日理系の方数名にマイクを回したのですが、ひとつひとつの質問に十分に答える余裕がなく、質問を投げっぱなし状態にしてしまったことは申し訳なかったです。今回は必然的に文系から見た大学・学問の話になってしまいましたが、京都アカデメイアの理念のひとつが「文系・理系の枠を超えて学びあう〈場〉を創る」ことなので、今後はもっと理系の方にも積極的に前に出てもらい発言してもらえれば、と考えています。ひとまずは、近々、京都アカデメイアのスタッフが近しい理系の方数名から意見を聞く場を作り、今後、理系と文系が交流・融合する可能性を探っていくつもりです。
「もっと会場とのやりとりがほしかった」
→会場とのやりとりについては、質問を用紙で回収することで出来る限り多くの質問も答えようとしたつもりなのですが、それでもやはりすべての質問に答えることは出来ませんでした。もう少し時間があれば直接会場にマイクを回す時間も設ける予定だったのですが、時間が押していたため断念しました。長時間のイベントだったので、第1部や第2部の間にも会場からの声を拾う工夫はできたかもしれません。この点も次回以降のイベントの教訓として生かしていきます。
「チャーリーさんや信友さんの話をもっと聞きたかった。他のパネリストが邪魔をして残念」
→この点については難しいところです。チャーリーさんや信友さんのほうがプレゼンは明らかに上手ですし、チャーリーさんや信友さんの理論的な整理から多くの学びを得たという声は多かったです。いっぽうで、今回の企画を「鈴木謙介氏講演会」ではなく、あえて「公開討論」というかたちにしたのは、無謀とは知りながらも、チャーリーさんをあくまでいちパネリストという位置づけに置かせてもらい、チャーリーさんと京大生(京大卒業生)がガチ討論する!という企画に挑戦してみたかったからです。その挑戦が成功に終わったか失敗に終わったかは聴衆のみなさまの判断にお任せするしかありません(両方の意見を頂きました)。ただ、ゲスト除くパネリスト一同、それぞれのプレゼン力の至らなさを痛感しており、次回このような機会があったときのために、さらにプレゼン力を磨く必要があることは自覚しております。
「第2部での京大生によるチャーリーdisはいかがなものか」
→この点についても難しいところですが、チャーリーさんをdisったことが問題というよりも(チャーリーさんには寛容に受けとめて頂き感謝しています)、そのdisり方が問題だったのかなと思います。パネリスト間でもっとテーマを共有し、どのような点について議論するのかという意識を明確にしておくべきだったのでしょう。その意味で、やや議論が拡散した印象、感情的なイチャモンをつけている印象、建設的な議論がなされていない印象を与えてしまったとすれば、チャーリーさんにも聴衆の方々にも申し訳なかったです。チャーリーさんのような話術巧みかつ頭の回転が早い方に現役京大生が議論を挑もうとすること自体が無謀な挑戦であったわけですが、その挑戦じたいはやはりしてよかったと思いますので、今後はゲストの方を批判するにももっとそのプレゼン力をあげて臨まなければと考えています。
「聴衆を意識した議論になっていなかった」
→この点はひとえに我々の力不足です。ひとりひとりのプレゼン力を上げることと、進行の仕方や議題設定を工夫することで、次に繋げられればと考えています。
「チャーリー、信友さん以外にもうひとり全体を掴んで議論できる人がいたほうがよかった」
→上記質問の回答に同じ。
他に肯定的な意見として以下のようなご意見も頂きました。
・スタッフの人が優しかった。
・時間の大きな遅れがなくよかった。(ただし4時間は長すぎるとの意見あり)
・漫才風の前説の心意気good!(ただし「お笑いはいらないのでは?」との意見もあり)
・京都アカデメイアの理念に共感。こういった試みを他大学・他地域にまで広げてほしい。(京アカの理念を明確に定めるべきとのアドバイスあり)
これでもすべてのご意見を紹介できてはいないのですが、主なものを紹介させて頂きました。
これらのご意見・ご批判を真摯に受け止め、今後の京都アカデメイアの活動に生かしていきたいと思います。
またブログやtwitterでも多くの方に感想をコメントしていただきました。ありがとうございます。
togetterとブログ記事を紹介させて頂きます。
togetter 京都アカデメイア公開討論「いま、大学で〈学問〉する意味」
京都アカデメイアの「公開討論」に行った。 – あらやしき
「更新されゆくリアリティー」~鈴木謙介さんが参加した京大11月祭公開討論「いま、大学で<学問>することの意味」を聴いて~ -文化ブログ
その他にもご意見・ご感想等あれば、kyotoacademeia□gmail.com(□に@を入れてください)までどんどんメールください。今後も、「様々な専門分野の〈知〉を横断した〈学び合いの場〉を創出する」という理念のもと、京都アカデメイアの活動を広げていければと考えていますので、長い目で見守ってくだされば幸いです。
長文失礼致しました。