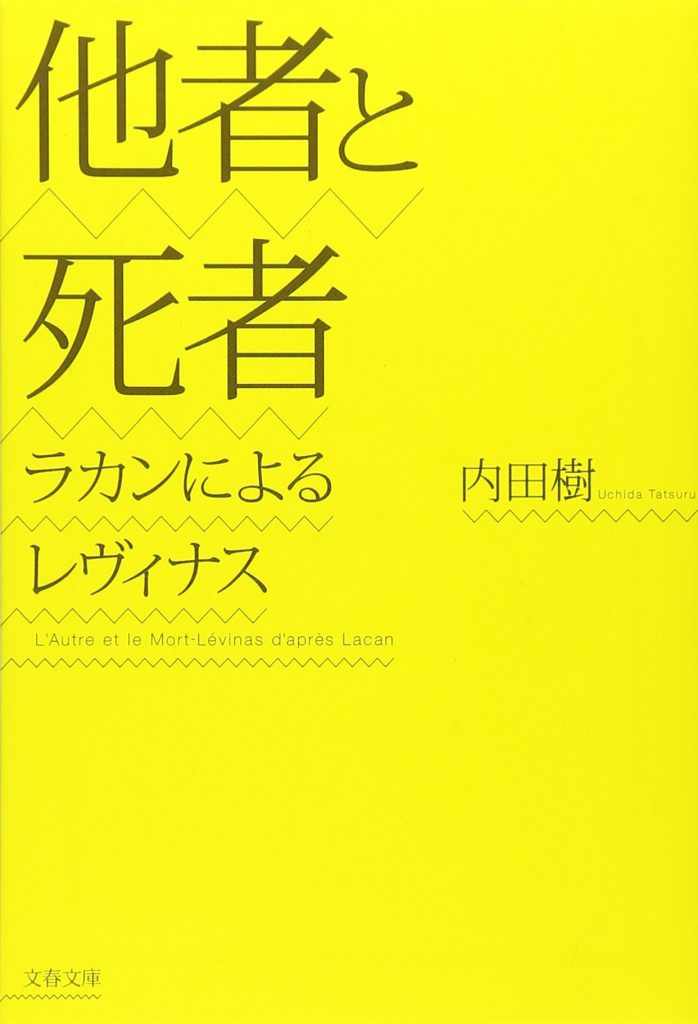内田樹『他者と死者』の書評の末尾の部分で、評者は次のようなことを示唆した。西洋ではヘブライズムの一神教的伝統が近代社会にあってもどこまでもつきまとうために、そこからの逃走ないし脱構築のポストモダン的実践は、いくらフランス流のエスプリをきかせてもその身振りとは裏腹にどこか深刻なものがついてまわる。この点で、日本のニューアカデミズムの称揚したポップさとそれとはじつは似て非なるものだったのではないか、と。
だとすれば、近代の普遍性をまずは額面通りに受けとらず、その文化的・文明的なバックグラウンドに慎重に目をむけることがなお必要だというべきである。ここでは、こうした点についての簡単な考察を行ってみたい。世俗性を表看板とする近代社会を非西洋圏で確立させるうえで、キリスト教への「改宗」がそのための要件とはされていないのはもちろんである。しかし、少なくとも西洋世界の一神教的背景を知っていなければ、世俗的な理念――人権や民主主義――にたいして彼らが示す、ほとんど宗教的に映じるほどの強いコミットメントの源泉は理解できないだろう。
世俗化された近代的理念が、しかしある面では絶対的で超越的な価値として理解されていると考えなければ、たとえばシャルリ・エブド周辺のジャーナリストたちが示した「蛮勇」の本質はとらえることができない。自己保存を旨とする個人のもっぱら合理的な選択の結果として正義を考えるのでは、自己の生命を大きな危険にさらしてでもこの種の価値の実現に奉仕しようとする人びとの行動は、とても説明できないからである。
ヘブライズム的拘束のない世界におけるポストモダン
逃れるべき一神教的伝統など存在しない世界における後期近代――それをポストモダンと見るかどうかは別として――という時代は、それ固有の歴史的課題を提出する。あらためて、われわれには理念や価値というものを成立せしめる「絶対的なもの」や「超越的なもの」といった観念に欠けるところがあったのではないかという密かな疑念が、浮上しつつある。
前期近代における近代性や近代社会についての基本的な建前は、それが特定の文化に依存しない普遍的な価値を提示しているというところにあった。個人の自由、人権、基本的平等、民主主義、法の支配といった近代の諸価値は、その由来は西洋世界にあるとしても、その起源を超えてあらゆる社会に普遍的に受容可能であり、移植可能であると考えられた。それと同時に、とりわけリベラリズムの潮流において、そうした基本的諸価値は、具体的な内実をともなった善というよりは形式的な正義という形態をとって理解され、社会の基本構造のみに関与するミニマルな価値として定位される。法や政治の領域は一定の普遍的な価値によって制度化されるが、その領域は建前上は必要最小限のものとして制限され、広大な私的領域においてはそれぞれの社会や共同体の固有の文化が大きな場所を占めることができるとされる。
みずからをミニマルなものとして自己限定したうえでその普遍妥当性を主張する、このような近代的諸価値の体系は、後期近代にいたって、ポストモダンやラディカルな多文化主義によってその欺瞞性が告発されるようになったことももはや周知の事項に属するだろう。コミュニタリアンらによる批判に応えるなかで、後期ロールズが正義の普遍主義的な基礎づけをなかば断念し、重なり合う合意が事実的に存在することをもってみずからの正義論を再構築しようとしたという、これまた比較的よく知られた事実は、象徴的な意味をもつだけではない。それが示唆するのは、リベラリズムが実際の文化政治のなかで十分な説得力と影響力をもちえなかったというだけでなく、その理論構成に原理的な困難が存在しているということでもあったからである。
こうした流れのなかで、近年は政治哲学の領域などでこうした普遍主義批判の議論を迂回するような形でふたたび規範理論の構築を志向する動向も見られるが、とはいえこうした批判が原理的なものである以上(重田園江『社会契約論』に対する筆者の書評を参照のこと)、普遍的に通用するような規範を再興するための土台はなお揺らいだままである。したがって、発祥地域を超えてかつてなかったほどに世界的な影響力をもつようになった近代西洋文明がどのような文化的バックグラウンドのもとに成立したのか、この点にあらためて目をむける必要があるように思われる。それは、ラディカルな多文化主義が行ってきた西洋中心主義批判という、言説闘争にあまりに傾いた実践とは多少とも異なるものである必要があるだろう。
他方、リベラルな諸価値はその真理性が「証明」されることによっておのずと実現されるものではなくて、それを支持する人びとのコミットメントを作りだす公共文化が存在してこそ堅持されると主張する政治哲学の潮流として、リベラル・ナショナリズムがあげられるが、この種の議論でも十分でないところがある。というのは、通常、リベラル・デモクラシーを受容している大社会を構成するそれぞれの文化共同体は、多少ともそうした形式的価値に親和的な固有の文化的価値を有しているものであり、それを支援し活性化することでリベラル・デモクラシーの形式を支える文化的実質としての公共文化は涵養されるだろうという想定が、こうした議論には含まれているからである。しかし、たとえば一見中立的に見える人権や人間の尊厳の観念に含まれる絶対的な性格が、実のところ一神教的伝統に大きく由来しているとするならば、それに対応するような文化的要素を、多神教世界やアニミズム崇拝を有するような原始的社会に見出すことは一挙に困難となるだろう。リベラル・ナショナリズムの議論は、リベラルな公共文化への実質的な支持を社会から調達するという実践的な目的を離れてみるならば、こうした原理的な問題を提出する理論として読み直すこともできるものである。
戦後の日本は、上述したような前期近代の価値的前提、つまり自由や民主主義といった近代的価値は西洋由来ではあるけれどもそれを超えて非西洋圏にも普遍的に受容可能であるという前提のもとに、封建遺制を解体して近代化に邁進すべきとの公式見解を掲げた。実際には、戦後知識人の一部は、日本における真の近代社会樹立のためにはミニマルな改革以上のことが必要だと考えただろう。すなわち、大塚久雄や丸山真男などは単なる表面的な制度改革だけではなく、一種の文化革命が戦後日本には必要だと考えた。それは日本文化への根本的批判を含む社会の構造改革であり、ある意味で「日本改造計画」でなければならなかった。つまり、私的・文化的領域は温存しつつ公的領域における政治経済の諸制度を改革していくといったミニマリズムの建前は、ほとんど視野の外に置かれていたのである。彼らは和魂洋才論を批判した明治期の福沢諭吉と同じように、そのような生ぬるい考えでは真の近代化は達成できないと密かに考えていたわけである。
けれども、その文化的革命は、封建的で非近代的な文化を徹底して取り除いていけばおのずと達成されるといったものではなかったようである。たとえば大塚久雄は、「資本主義の精神」を真に確立するためには、「プロテスタンティズムのエートス」あるいはその機能的等価物が不可欠だと考えていた。その妥当性はここでは問わないとして、パラレルなテーゼが政治社会についても提出できそうである。日常生活で基本的人権に配慮した振る舞いをするというのにとどまらず、究極的な場面でもそうした価値――そこでは広義の法的概念としての人権を超えて人間の尊厳という価値が前景化するだろう――に敢えてコミットするだけの近代的精神を真に確立するためには、キリスト教のエートスに相当するような精神的基底が必要だというテーゼである。ここでその価値は、不可譲の絶対的な価値として擁護される。ところが、それが実際に何であるかという価値の本質や内実にかんしては括弧に入れるとして(個人の自由はそうだが民主主義はそれに当たらないとする立場もあるだろうし、世俗的価値ではなく宗教的価値のみがそれに値するという立場もありうる)、そもそもそうした絶対的価値というもの自体が存在するとは考えないような信念体系を有する社会も、当然ながら存在するのである。
おそらくここに、一神教文化と多神教文化の重大な相違がある。だとすれば、ほかのどんな価値とも天秤にかけられるべきではない、それ自体で正しい――つまり他のものとの関係に依存しない――価値というものが、文化の信念体系のなかに存在していること、これが近代的諸価値をこうしたものとして受容するための必要条件となる。それは十分条件ではない。しかし、これだけで次のことが帰結してしまうのである。すなわち、少なくとも一神教的な精神構造がその社会にあらかじめ存在するかのちに確立されるかしなければ、人権を不可譲の価値として理解し実践することは不可能だ、ということが。(続く)
上野大樹