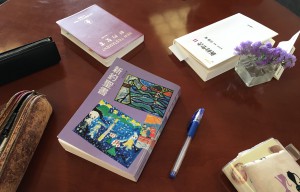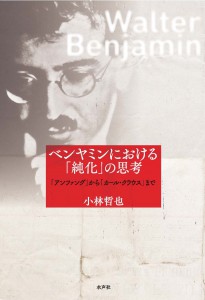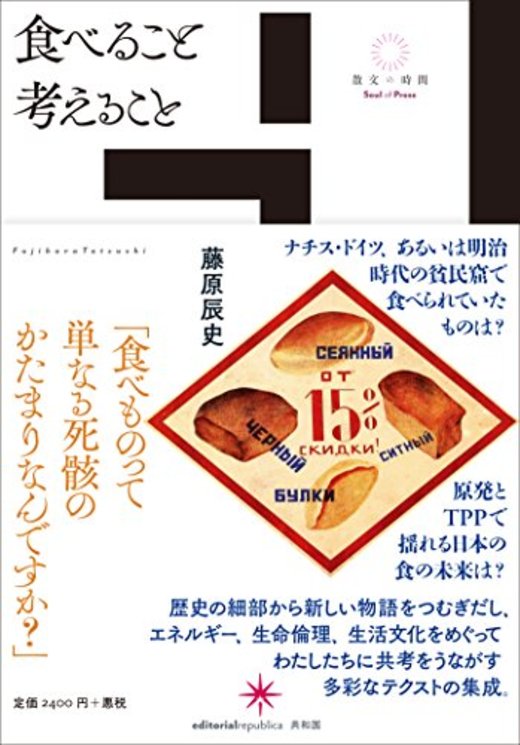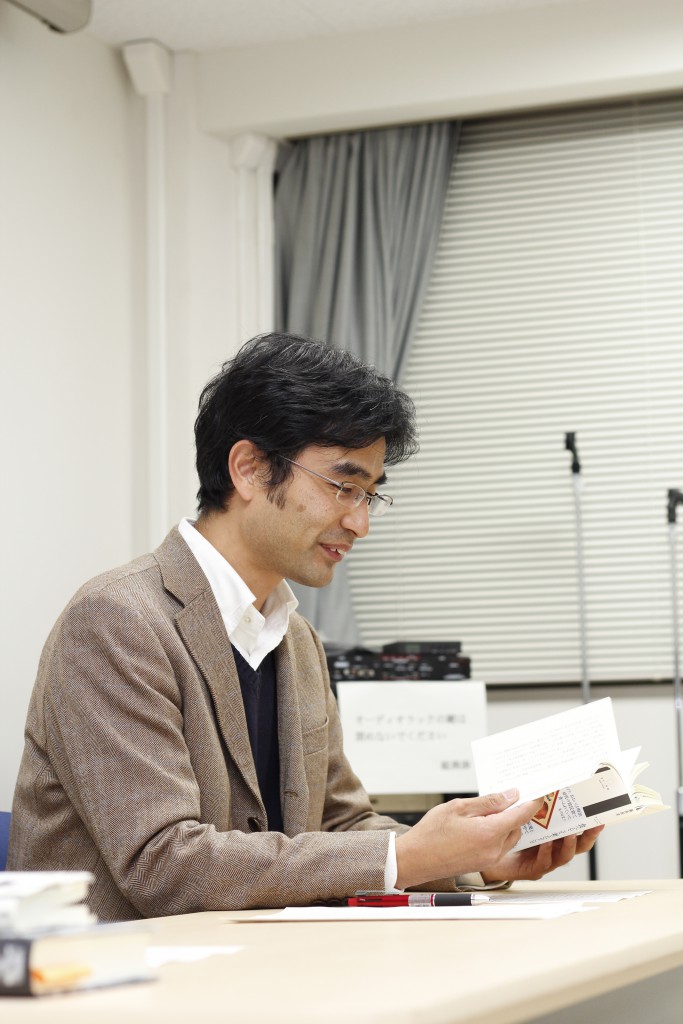超おひさしぶりです、村田です。
夏前くらいからほそぼそと、聖書読書会を続けております。
Fさんの発案で始まったこの読書会、Fさんいわく、「信仰のない者たちが平日に聖書を読んであれやこれや言う浮世ばなれした集い」 ということで、参加者も興味関心もバラバラ。
私は、自分は西洋文化の素養がないなあ、と常々思うており、その基盤となるところの聖書をちゃんと読まねば……とは思うていたのですが、聖書ってひとりで読むにはなかなか意外にハードル高いのですよね。前提が分からんかったり、謎の比喩が出てきたり。というわけで、皆でああとちゃうか、こうとちゃうか、と言い合いながら読めるのは有難いのです。
(ちなみに、昔、人文系知識人何人かに、「読んでいるべきなのに読んでいない本」アンケートを取ったところ、2位に聖書がランクインしたという話を聞いたことがあります。1位は『資本論』だったとか。)
聖書を読むだけでなく、毎回、そこからの連想であちこちいろんなところに話題が飛ぶのも愉快です。それぞれの専門分野から無駄話まで(無駄話をするのんはだいたい私ですが)。なぜか今、仏教の専門家多めなので、仏教の裏話をいろいろ聞けるのが面白かったりします。
レジュメは切らない輪読形式の読書会なので、興味ある方はお気軽に参加ください。(信仰のある方もない方もどなたでもどうぞ。) 日時はだいたい平日午前に隔週で、人数は3~6人で続けております。マタイ福音書を(半年くらいかけて)読み終わり、最近、「コリント信徒への手紙」に入ったところです。
新約聖書であれば、訳も言語もなんでもOKです(下の写真ではどれも新共同訳ですが……)。
場所は今のところ、京都大学時計台内の京大サロンを使っています。
京大サロン、できた頃は「気取ったもん作りやがって」と思ってましたが便利ですね。あと、毎日、日替わりでいろんな可愛いお花が飾られているのがひそかに楽しみです。話がそれたところで、お花の写真をupして終わります。