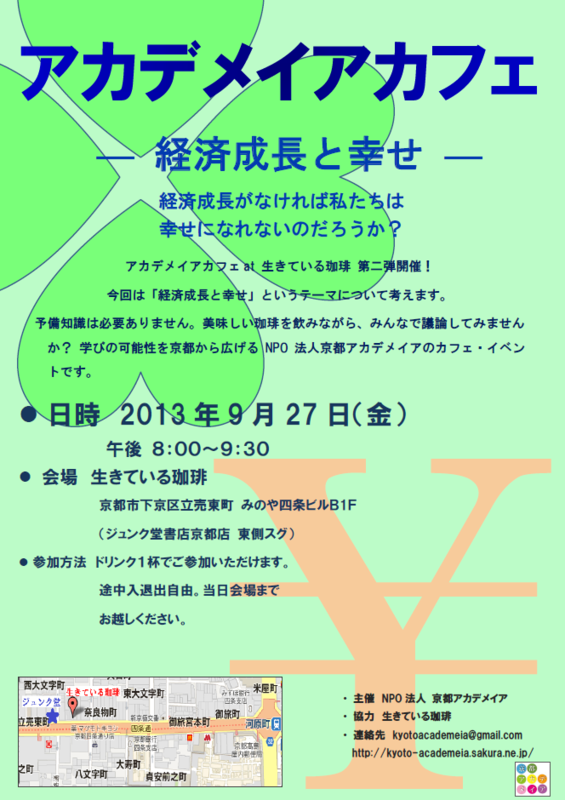百木です。第5回目の批評鍋では『ゆとり京大生の大学論』を取り上げました。
ゆとり京大生の大学論―教員のホンネ、学生のギモン
作者: 益川敏英 ,橋本勝 ,毛利嘉孝 ,山極寿一 ,山根寛 ,吉川左紀子 ,河合潤 ,佐伯啓思 ,酒井敏 ,阪上雅昭 ,菅原和孝 ,杉原真晃 ,高橋由典 ,戸田剛文 ,安達千李 ,新井翔太 ,大久保杏奈 ,竹内彩帆 ,萩原広道 ,柳田真弘 ,辻井タカヒロ 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版 発売日: 2013/06/01メディア: 単行本この商品を含むブログ (6件) を見る
この本は、昨年から京大で起こった「大学改革」の流れをうけて、現役京大生(ゆとり京大生)6人が自主的に企画して出来上がった本です。こちらの記事 をご覧ください)
当日は、この本の編集・企画者のひとりである安達千李くんがゲストで参加してくれました。このような本を作ろうと思った経緯から、作る過程での苦労話、作り終えたあとでいろいろ考えたこと、本に盛り込めなかった裏話など、いろいろと興味深い話を聞かせてくれました。
読売新聞の紹介記事:「ゆとり世代 京大生の大学論…6人で編集・出版」 毎日新聞の紹介記事:「京都・読書之森:ゆとり京大生の大学論 /京都」
批評鍋参加者からの感想としては、
・揶揄/自虐にむかいがちな「ゆとり世代」をポジティヴにとらえてるのが新鮮
などといった意見・批判・疑問などが出されました。
それに対する安達くんからのレスポンスやその後の議論などが気になる方はYouTubeに残されている動画などを見ていただければと思います。大学外での学び(ラーニング・コミュニティ)について、安達くんから、1)場所、2)人、3)質、の3点をどう確保するのか 、という課題が投げかけられたことです。この問題は、まさに「大学の外での学びの可能性」を追求してきた京都アカデメイアが抱える課題でもあります。それに対しても、参加者からいくつかのレスポンスがあったので、こちらも関心ある方は動画をご覧ください(動画後半のほうです)。
今回の大学改革は京大だけの問題ではなく、日本の大学全体の問題へと発展しつつあります。それが悪い面だけを持っているわけでもないと思うのですが、やはりいろいろと疑問に感じてしまうところがあるのも事実です。もはやこの改革の流れは止めようがないもののようにも思えますが、この『ゆと京』本のように、それぞれの立場からこの問題について考え・議論し、声をあげるべきところで声をあげていくことはとても大切なことだと思います。「いまこそ大学に〈ゆとり〉が必要なんじゃないか」 という座談会でのゆとり大学生の発言でした。本当にその通りだなぁ、と感じました。「ゆとり乙」と揶揄されがちなゆとり世代ですが、むしろその強みを活かして、ゆるい立場から・しかし本質的な問題に切り込んでいる彼・彼女らの姿にこそ、いまの大学の希望があるのかなぁと思ったり、自分もそれに負けずに頑張らねばなぁと思った次第です。
大学のあり方、大学で学ぶ意味、大学の外で学ぶ可能性、教養とはなにか、なぜ学問するのか、などのテーマは、これまでも京都アカデメイアのイベントの中でたびたび議論されてきたことですが、今回の批評鍋でまた少しその議論を前に進めることができたかなと思っています。今後もこれらのテーマについてはいろんな機会に考え続けていくつもりです。
参考:大窪くんによる書評:吉見俊哉『大学とは何か』(岩波新書)