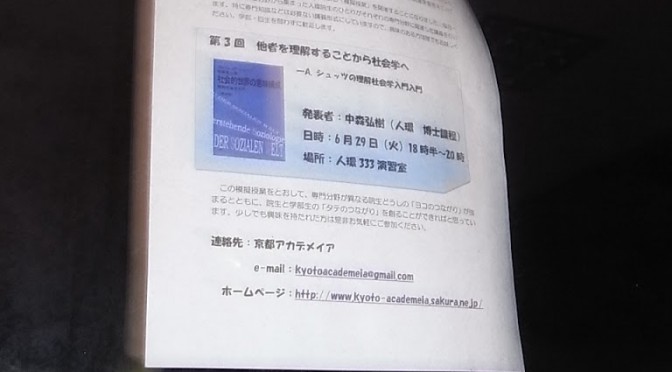百木です。
先週の作戦会議の議事録です。
■模擬授業について
・テーマ選びは自分の専門に近いほうがよい(中森)
→そのほうが質問などにも答えやすい。
・どのような経緯でそのテーマに興味をもったのか、学問への「斬りこみ方」を知りたい(中山・安達)
・ディスカッションをどう盛り上げるか(百木)
→そもそもディスカッション(ヨコの議論)なのか質疑応答(タテの応答)なのか。
→基本は質疑応答。+αとしてディスカッション。
(ディカッション中心にすると院生どうしの議論が盛り上がりがちなため。
・司会者の裁量を増やしてもよいのではないか(百木)
→議論の簡単な整理、学部生へのフリ、ディスカッションの種をまくetc
・専門発表の機会を別に設けてもよいのではないか(浅野)→今後企画していきます(百木)
・理系をいかにして取り込むか(並河)
→後期は理系テーマの模擬授業を企画予定。
・年間を通しての目標を立てておいてはどうか(中森)
→前期は人環・総人の文系を中心に取り込み、後期で理系にまで範囲を広げる。年間通して人環・総人全体に認知度を広める(百木)
■人環フォーラムとのコラボ案
・企画じたいまだ動き出したばかりなので、今後の動向を見つつ計画を立てる
→安達くんを担当大臣に任命。全体で協力しつつ、前向きに参加を検討。
→模擬授業企画をぶつけるか、前年にならい学生ゼミを開催するか。要検討。
■NF祭への出展案
・大変そうなので後ろ向きに検討。
→もし積極的に企画・運営をしたいという人が立候補してくれれば検討。
→期限は9月3日。やるとすれば、模擬授業か外部からゲストを招いての勉強会?
■HPコンテンツの充実化に向けて
・「学問の地図」となるようなブックガイドを作成してはどうか(中山)
→どのレベルで作るかという問題。大分野(経済学、社会学…etc)、中分野(マクロ経済、ミクロ経済、経済思想史…etc)、小分野=テーマ(マルクス、アダム・スミス…etc)。
→作成する個々人の裁量に任せる。夏休み(8月中)をめどに院生を中心に担当を割りふり作成予定。
・HP作成の担当がひとりに集中しがちなので、複数で担当できる体制の構築を進める(夏休み中)
以上です。
もし抜け落ちている点があればご指摘ください。便宜的に勝手に名前使わせてもらいましたが、不都合ある人は連絡ください。すぐに修正します。