
「書評・レビュー」カテゴリーアーカイブ
Kindle Unlimitedスタート! で、学術書は?
夏休みに読みたい おすすめの本18選
映画「シン・ゴジラ」:破局と救済のアンビギュイティ
堀内進之介 『感情で釣られる人々』:カモられないための戦略とは?
ポケモンGOと都知事選
先日日本でも配信が始まったスマートフォン・ゲームアプリ「ポケモンGO」。またたくまに社会現象を巻き起こしており、22日のニューヨーク・タイムズによると、配信初日だけで国内で1000万人の人がアプリをダウンロードしたといいます。東京に住んでいる人のほとんどがポケモンで遊んでいる、と喩えると規模の大きさがわかります。
都知事選の候補も、ポケモンGOの影響力を無視できなかったようです。ある候補者は街頭で、「ポケモンを探しに外に出たついでに(?)投票にも行ってほしい」と呼びかけたほど。完全に話題をポケモンに持って行かれた格好です。
続きを読む
ジジェク『大義を忘れるな』:「他者」に背いて他者を救う
非常識な友情?
本書はスロヴェニア出身の哲学者 スラヴィオ・ジジェクの著作で、内容は、現在グローバルに展開する資本主義、先進諸国で行き詰まりをみせる民主主義の問題について、毛沢東からロベルピエール、スターリン、チェ・ゲバラなどの革命家、そして、フロイト・ラカンやマルクス、ヘーゲル、ハイデガーといった名だたる思想家・哲学者の議論を、彼独特のスリリングな語り口でもって、批判的に吟味しながら検討していきます。
ところで本書にはユニークな謝辞が添えられています。
おもしろいのでそのまま引用しておきます。
続きを読む
高橋哲哉『沖縄の米軍基地』:哲学的な側面から考える
今年4月に沖縄県うるま市で発生した女性殺害遺棄事件。後日、在沖米軍関係者が逮捕されたのを受けて、改めて沖縄の米軍基地の問題に注目が集まっています。
「米軍よりも日本人による犯罪の方がずっと多い」といった声もあるようですが、しかし、事件への注目がもっている象徴的な意味を見過ごしています。ほんとうの問題の核心は、「沖縄に米軍基地が存在する」ということ、これでしょう。
翁長県政の誕生と「オール沖縄」で米軍基地反対の運動が高まるなか出版されたこの本は、沖縄の声に応える形で、在沖米軍基地の県外移設を主張します。なぜ基地を本土が引き受けねばならないのか、そして現実的に可能なのかなど、議論には非常に説得力があります。
ところで、高橋さんは哲学者J.デリダの研究者として有名な方で、本の中でもたびたびデリダの名が出てくるのですが、あくまでも政治的な議論に禁欲されているという印象です。ですが、内容をより深く理解するためにも、今回はあえて哲学的な側面から考えてみることにしましょう。
シャルリ・エブドの否定神学(2):内田樹『他者と死者』書評のポストスクリプト的考察
【承前】こうした意味では、非西洋圏では人権思想や民主主義はある種の「暫定協定(Modus Vivendi)」としてもっぱら機能してきたと考えるのが、おそらく妥当である。それは不可譲という意味で絶対的な価値ではなく、状況次第で変化するほかのさまざまな価値とのバランスのなかで差し当たり採用された、条件つきの価値である。状況によって諸価値の関係性とバランスは変化し、プラグマティックな調整過程のなかで、人権も民主主義もときに最優先の地位から引き下げられる可能性があるということである。いわば「その程度のもの」としての人権であり、民主主義なのである。実際的には、多くの場合、否ほとんどの場合にこれらの基本的諸価値はできる限り擁護されている。それでも、原理的には、それらは不可譲で無条件の価値としては擁護されていないのである。
言論の自由という価値の絶対性――シャルリ・エブド事件のケース
シャルリ・エブドの襲撃事件は、この問題を考えるうえでよいケースである。その後2015年11月により大規模なパリ同時多発テロが発生したために、1月のテロ事件もこれと併せて、国際社会が今後テロの脅威にどう対峙していくかという文脈へと還元されて見られるようになった。けれども、シャルリ事件が、こうした文脈とは別に、日本である種の驚きと違和感をもって受け止められてもいたことはあまり記憶されていない。ヨーロッパの知性にとって言論の自由のような基本的価値がどれほど大きな意味をもつのか、日本のジャーナリズムや文化人はじつは把握しきれていないのではないかという戸惑いが、あのとき一部には見られたのである。
シャルリ・エブドの否定神学(1):内田樹『他者と死者』書評のポストスクリプト的考察
内田樹『他者と死者』の書評の末尾の部分で、評者は次のようなことを示唆した。西洋ではヘブライズムの一神教的伝統が近代社会にあってもどこまでもつきまとうために、そこからの逃走ないし脱構築のポストモダン的実践は、いくらフランス流のエスプリをきかせてもその身振りとは裏腹にどこか深刻なものがついてまわる。この点で、日本のニューアカデミズムの称揚したポップさとそれとはじつは似て非なるものだったのではないか、と。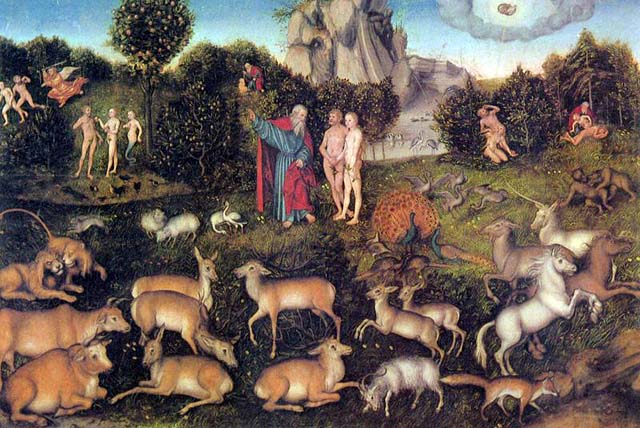
だとすれば、近代の普遍性をまずは額面通りに受けとらず、その文化的・文明的なバックグラウンドに慎重に目をむけることがなお必要だというべきである。ここでは、こうした点についての簡単な考察を行ってみたい。世俗性を表看板とする近代社会を非西洋圏で確立させるうえで、キリスト教への「改宗」がそのための要件とはされていないのはもちろんである。しかし、少なくとも西洋世界の一神教的背景を知っていなければ、世俗的な理念――人権や民主主義――にたいして彼らが示す、ほとんど宗教的に映じるほどの強いコミットメントの源泉は理解できないだろう。
世俗化された近代的理念が、しかしある面では絶対的で超越的な価値として理解されていると考えなければ、たとえばシャルリ・エブド周辺のジャーナリストたちが示した「蛮勇」の本質はとらえることができない。自己保存を旨とする個人のもっぱら合理的な選択の結果として正義を考えるのでは、自己の生命を大きな危険にさらしてでもこの種の価値の実現に奉仕しようとする人びとの行動は、とても説明できないからである。 続きを読む




